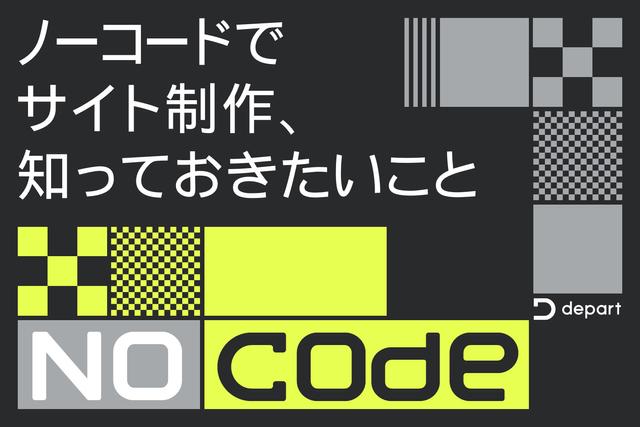- Share On
目次
Webサイトやアプリケーションで一貫したユーザー体験(UX)を提供するために不可欠な「デザインシステム」は、プロダクトの品質と開発効率を両立させる仕組みとして重要な役割を担っています。
さらに近年では、AIがデザインやコーディングに参加することが当たり前になり、デザインシステムが人間同士の「共通言語」であるだけでなく、AIがデザインの意図やルールを正確に理解し、一貫性のあるアウトプットを生み出すための「設計図」としての役割も担い始めており、その重要性はますます高くなっています。
この記事では、デザインシステムの重要性を解説するとともに、これからデザインシステムを構築・改善する上で、非常に参考になる国内外の優れた公開事例をご紹介します。
デザインシステムとは?
デザインシステムとは、「高品質なプロダクトを、効率よく、一貫して作り続けるための仕組み」です。Webサイトやアプリケーションの開発における「共通のルールブック」と、「再利用可能な部品」がセットになったもの、とイメージすると分かりやすいでしょう。
具体的には、以下のような要素を体系的にまとめたものです。
1. デザイン原則・思想
考え方や「らしさ」を定義する、デザインの判断基準をまとめたドキュメント
2. スタイルガイド
カラー、タイポグラフィ、スペーシング、アイコンなど、デザインの具体的なルール集
3. パターンライブラリ(UIコンポーネントライブラリ)
スタイルガイドに基づいて作られた、再利用可能なデザインの「部品」集(例:ボタン、入力フォーム、ヘッダーなど)
デザインデータとソースコードがセットで管理される
このほかにも、プロダクト内で使われる言葉や文章に関するガイドラインや、ブランドガイドライン、インタラクションにおけるルールなどもデザインシステムに含まれている場合があります。
デザインシステムの目的
これらの仕組みが整備されていることで、特定の誰かの知識や感覚に依存することなく、一貫した品質でプロダクトの開発や運用をすることができます。
デザインシステムは、デザイナー、エンジニア、プロダクトマネージャーなど、プロジェクトに関わる全員が「共通言語」で会話し、一貫性のあるプロダクトを効率的に開発し続けるための「信頼できる唯一の情報源」として機能するのです。
なぜいまデザインシステムが重要なのか
デザインシステムは、これまで主にデザイナーとエンジニアの「共通言語」として機能してきました。しかしこれからは、AIが開発に参加するための「共通言語」としても極めて重要な役割を担います。
AIがデザインカンプからコードを生成したり、既存のコンポーネントを組み合わせて新しい画面を提案したりする際、その基盤となるのがデザインシステムです。ルールやコンポーネントが整備されていなければ、AIは一貫性のあるアウトプットを生み出せません。
つまり、デザインシステムを整備することは、プロダクト開発におけるAI活用の価値を最大化するための鍵となります。
AIと親和性の高い「AIフレンドリー」なデザインシステムの構築については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。
優れたデザインシステム事例
国内外の多くの企業が自社のデザインシステムを公開しており、その思想やコンポーネントを参考にすることができます。ここでは、特に参考になる事例を国内・海外に分けてご紹介します。
国内の優れたデザインシステム事例10選
Spindle | CyberAgent
「つくる、つむぐ、つづく、」という思想を掲げ、"Amebaらしさ"を一貫してユーザーに届けるためのデザインシステムです。Amebaを始めとする大規模メディアサービス群を支えており、多様なサービスを抱える企業が、いかにしてユーザーの信頼につながる一貫性を保つかという点で非常に参考になります。アクセシビリティやパフォーマンスに関する原則も明確に定義されており、コンポーネントやアイコンはGitHubで公開されています。
 出典:Spindle
出典:Spindle
SmartHR Design System | SmartHR
「だれでも・効率よく・迷わずに」を掲げ、B2B SaaSのお手本とも言える包括的なデザインシステムです。プロダクトUIだけでなく、マーケティングやセールスで使うコミュニケーション資料まで、一貫した「SmartHRらしさ」を届けるための原則や要素が定義されています。特にアクセシビリティへの徹底したこだわりが特徴で、具体的なガイドラインも充実しており、あらゆるユーザーにとっての使いやすさを追求する姿勢が学べます。
デジタル庁デザインシステム | デジタル庁
デジタル庁のミッションである「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を。」をデザイン面から支える、公共のためのシステムです。「使いやすい」行政サービスを実現するための設計思想やUIコンポーネントが整備されています。特にアクセシビリティに関する詳細なガイドラインは、行政サービスのみならず、公共性が求められるあらゆるWebサイトやアプリケーション開発において参考にできる内容です。
LINE Design System | LINE
LINEアプリ本体(メッセンジャー)用と、金融・エンタメなど多岐にわたるグローバルファミリーサービス用の、2つのガイドラインで構成されるデザインシステムです。世界中の膨大なユーザーに対し「LINEらしさ」を備えた一貫したユーザー体験(UX)を提供するため、デザイン原則(Principles)やUXガイドラインが体系化されています。多様な事業ドメインを横断しながら、いかにして統一されたデザイン言語でブランドの一貫性を保つかという点で、非常に参考になる包括的なシステムです。
Ubie Vitals | Ubie
医療プラットフォーム「Ubie」のプロダクトUIのためのデザインシステムです。医療・ヘルスケアというドメインの特性上、デザイン原則として特に「信頼できる」「わかりやすい」ことを最重要視しています。命に関わる情報を扱うからこそ、ユーザーの誤解を防ぎ、絶対的な信頼性を確保するための設計思想が貫かれており、サービスが持つ責任をデザインでどう体現するかの模範例と言えます。
 出典:Ubie Vitals
出典:Ubie Vitals
sugao | カオナビ
タレントマネジメントシステム「カオナビ」のプロダクトデザインシステム。「個」の力が開かれ、誰もが活躍できる未来を目指すというブランドの哲学が、デザイン原則にまで一貫して反映されています。ブランドの個性を鮮明にしつつ、使いやすい体験を提供するというアプローチは、コンセプトの作り方として非常に参考になります。
 出典:sugao
出典:sugao
Inhouse | GMOペパボ
複数の個性豊かなサービスを展開しながら、全体のデザイン品質と開発効率を向上させるために作られた共通基盤デザインシステム。各ブランドの独自性を尊重しつつ、共通化できる部分はコンポーネントとして提供する柔軟なアプローチは、多角的な事業を持つ企業が抱える課題へ向き合うの良い事例です。
 出典:Inhouse
出典:Inhouse
kamii | ラクスル
印刷・集客のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」のデザインシステム。印刷という伝統的な産業を、テクノロジーで再構築するプラットフォームの基盤となっている。複雑な取引構造のプラットフォームを誰にとってもシンプルで直感的な体験へと変えるための工夫が見られます。
 出典:kamii
出典:kamii
Serendie Design System | 三菱電機
総合電機メーカーである三菱電機が、多様な事業領域(BtoC製品から複雑な産業用BtoBシステムまで)に一貫した体験を提供するために構築したデザインシステムです。伝統的なモノづくり文化に寄り添いつつも、実験的で新しいサービスをスピーディーに生み出す「軽やかで柔軟なプロダクトづくり」の基盤となることを目指しています。各事業の独自性を尊重しつつ全体の骨格として機能させる、大企業ならではの柔軟なアプローチが非常に参考になります。
Sparkle Design | グッドパッチ
UI/UXデザインカンパニーであるグッドパッチが、多様なクライアントワークを通じて培ってきた実践的な知見を集約したデザインシステムです。共通部品の設計コストを削減し、チームが「プロダクトの体験設計」という本質的な課題解決に集中できる環境を作ることを目指しています。新規事業の立ち上げや既存事業のリニューアルの「ベース」として活用でき、これからデザインシステムを構築するチームにとって、非常に実践的なお手本となります。
海外の優れたデザインシステム事例10選
Material Design | Google
Googleが開発した、Androidアプリの公式ガイドラインであり、世界で最も広く採用されているデザインシステムの一つです。近年では「Material You」へと進化し、ユーザーの壁紙から動的にカラーを抽出する「Dynamic Color」など、高度なパーソナライゼーション(個別最適化)を実現。単なるガイドラインに留まらず、あらゆるプラットフォームで一貫しつつも、個人の好みに寄り添う表現力豊かな体験を構築するための、包括的な思想とツールを提供しています。
Human Interface Guidelines | Apple
iOSやmacOSなど、Appleのエコシステム全体にわたる卓越したユーザー体験の根幹をなすガイドラインです。個々のUIコンポーネントの仕様だけでなく、「Clarity(明瞭さ)」や「Deference(尊重)」といった、プラットフォームとアプリがシームレスに調和するための普遍的なデザイン原則を提示しているのが特徴です。ユーザーが直感的に操作できる世界観を実現するための哲学が貫かれており、あらゆるデザイナーにとって必読のドキュメントです。
Fluent UI | Microsoft
WindowsやMicrosoft 365など、Microsoftの多岐にわたる製品群のデザイン原則であり、クロスプラットフォーム(Web、Windows、iOS、Android等)でのシームレスな体験を目指すシステムです。光、動き、奥行きといった物理的な要素を取り入れたデザインが特徴で、プラットフォームを問わずユーザーが自然で直感的に操作できる、「生産性」の高いアプリケーション開発の実践的な指針とコンポーネントを提供しています。
 出典:Fluent UI
出典:Fluent UI
Lightning Design System | Salesforce
世界的なCRMプラットフォームであるSalesforceのデザインシステムです。「Clarity(明快さ)」「Efficiency(効率性)」など4つの原則を掲げ、複雑な業務データを扱うエンタープライズ向けソフトウェアに、美しさと効率性をもたらします。膨大な情報を整理し、ユーザーがタスクに集中できるよう設計されたコンポーネント群は、B2B/SaaSプロダクトを開発する上で非常に優れた手本となります。
Spectrum | Adobe
PhotoshopやIllustratorなど、プロのクリエイターが使用する多種多様なツール群に、一貫した体験を提供するためのAdobeのデザインシステムです。各ツールの高度な専門性を尊重しつつ、共通の操作感やルック&フィールを実現する、論理的でスケーラブル(拡張可能)な設計が特徴です。複雑な製品ポートフォリオを持つ企業にとって、必見の事例と言えます。
 出典:Spectrum
出典:Spectrum
Polaris | Shopify
世界最大級のEコマースプラットフォームShopifyが、ストアオーナーのビジネス成功を第一に考えて設計したデザインシステムです。単なるUIキットに留まらず、コンバージョン率を高めるためのコンテンツガイドラインやデザインパターンといったベストプラクティスが豊富に含まれており、Eコマースサイトを構築する上で非常に実践的な内容となっています。
 出典:Polaris
出典:Polaris
Carbon Design System | IBM
100年以上にわたるIBMのデザイン哲学と経験が凝縮された、オープンソースのデザインシステムです。特にアクセシビリティは同業界でも高い水準で配慮されており、大規模でミッションクリティカル(基幹業務)なシステムを、誰もが確実に利用できるようにするための堅牢な基盤を提供しています。
Atlassian Design System | Atlassian
JiraやConfluenceなど、世界中のチームの共同作業(コラボレーション)と生産性を支えるツール群のデザインシステムです。チームがよりスマートに働けるよう、複雑なワークフローをシンプルに見せるための実践的なUI/UXの知見が豊富に盛り込まれており、多くのプロダクト開発で参考になります。
Base design system | Uber
配車サービスからフードデリバリーまで、グローバルに展開するUberの多角的な事業を、一貫したブランド体験で束ねるためのシステムです。言語や文化を超えて機能する普遍的な分かりやすさを追求し、モーションデザインなども効果的に活用することで、シンプルかつ直感的な操作性を実現しています。
Helios | Spotify
音楽ストリーミング企業のSpotifyが、急成長する組織の中で開発スピードとデザインの一貫性を両立させるために再構築した新しいデザインシステム(旧称Encore)です。デザイントークンを全面的に採用し、複数のプラットフォームへ効率的にデザインを展開する現代的なアプローチは、スケールするプロダクト開発を目指す多くのチームにとって、大きな学びが得られます。
 出典:Helios
出典:Helios
まとめ
これまでデザインシステムは、事業の拡大やサービス改善のタイミングで、主に「中長期的な投資」として導入される傾向がありました。一貫したブランド体験(UX)の構築や、将来的な開発効率の向上といった、未来へのリターンを期待する側面が強かったと言えます。
しかし、AIが本格的に開発プロセスに参加し始めた今、その位置づけは大きく変わりつつあります。デザインシステムは従来の「中長期的な資産」であると同時に、「AIの能力を引き出し、開発効率を“すぐに”高めるための短期的な施策」という、即時性の高い価値も併せ持つようになりました。
一貫したユーザー体験の提供という従来からの目的に加え、これからはAIとの協業を前提としたプロダクト開発の基盤として、デザインシステムは不可欠な存在となるでしょう。
未来の開発スタイルで優位に立つためにも、今回ご紹介した事例を参考に、自社のデザインシステムの構築や見直しを検討してみてはいかがでしょうか。
Contact
制作のご依頼やサービスに関するお問い合わせ、
まだ案件化していないご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
- この記事をシェア





 出典:
出典: 出典:
出典: 出典:
出典: 出典:
出典: 出典:
出典: 出典:
出典: 出典:
出典: 出典:
出典: 出典:
出典: 出典:
出典: 出典:
出典: