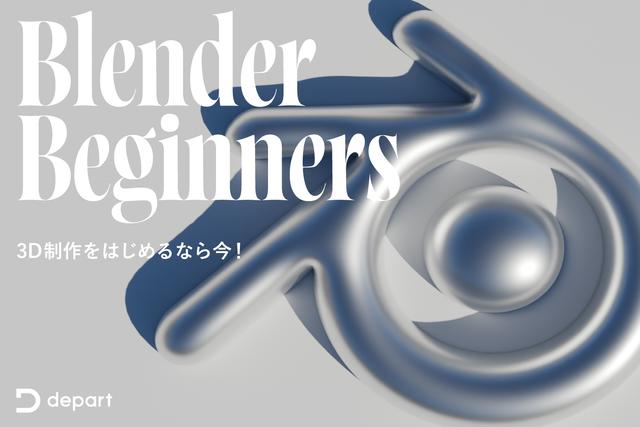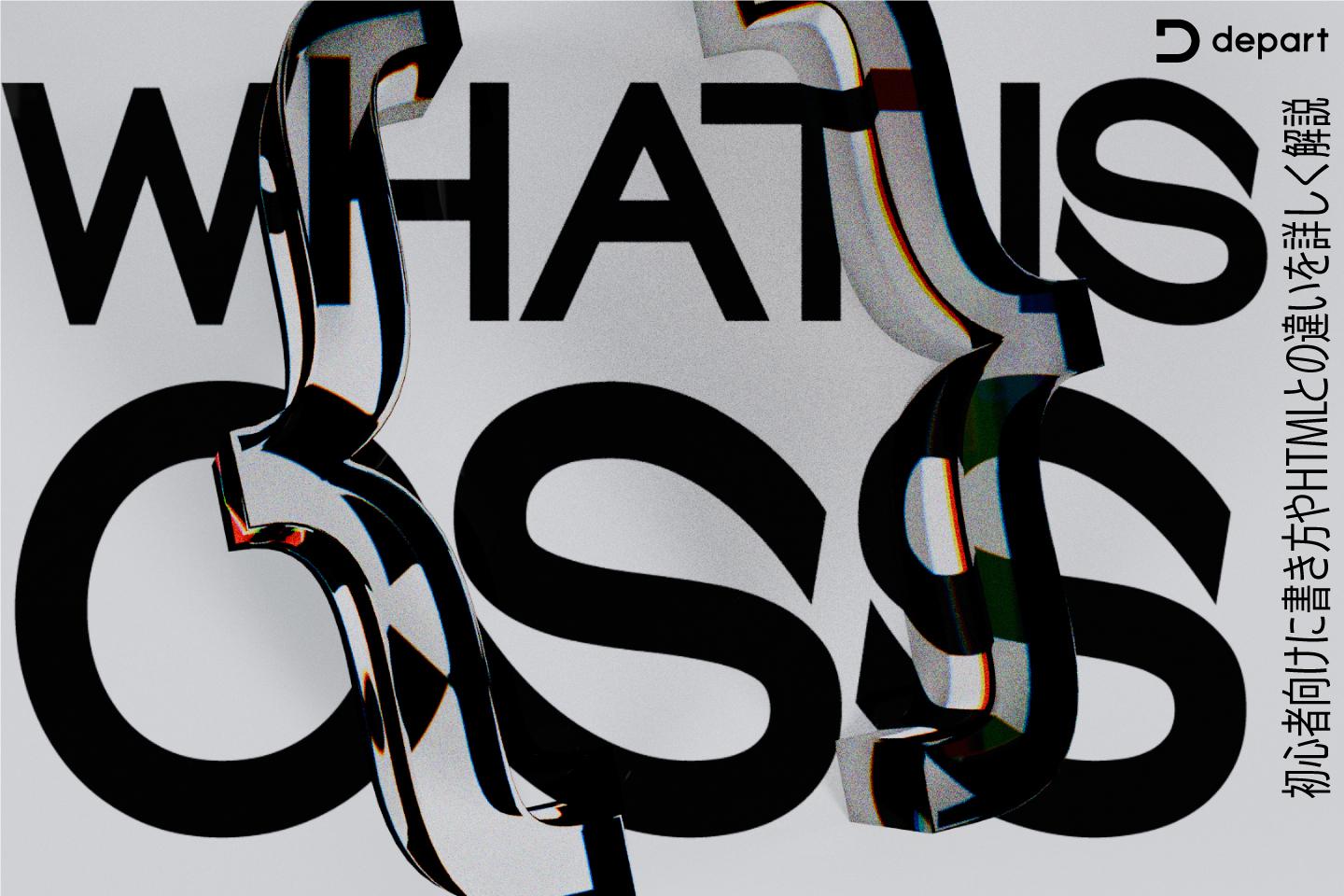
- Share On
目次
目次
- CSSとはWebページの見た目を整える言語
- HTMLとCSSの役割分担を理解しよう
- HTMLはWebページの構造を定義するマークアップ言語
- CSSがないとWebページは文字と画像の羅列になる
- CSSでWebページをデザインする3つのメリット
- Webサイト全体のデザインに統一感を持たせられる
- HTMLの記述がシンプルになり修正や管理がしやすくなる
- デバイスごとに表示を最適化できるレスポンシブデザインに対応可能
- CSSを構成する3つの基本要素
- どの部分のデザインを変えるか指定する「セレクタ」
- どんなデザイン項目を変えるか指定する「プロパティ」
- どのようにデザインを変えるか指定する「値」
- CSSを記述する3つの場所とそれぞれの特徴
- HTMLタグに直接書き込むインラインスタイル
- HTMLのhead内にまとめて記述する内部スタイルシート
- 専用ファイルで管理する外部スタイルシート
- これだけは覚えたい!基本的なCSSプロパティの例
- 文字の色や大きさを変更するプロパティ
- 背景の色や画像を指定するプロパティ
- 余白や配置を調整するプロパティ
- 初心者におすすめのCSS学習ステップ
- まずは学習サイトや本で基本の書き方を学ぶ
- 簡単なWebサイトのデザインを真似てコーディングしてみる
- オリジナルのデザインでWebページを作成する
- まとめ
CSSとは、Webサイトの「見た目」を整えるための言語であり、HTMLと組み合わせて使うことで、はじめてページが「きちんとしたデザイン」として成立します。
HTMLがWebページの「構造」を定義するのに対し、CSSは「どのように表示するか」を指示する、いわばデザイン担当の役割を持っています。
この記事では、HTMLとCSSの違いや、HTMLにCSSを適用する手順、そしてCSSを指定するための基本的な使い方などを、これからWeb制作や運用に携わる方にもわかりやすく解説します。
「なぜCSSが必要なのか」「CSSの役割は何なのか」を理解しながら、実際に使えるコード例や設定方法も紹介していきます。
CSSとはWebページの見た目を整える言語
CSSは「Cascading Style Sheets(カスケーディング・スタイル・シート)」の略で、Webページの見た目を整えるための言語です。
HTMLが「文章や画像の構造」を決めるのに対し、CSSは「その構造をどのように見せるか」を定義します。つまり、HTMLが設計図ならCSSはデザイン図面にあたります。
CSSを指定することで、文字の色や大きさ、背景色、レイアウトなどを細かく制御できる
HTMLとCSSを分けて管理することで、デザイン変更やメンテナンスが簡単になる
Webサイト全体の統一感を保ちながら、ブランドらしさを演出できる
たとえば、HTMLで文章を定義し、CSSを指定するだけで印象はまったく変わります。
<!-- HTML -->
<p>株式会社デパートは東京都に本社を置くWeb制作会社です。</p>/* CSS */
p {
color: #ff0000;
font-size: 24px;
line-height: 1.8;
margin: 0px 0px 24px;
}同じHTMLでも、CSSを適用するだけで「読みやすく、整ったWebページ」に変わります。
CSSの役割は、単に見た目を美しくすることではなく、情報をわかりやすく伝える手段でもあるのです。
HTMLとCSSの役割分担を理解しよう

Webページの制作では、HTMLの役割とCSSの役割を明確に区別して考えることが基本です。
どちらも重要ですが、混同してしまうとコードが複雑になり、修正や運用に手間がかかります。
HTMLの役割:文書構造(見出し、段落、リスト、リンクなど)を定義する
CSSの役割:構造に対して装飾や配置などの見た目を指定する
HTML使い分けとCSS指定を意識することで、見通しの良いコードになる
この分離を意識すると、Webページの再利用性や保守性が格段に高まり、後からのデザイン変更にも柔軟に対応できるようになります。
HTMLはWebページの構造を定義するマークアップ言語
HTML(HyperText Markup Language)は、Webページの骨格となる「構造」を定義するための言語です。
文章の意味を明確にし、見出しや段落、リストなどを「HTMLタグ」で表現します。
HTML定義の基本:
<h1>〜<h6>(見出し)、<p>(段落)、<a>(リンク)、<img>(画像)などHTML役割の理解:情報の意味を伝えることが目的で、見た目はCSSで制御する
HTML手順の流れ:①構造設計 → ②HTMLタグで記述 → ③CSSでデザインを付与
例えば以下のHTML構造を定義し、あとからCSSで見た目を指定します。
<section>
<h2>会社概要</h2>
<dl>
<dt>代表取締役社長</dt>
<dd>田中 太郎</dd>
<dt>所在地</dt>
<dd>東京都新宿区…</dd>
</dl>
</section>この時点ではただのテキストですが、ここにCSSを指定することで、見出しや余白、フォントが整い、情報が整理されたWebページになります。
CSSがないとWebページは文字と画像の羅列になる
CSSを無効にすると、Webページは文字と画像がただ並んだだけの状態になります。
すべてのテキストが同じ大きさ・色で表示され、どこが重要なのかがわからなくなります。
 左:HTMLのみ 右:CSSで装飾
左:HTMLのみ 右:CSSで装飾
見出しや本文の違いがなく、視覚的に読みづらい
余白(marginやpadding)がなく、ページ全体が詰まった印象になる
情報の構造が理解しづらく、ユーザーが離脱しやすい
CSSは装飾ではなく、「読みやすさを設計するための道具」です。
デザインの違いが情報の優先順位を明確にし、ユーザー体験を向上させます。
CSSでWebページをデザインする3つのメリット
Web制作でCSSを使う最大のメリットは、デザインの一括管理と保守のしやすさにあります。
ページ数が多いサイトほど、CSSの効果が大きくなります。
Webサイト全体のデザインに統一感を持たせられる
外部CSSを1つにまとめると、Webサイト全体の見た目を統一できます。
会社のブランドカラーやフォントをCSSで指定しておけば、すべてのページに同じ印象を与えられます。
企業サイトの統一感を保てる
変更箇所を一括で修正できる
ページごとのズレや差異が減る
この仕組みによって、どのページを見ても「同じ会社のWebサイト」としての一貫性が保たれます。
HTMLの記述がシンプルになり修正や管理がしやすくなる
CSSをHTMLから切り離すと、HTMLは構造定義に集中でき、コードがすっきりします。
CSSにスタイルを集約すれば、修正作業もスムーズになります。
HTMLタグが短くなり、可読性が上がる
修正はCSSファイル1箇所で完結
余白などをまとめて調整できる(例:
margin: 0px auto;)
こうした「構造と見た目の分離」は、長期運用を見据えたWeb制作に欠かせない考え方です。
デバイスごとに表示を最適化できるレスポンシブデザインに対応可能
CSSでは、デバイスの幅に応じてスタイルを切り替えることができます。
これを「メディアクエリ」と呼びます。
.container { width: 80%; margin: 0px auto; }
@media (max-width: 768px) {
.container { width: 100%; padding: 0px 16px; }
}スマートフォンやタブレット、PCなど、どのデバイスでも見やすいWebページを1つのHTMLで実現できます。
これにより、メンテナンスコストを抑えながら、快適な閲覧体験を提供できます。
CSSを構成する3つの基本要素
CSSは「セレクタ」「プロパティ」「値」の3つの要素で成り立っています。
これを理解すれば、どんなWebページでも自在にデザインをコントロールできます。
どの部分のデザインを変えるか指定する「セレクタ」
セレクタは、どのHTMLタグや要素にスタイルを適用するかを指定します。
タグ名セレクタ:
p,h1,ulなどクラスセレクタ:
.btn,.cardなど、複数の要素に使えるIDセレクタ:
#header、#footerなど、特定の要素に1回だけ適用
p { color: #333; line-height: 1.8; margin-bottom: 16px; }どこにCSSを指定するかを的確に選ぶことで、管理がしやすく、変更の影響範囲も把握しやすくなります。
どんなデザイン項目を変えるか指定する「プロパティ」
プロパティは、「何を変えるか」を示す部分です。
文字系:
color,font-size,line-height背景系:
background-color,background-image配置系:
display,position,flex余白系:
margin,padding,gap
これらを組み合わせて使うことで、Webページ全体のデザインを自由に構成できます。
どのようにデザインを変えるか指定する「値」
値は、プロパティの具体的な設定内容です。
単位(px、%、emなど)や色指定(#333、rgb()など)を指定します。
.container {
width: 80%;
margin: 0px auto;
background-color: #fafafa;
}値の理解が進むと、「見た目を意図的にコントロールする力」が身につきます。
CSSを記述する3つの場所とそれぞれの特徴
CSSは、書く場所によって3種類の方法があります。
目的や規模に合わせて使い分けましょう。
インラインスタイル:HTMLタグ内に直接書く
内部スタイルシート:HTMLの
<style>内に書く外部スタイルシート:別ファイル(.css)を読み込む
HTMLタグに直接書き込むインラインスタイル
<p style="color:#0a7cff; margin-top:8px;">お知らせを更新しました。</p>メリット:その場で簡単に変更できる
デメリット:スタイルが分散し、管理しづらい
一時的な変更やテストには便利ですが、長期運用には不向きです。
HTMLのhead内にまとめて記述する内部スタイルシート
<head>
<style>
.lp-title { color:#222; font-size:24px; margin:0px 0px 16px; }
</style>
</head>メリット:1ページで完結するため簡単
デメリット:他のページに再利用できない
単体ページやメールテンプレートなど、小規模なコンテンツで使われます。
専用ファイルで管理する外部スタイルシート
<link rel="stylesheet" href="/css/style.css">メリット:複数ページで共有でき、保守性が高い
デメリット:ファイル分割と読み込み設計が必要
外部化することで、Webサイト全体の更新がしやすくなり、変更時のリスクを減らせます。
(補足)比較の目安
横にスクロールできます
方法 | 向き/規模 | 運用性 | 代表的な用途 |
|---|---|---|---|
インライン | 極小 | 低 | 緊急修正、検証 |
内部スタイルシート | 小 | 中 | LP、HTMLメール |
外部スタイルシート | 中〜大 | 高 | コーポレート/サービス全般 |
これだけは覚えたい!基本的なCSSプロパティの例

CSSには数多くのプロパティがありますが、まずはよく使う基本的なものから覚えましょう。
これだけでも多くのWebページがデザインできます。
テキスト:
color/font-size/font-weight/line-height背景:
background-color/background-image/background-size余白・枠:
margin/padding/border/border-radiusレイアウト:
display(flex/grid)/gap/align-items/justify-content
文字の色や大きさを変更するプロパティ
p {
color: #333;
font-size: 16px;
line-height: 1.8;
}
h2 {
font-size: 24px;
color: #111;
margin: 0px 0px 16px;
}読みやすさを保ちながら、見出しと本文の階層を意識して設定することが大切です。
背景の色や画像を指定するプロパティ
.hero {
background-color: #f5f7fa;
background-image: url('/images/bg.jpg');
background-size: cover;
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
}背景設定を工夫することで、ページの印象を大きく変えられます。
ブランドカラーを背景に使えば、統一感も出せます。
余白や配置を調整するプロパティ
.section { padding: 40px 0px; }
.card {
padding: 16px;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 12px;
margin: 0px auto;
width: 80%;
}margin: 0px auto;は中央寄せの基本形です。
0pxなど具体的な数値を明示することで、他の開発者にも意図が伝わりやすくなります。
初心者におすすめのCSS学習ステップ
CSSを学ぶ際は、段階的に理解を深めていくのが効率的です。
「基本を学ぶ → 既存サイトを真似る → 自分のページを作る」という流れが特に効果的です。
まずは学習サイトや本で基本の書き方を学ぶ
HTMLとCSSの関係(構造と見た目の違い)を理解する
セレクタ・プロパティ・値の書き方を覚える
実際にブラウザで結果を確認しながら進める
ProgateやMDNなどの学習サービスを活用すると、試しながら学べます。
重要なのは、理解より「慣れ」です。CSSは書いてみることで身につきます。
簡単なWebサイトのデザインを真似てコーディングしてみる
既存サイトを参考に、自分でHTMLとCSSを書いて再現してみましょう。
この「模写コーディング」は実務に最も近い練習です。
ページ構造を観察し、どのHTMLタグにCSSが当たっているか考える
完成度は80%を目指す(完璧でなくてよい)
どのプロパティがどの見た目に影響しているかを確認する
これを繰り返すことで、実務で通用するデザイン力が自然に身についていきます。
オリジナルのデザインでWebページを作成する
最後に、自分で1ページのWebサイトを設計・制作してみましょう。
テーマは自己紹介ページでも企業紹介でも構いません。
HTML構造を考え、CSSで色や余白を調整
スマートフォンにも対応できるようレスポンシブ化
作成したページを公開して動作を確認
この段階を経験することで、HTMLとCSSの使い分けや役割の違いがより深く理解できます。
まとめ
CSSは、HTMLで定義した構造に見た目を与えるための言語です。
HTMLが情報を整理する役割を持つのに対し、CSSはその情報を伝わりやすく、魅力的に表現するためのツールです。
HTMLの役割:Webページの構造を定義
CSSの役割:デザイン・色・レイアウトを指定
HTMLにCSSを指定することで、統一感のあるWebサイトが構築できる
外部スタイルシートを使うと、管理や運用が格段に効率化できる
まずは基本的なCSSの書き方を理解し、小さな修正や改善から始めてみましょう。
構造とデザインを分けて考える習慣がつけば、運用時のトラブルを減らし、より高品質なWebサイトを保てます。
株式会社デパートでは、Webサイトの更新や改修を想定した“運用しやすいCSS設計”や、既存サイトのスタイル見直し・設計整理、デザインシステム化(ガイドライン整備)のご相談も承っています。共通部分のみや、特定のページのみでもお気軽にご相談ください。
Contact
制作のご依頼やサービスに関するお問い合わせ、
まだ案件化していないご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
- この記事をシェア