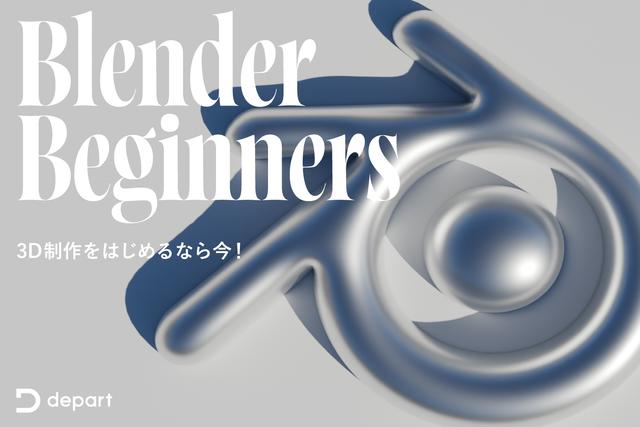- Share On
目次
目次
- ESGとは?3つの要素(環境・社会・ガバナンス)を解説
- 環境(Environment):気候変動や資源問題への取り組み
- 社会(Social):人権や地域社会への貢献
- ガバナンス(Governance):透明性の高い企業経営
- ESGとサステナビリティの違いは?
- サステナビリティとは
- ESGとは
- 両者の関係性
- ESGとSDGsやCSRは何が違う?それぞれの関係性を解説
- SDGsとの違い:投資家の視点か、世界共通の目標か
- CSRとの違い:投資判断の指標か、企業の社会的責任か
- SRIとの違い:企業の持続的成長を重視するか、倫理的観点を重視するか
- ESG経営が世界的に注目されるようになった3つの背景
- 背景1:地球規模の環境・社会問題の深刻化
- 背景2:投資家の価値観の変化と長期的なリターンの追求
- 背景3:年金基金などの大規模な機関投資家による採用
- 企業がESG経営に取り組む4つのメリット
- メリット1:新たな資金調達の機会が広がる
- メリット2:企業のブランドイメージと価値が向上する
- メリット3:事業リスクの低減と経営の安定化につながる
- メリット4:優秀な人材の獲得と従業員の定着につながる
- 代表的なESG投資の7つの手法
- ネガティブ・スクリーニング:特定の業界を投資対象から除外する手法
- ポジティブ・スクリーニング:ESG評価が高い企業を選別して投資する手法
- 規範に基づくスクリーニング:国際的な規範を基準に投資先を選定する手法
- ESGインテグレーション:財務情報に加えてESG要素も分析に組み込む手法
- サステナビリティ・テーマ投資:持続可能性に関するテーマに投資する手法
- インパクト投資:社会的・環境的な課題解決への貢献度を重視する手法
- エンゲージメント・議決権行使:株主として企業に積極的に働きかける手法
- ESG経営に取り組む上での課題と注意点
- 評価基準が統一されておらず判断が難しい
- 短期的な収益に結びつきにくい場合がある
- コストの増加や専門知識を持つ人材が必要になる
- 【分野別】国内企業のESGへの取り組み事例
- 【環境】再生可能エネルギーの導入とサプライチェーン全体のCO2削減
- 【社会】多様な人材の活躍推進と働きやすい職場環境の整備
- 【ガバナンス】社外取締役の増員による経営の透明性向上
- まとめ
近年、企業の持続的な成長には、財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの要素を考慮した経営が不可欠とされています。この3つの頭文字を取った「ESG」は、企業が長期的に成長し、持続可能な社会を実現するために重要な考え方です。
本記事では、ESGの意味や、企業がESGに取り組むメリット、SDGsやCSRといった関連用語との違いを解説し、具体的な企業の取り組み事例も紹介します。
ESGとは?3つの要素(環境・社会・ガバナンス)を解説

ESGは(読み方:イーエスジー)と読み、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の頭文字を組み合わせた言葉です。 簡単に言うと、企業が持続的に成長するために必要な「環境・社会・ガバナンス」の3つの観点を示しており、企業が社会に対して負う責任も意味しています。 ESGについて、それぞれの要素を詳しく見ていきましょう。
環境(Environment):気候変動や資源問題への取り組み
環境は、企業活動が地球環境に与える影響と、それに対する取り組みを指します。 具体的には、気候変動への対策として温室効果ガス排出量の削減や再生可能エネルギーの導入、水資源の有効活用、廃棄物の削減、リサイクル推進、生物多様性の保護などが含まれます。 例えば、環境省が推進するような環境負荷低減の取り組みは、企業の持続可能性を高めるだけでなく、環境問題の解決にも貢献します。 環境への配慮は、企業のサプライチェーン全体で求められており、環境に優しい製品・サービスの開発も重要な要素です。
社会(Social):人権や地域社会への貢献
社会(Social)は、企業が従業員、顧客、取引先、地域社会といったあらゆるステークホルダーに対して果たすべき責任と貢献を意味します。具体的には、人権の尊重、多様な人材の活用(ダイバーシティ&インクルージョン)、安全で働きやすい職場環境の整備、労働条件の改善、ハラスメント防止、地域社会への貢献、サプライチェーンにおける人権問題への対応などが挙げられます。
これらの取り組みは、企業の社会的評価を高め、持続可能な社会の実現に寄与します。
ガバナンス(Governance):透明性の高い企業経営
ガバナンスは、企業が健全で透明性の高い経営を行うための管理体制を指します。 具体的には、法令遵守の徹底、適切な情報開示、独立した役員を含む取締役会の構成、内部監査・外部監査による経営の健全性チェック、株主との対話などが含まれます。 透明性の高い企業経営は、不正リスクを低減し、投資家やステークホルダーからの信頼を獲得するために不可欠な要素です。
ESGとサステナビリティの違いは?
ESGとあわせてよく使われる言葉に「サステナビリティ(Sustainability)」があります。両者は似た文脈で用いられますが、焦点や使われ方に違いがあります。
サステナビリティとは
サステナビリティは「持続可能性」を意味し、社会全体や地球規模で環境・社会・経済のバランスを保ちながら未来世代に負担を残さない考え方を指します。政府、国際機関、NPO、個人など幅広い主体が関わります。

近年、「サステナビリティ」という言葉を耳にする機会が増えました。環境問題や社会課題の深刻化を背景に、企業活動においても持続可能な社会の実現への貢献が強く求められています。ここでは、サステナビリティとは何か、その基本的な意味から、企業が取り組むメリット、そして参考になるメディアやポータルサイトまで、分かりやすく解説します。
ESGとは
ESGはその考え方を企業経営や投資の現場で実践的に評価するためのフレームワークです。特に投資家が企業の持続可能性を測る指標として活用されることが特徴です。
両者の関係性
つまり、サステナビリティは大きな方向性や社会全体の目標を示し、ESGは企業がそれを実現するための具体的な行動や評価軸と捉えると分かりやすいでしょう。
ESGとSDGsやCSRは何が違う?それぞれの関係性を解説
ESGと混同されやすい概念として、SDGsやCSRが挙げられます。 これらの用語はすべて持続可能性に関連していますが、その目的や視点には違いがあります。 それぞれの関係性を理解することで、ESGの全体像をより深く把握できます。
SDGsとの違い:投資家の視点か、世界共通の目標か
SDGs(持続可能な開発目標)は、2015年の国連サミットで採択された世界共通の目標であり、貧困や飢餓の撲滅、気候変動対策など17の目標と169のターゲットから構成されています。SDGsとは、社会全体が目指すべき指針であり、企業だけでなく政府、NPOなどあらゆる主体がその達成に貢献することが求められます。
一方、ESGは投資家が企業の持続可能性を評価するための指標であり、投資判断の基準として用いられることが多いです。しかし、ESG経営がSDGsの達成に貢献するなど、両者には密接な関係があります。
CSRとの違い:投資判断の指標か、企業の社会的責任か
CSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)は、企業が事業活動を通じて社会や環境に与える影響に対して負う責任を指します。CSRは、企業が自主的に行う社会貢献活動や環境保護活動など、幅広い取り組みを含みます。
一方、ESGは投資家が企業の持続可能性を評価する際の指標であり、特に「投資判断の指標」としての側面が強調されます。CSRは企業の倫理的側面を重視するのに対し、ESGはより具体的に「環境」「社会」「ガバナンス」という要素に焦点を当て、長期的な企業価値向上への影響を評価します。
SRIとの違い:企業の持続的成長を重視するか、倫理的観点を重視するか
SRI(Socially Responsible Investment:社会的責任投資)は、投資家が財務的リターンだけでなく、倫理的・社会的な観点も考慮して投資先を選定する手法です。 SRIは、たばこや武器製造といった特定の業界を投資対象から除外するなど、倫理的観点を重視する傾向があります。
これに対し、ESG投資は企業の「持続的成長」を重視し、サステナビリティ(Sustainability)への貢献度をより広範な視点で評価します。 SRIはESG投資よりも歴史が古く、両者は似た意味で使われることもありますが、ESGがより具体的な評価項目を持つ点で異なります。
ESG経営が世界的に注目されるようになった3つの背景
 ESG経営は、近年世界的に注目を集めています。 その普及の背景には、地球規模の環境・社会問題の深刻化、投資家の価値観の変化、そして機関投資家によるESG投資の採用が大きく影響しています。 なぜESG経営がこれほどまでに重要視されるようになったのか、その理由を見ていきましょう。
ESG経営は、近年世界的に注目を集めています。 その普及の背景には、地球規模の環境・社会問題の深刻化、投資家の価値観の変化、そして機関投資家によるESG投資の採用が大きく影響しています。 なぜESG経営がこれほどまでに重要視されるようになったのか、その理由を見ていきましょう。
背景1:地球規模の環境・社会問題の深刻化
近年、気候変動による異常気象、海洋プラスチック汚染、資源枯渇、人権侵害、貧富の格差拡大など、地球規模の環境・社会問題が深刻化しています。これらの問題は、企業の事業活動に直接的・間接的に影響を及ぼし、サプライチェーンの寸断や風評被害など、経営リスクとなる可能性が高まっています。
企業が持続的に成長するためには、これらの環境・社会問題への取り組みが不可欠であるという認識が広まったことが、ESG経営が注目される大きな背景です。
背景2:投資家の価値観の変化と長期的なリターンの追求
2008年のリーマンショック以降、短期的な利益追求だけでは持続的な企業価値を生み出せないという反省が生まれました。 これにより、投資家は企業の財務情報だけでなく、ESG要素といった非財務情報も重視するようになりました。 ESGへの取り組みは、企業の長期的な成長性や安定性を示す指標と捉えられ、長期的なリターンを追求する投資家の間で重要性が増しています。
背景3:年金基金などの大規模な機関投資家による採用
ESG経営が注目されるようになったもう一つの大きな要因は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)をはじめとする大規模な機関投資家が、運用戦略にESGの観点を取り入れ始めたことです。
GPIFは2015年に国連の責任投資原則(PRI)に署名し、ESG投資を推進する姿勢を明確にしました。
機関投資家がESGを重視することで、被投資企業もESGへの取り組みを強化せざるを得なくなり、結果としてESG投資の普及が加速しています。
企業がESG経営に取り組む4つのメリット
 企業がESG経営に取り組むことは、多岐にわたるメリットをもたらします。 単なる社会貢献活動にとどまらず、企業の競争力強化や持続的な成長に直結する重要な経営戦略として位置づけられています。 以下に、その主なメリットを4つご紹介します。
企業がESG経営に取り組むことは、多岐にわたるメリットをもたらします。 単なる社会貢献活動にとどまらず、企業の競争力強化や持続的な成長に直結する重要な経営戦略として位置づけられています。 以下に、その主なメリットを4つご紹介します。
メリット1:新たな資金調達の機会が広がる
メリット2:企業のブランドイメージと価値が向上する
メリット3:事業リスクの低減と経営の安定化につながる
メリット4:優秀な人材の獲得と従業員の定着につながる
メリット1:新たな資金調達の機会が広がる
ESG経営に積極的に取り組む企業は、投資家からの評価が高まり、資金調達がしやすくなるというメリットがあります。近年、投資家は従来の財務情報だけでなく、ESG要素を重視した「ESG投資」を拡大しており、ESGに配慮しない企業は投資を受けにくくなっています。
ESGへの取り組みを強化することで、新たな資金調達の機会が広がり、事業拡大や新規事業への投資が円滑に進む可能性が高まります。
メリット2:企業のブランドイメージと価値が向上する
ESG経営は、企業のブランドイメージと価値の向上に大きく貢献します。 環境への配慮や社会貢献活動、透明性の高い経営は、顧客、消費者、従業員、取引先などのステークホルダーからの信頼を獲得し、企業の評判を高めます。 ESGへの取り組みをIR(Investor Relations)活動や統合レポートを通じて積極的に開示することで、企業価値の向上につながり、競争優位性を確立することが可能となります。
メリット3:事業リスクの低減と経営の安定化につながる
ESG経営は、事業リスクの低減と経営の安定化に寄与します。環境問題への対応不足は規制強化や訴訟リスクにつながり、社会問題への配慮不足は従業員の離職や消費者からの不買運動を引き起こす可能性があります。ガバナンスの不備は不祥事や不正会計のリスクを高めます。ESGに配慮した経営を行うことで、これらのリスクを未然に防ぎ、法的な問題や評判の悪化、取引先とのトラブルなどを回避し、長期的に安定した経営基盤を構築できます。
メリット4:優秀な人材の獲得と従業員の定着につながる
ESG経営は、優秀な人材の獲得と従業員の定着にもつながります。 環境や社会に配慮し、多様な働き方を尊重する企業は、社会貢献意識の高い求職者にとって魅力的な職場となります。 働きやすい職場環境の整備や従業員の健康維持への取り組みは、従業員のエンゲージメントを高め、離職率の低下にも貢献します。 これにより、企業は持続的な成長に必要な人材を確保しやすくなります。
代表的なESG投資の7つの手法
ESG投資は、企業の財務情報だけでなく、環境・社会・ガバナンスの要素を考慮して投資判断を行う手法であり、その定義は多岐にわたります。 世界のESG投資額の統計を集計している国際団体のGSIA(グローバル・サステナブル投資連合)は、ESG投資を主に以下の7つの手法に分類しています。
ネガティブ・スクリーニング:特定の業界を投資対象から除外する手法
ポジティブ・スクリーニング:ESG評価が高い企業を選別して投資する手法
規範に基づくスクリーニング:国際的な規範を基準に投資先を選定する手法
ESGインテグレーション:財務情報に加えてESG要素も分析に組み込む手法
サステナビリティ・テーマ投資:持続可能性に関するテーマに投資する手法
インパクト投資:社会的・環境的な課題解決への貢献度を重視する手法
エンゲージメント・議決権行使:株主として企業に積極的に働きかける手法
ネガティブ・スクリーニング:特定の業界を投資対象から除外する手法
ネガティブ・スクリーニングは、特定の社会的・環境的基準に合致しない企業や業界を投資対象から除外する手法です。例えば、たばこ、武器、ギャンブル、原子力発電など、倫理的に問題があるとされるセクターの企業を排除するケースが挙げられます。これは、ESG投資の中で最も歴史の古い手法の一つであり、投資家の倫理的観点を反映したものです。
ポジティブ・スクリーニング:ESG評価が高い企業を選別して投資する手法
ポジティブ・スクリーニングは、ESGの観点から評価が高い企業や、環境保護、人権尊重、ダイバーシティ推進などの社会問題や環境問題でリーダーシップを発揮している企業を選別して投資する手法です。この手法では、企業が開示するESG情報やサステナビリティ・レポート、ESG評価機関の格付けなどを参考に、投資先を選定します。ポジティブ・スクリーニングにより、投資家は持続可能な社会の実現に貢献する企業に積極的に投資できます。
規範に基づくスクリーニング:国際的な規範を基準に投資先を選定する手法
規範に基づくスクリーニングは、国際的な規範や基準(例:国連グローバル・コンパクト、OECDガイドラインなど)に照らし合わせ、その基準を満たしていない企業を投資対象から除外する手法です。 この手法は、企業が社会的に受け入れられる行動規範を遵守しているかを重視し、投資先の選定に活用されます。
ESGインテグレーション:財務情報に加えてESG要素も分析に組み込む手法
ESGインテグレーションは、従来の財務情報分析に加えて、ESG要素を体系的かつ明示的に投資分析に組み込む手法です。 企業の長期的な成長には、財務情報だけでなく、環境リスクや社会問題への対応、ガバナンス体制といった非財務指標も重要であるという考えに基づいています。 この手法は、近年最も広く普及しつつあるESG投資の主流なアプローチとされています。
サステナビリティ・テーマ投資:持続可能性に関するテーマに投資する手法
サステナビリティ・テーマ投資は、持続可能性に貢献する特定のテーマや産業に投資する手法です。 具体的には、再生可能エネルギー、省エネルギー技術、持続可能な農業、水資源管理、グリーンビルディングなど、環境・社会課題の解決に直接的に寄与する分野への投資が挙げられます。 この投資は、社会的・環境的な成果と財務的リターンを両立させることを目指します。
インパクト投資:社会的・環境的な課題解決への貢献度を重視する手法
インパクト投資は、財務的リターンと同時に、測定可能な社会的・環境的インパクトを生み出すことを目的とした投資手法です。この投資は、社会・環境問題の解決に貢献する技術やサービスを提供する企業に焦点を当て、その貢献度を重視します。インパクト投資は、社会変革を促すための資金供給源としても期待されています。
エンゲージメント・議決権行使:株主として企業に積極的に働きかける手法
エンゲージメント・議決権行使は、投資家が株主として企業に対し、ESGに関する課題について積極的に働きかける手法です。これは、投資先企業の株式を保有し、株主総会での議決権行使や経営陣との対話を通じて、企業のESGパフォーマンスの向上を促すものです。エンゲージメントとは、対話を通じて企業に改善を促す活動であり、これにより企業の持続的成長と長期的な企業価値向上を目指します。
ESG経営に取り組む上での課題と注意点
ESG経営は多くのメリットをもたらす一方で、いくつかの課題と注意点も存在します。 これらの課題を認識し、適切な対策を講じることが、ESG経営を成功させる上で重要となります。
評価基準が統一されておらず判断が難しい
ESG評価の基準は、現時点では国際的に統一されていません。 評価機関によって重視する項目や評価方法が異なるため、企業がESGへの取り組み状況を適切に評価・開示し、外部からの評価を得ることが難しい場合があります。 企業は、自社の事業内容や特性に合わせた重要なESG課題(マテリアリティ)を特定し、その進捗を透明性高く情報開示していくことが求められます。
短期的な収益に結びつきにくい場合がある
ESG経営の成果は、短期的な利益やリターンに直結しにくい場合があります。 例えば、再生可能エネルギー設備の導入やサプライチェーンの改善には初期投資が必要であり、その費用対効果がすぐに現れるとは限りません。ESG経営は、長期的な視点での持続可能性や企業価値向上を目指すものであるため、短期的な収益目標とのバランスを考慮し、経営層の強いコミットメントが不可欠です。
コストの増加や専門知識を持つ人材が必要になる
ESG経営を推進するためには、新たな設備投資やシステム導入、従業員研修など、コストの増加を伴うことがあります。 また、ESGに関する専門知識を持つ人材の確保や育成も必要となります。 特に中小企業やスタートアップでは、人的・資金的リソースの制約が課題となる場合もあります。 これらの課題に対し、外部の専門家との連携や、既存の業務プロセスへのESG視点の統合など、効率的な取り組み方法を検討することが重要です。
【分野別】国内企業のESGへの取り組み事例
国内の多くの企業が、ESG経営を積極的に推進しています。 ここでは、環境、社会、ガバナンスの各分野における具体的な企業の取り組み例を紹介します。 これらの具体例は、自社の取り組みを検討する上での参考になるでしょう。
【環境】再生可能エネルギーの導入とサプライチェーン全体のCO2削減
環境分野における企業の取り組みとして、再生可能エネルギーの導入とサプライチェーン全体のCO2排出量削減が挙げられます。
例えば、自社工場やオフィスでの太陽光発電システムの導入、購入電力の再生可能エネルギーへの切り替えなどにより、事業活動におけるCO2排出量を削減する企業が増加しています。また、原材料調達から生産、物流、廃棄に至るサプライチェーン全体で環境負荷低減を目指し、サプライヤーと協力してCO2削減に取り組む企業も多く見られます。
経済産業省なども、企業の脱炭素化を推進する施策を打ち出しており、これは単なるコスト削減だけでなく、環境への貢献と企業価値向上を両立させる具体的な取り組みです。
【社会】多様な人材の活躍推進と働きやすい職場環境の整備
社会分野では、多様な人材の活躍推進と働きやすい職場環境の整備が重要な取り組みです。具体的には、性別、年齢、国籍、障がいの有無などに関わらず、すべての従業員が能力を発揮できるダイバーシティ&インクルージョンの推進が挙げられます。
例えば、育児や介護と仕事の両立支援、柔軟な働き方を可能にするテレワーク制度の導入、ハラスメント防止対策の強化、従業員の健康経営への注力などが進められています。
これらの取り組みは、従業員満足度を高め、人権を尊重した企業文化を醸成し、結果的に生産性向上にもつながります。
【ガバナンス】社外取締役の増員による経営の透明性向上
ガバナンス分野における取り組みとしては、経営の透明性向上を目的とした社外取締役の増員が一般的です。 社外取締役は、独立した立場から経営の意思決定を監督し、経営陣への牽制機能を果たすことで、不正の防止や企業倫理の遵守を強化します。 これにより、企業統治の健全性が高まり、株主や投資家からの信頼獲得に貢献します。 また、情報開示の徹底や内部通報制度の整備なども、透明性の高い経営を実現するための重要な取り組みです。
まとめ
ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの要素を指し、企業の持続的な成長と社会課題の解決を両立させるための重要な概念です。 ESG経営は、投資家からの評価向上や資金調達の機会拡大、ブランドイメージの向上、事業リスクの低減、優秀な人材の獲得といった多くのメリットをもたらします。 一方で、評価基準の未統一や短期的な利益への結びつきにくさ、コスト増加などの課題も存在します。 これらの課題を認識し、長期的な視点でESGの取り組みを進めることが、これからの企業経営には不可欠です。 本記事で紹介した内容が、貴社のESG経営推進の一助となれば幸いです。
デパートではサステナビリティサイトの制作支援を行なっております。専門チームがサステナビリティサイト構築/改修のトータルプランを提案いたします。ぜひお問い合わせください。
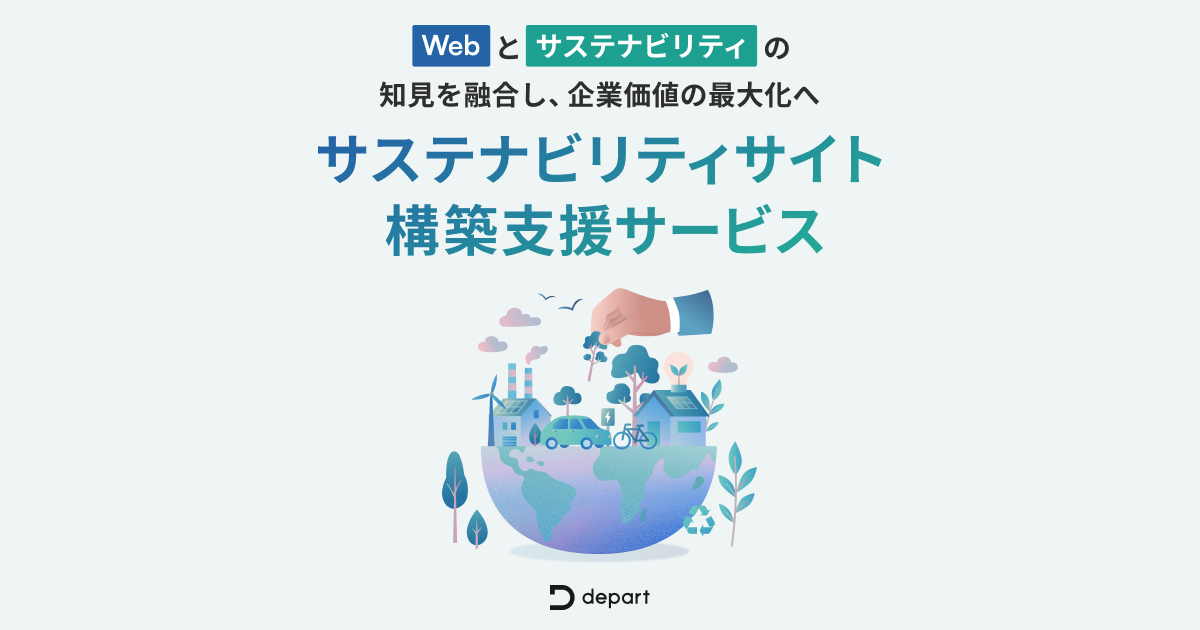
株式会社デパートで提供するサステナビリティサイト構築支援サービスでは、 Web制作とサステナビリティの知見を融合し、貴社のサステナビリティサイト構築に関連する、 戦略立案からサイト構築、そして継続的な運用・改善まで、全てお任せいただけます。

サスティナビリティサイトに関するご相談、 抱えられている課題など、お気軽にご相談ください。
Contact
制作のご依頼やサービスに関するお問い合わせ、
まだ案件化していないご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
- この記事をシェア