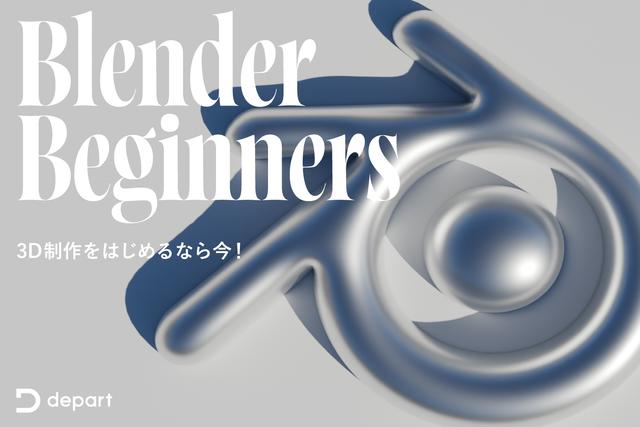- Share On
目次
目次
- インタビュー記事の基本
- インタビュー記事とは何か
- インタビュー記事の目的
- インタビュー記事の種類
- Q&A形式(対談形式)
- モノローグ形式(一人称形式)
- ルポ形式(三人称形式)
- インタビュー記事作成の準備
- 記事の目的と読者層の明確化
- 対象者の徹底的なリサーチ
- 質問事項の作成と共有
- 記事の構成案の検討
- インタビュー当日のポイント
- 録音・撮影機材の準備
- アイスブレイクの実施
- 話を引き出す質問の仕方
- 会話に集中する姿勢
- 記事執筆と公開までの流れ
- 文字起こしと内容の整理
- 伝わる文章への再構築
- 記事構成とストーリー性の意識
- 写真や視覚的要素の活用
- 校正と最終確認
- 記事の公開と拡散
- 面白いインタビュー記事を作るコツ
- 対象者の個性を引き出す
- 具体的なエピソードを盛り込む
- 読者を引き込む書き出し
- 話題の切り替えと深掘り
- インタビュー記事の事例
- 社員インタビュー
- 対談記事
- まとめ
読まれるインタビュー記事を作成するには、書き方や構成だけでなく、準備から当日の進行、執筆後の編集まで、様々なポイントを押さえる必要があります。この記事では、インタビュー記事とは何かという基本的な部分から、具体的な作成手順、記事をより面白くするためのコツまで詳しく紹介します。
インタビュー記事の基本
インタビュー記事は、特定の人物や企業に直接話を聞き、その内容を読者に分かりやすく伝えることを目的とした記事です。目的や伝える内容に応じて、いくつかの種類や形式が存在します。ここでは、インタビュー記事とは何か、その目的について掘り下げていきます。
インタビュー記事とは何か
インタビュー記事とは、特定の人物や企業に対して取材を行い、対象者の考えや専門知識、意見などを引き出し、それを分かりやすく読者に伝えることを目的とした記事です。SEO記事が二次情報の編集が中心なのに対し、インタビュー記事は一次情報を直接届けられるため、「共感」や「理解促進」を生み出すコンテンツとして非常に効果的です。現代においてインターネット上のコンテンツ量は計り知れないほど増加していますが、インタビュー記事はオリジナルの価値を発揮しやすく、独自性を出しやすいという特徴があります。取材を行う人を「インタビュアー」、取材される人を「インタビュイー」と呼び、対談や質疑応答を通じて構成されます。顧客の体験談や特定の仕事に従事するスタッフの業務内容など、多様な種類があります。
インタビュー記事の目的
インタビュー記事を作成する主な目的は情報発信と信頼獲得です。具体的には自社の商品やサービスを利用している顧客の声や導入事例を紹介することでその商品・サービスの信頼度を高め、購入を検討しているターゲット顧客の購買意欲を促進する効果が期待できます。また採用活動や企業のブランディングにも有効です。例えば社員インタビューを通じて社内の雰囲気や働きがいを伝えることで、求職者にとって魅力的な会社であることをアピールし採用ブランディングを強化できます。さらに新商品やサービスの開発秘話や開発者の想いや背景を伝えることで、読者の共感を生み出しファンの獲得にも繋がります。インタビュー記事は単なる情報の羅列ではなくストーリー性を持たせることで読者の心に響くコンテンツとなり得ます。

本記事では、オウンドメディアとコンテンツマーケティングの違いに触れながら、オウンドメディアの目的や制作手順などを紹介します。オウンドメディアを制作して、集客やブランディングを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

本記事では、効果的なオウンドメディアを構築するための戦略の手順やポイントを中心に解説します。また、オウンドメディアを運用する目的や、戦略を立てる際によくある失敗なども紹介します。オウンドメディアの導入を検討している方や、綿密な戦略を立てて効果的なコンテンツ制作を行っていきたい方は、ぜひ参考にしてください。
インタビュー記事の種類
インタビュー記事は、その内容や目的に応じて様々な形式で表現されます。主要な形式としては、Q&A形式(対談形式)、モノローグ形式(一人称形式)、ルポ形式(三人称形式)の3種類が挙げられます。それぞれの形式には異なる特徴があり、記事の雰囲気や読者への伝わり方が大きく変わるため、伝えたい内容や読者に与えたい印象に合わせて適切な形式を選択することが重要です。

【インタビュー記事の種類】
Q&A形式(対談形式)
モノローグ形式(一人称形式)
ルポ形式(三人称形式)
Q&A形式(対談形式)
Q&A形式は、インタビュアーの質問とインタビュイーの回答を交互に配置する対談形式です。この形式は、実際の会話に近い構成であるため、読者にとって親しみやすく、テンポ良く読み進めやすいという特徴があります。質問と回答が明確に分かれているため、知りたい情報にすぐにたどり着くことができ、複数のインタビュー対象者がいる場合でも、誰が何を話しているのかが分かりやすく表現できます。会話の臨場感やインタビュイーの人柄を伝えやすく、口語を交えながら記事にすることで個性を表現しやすいというメリットもあります。文字起こししたものを整理するだけで比較的執筆しやすいため、インタビュー記事の中でも最も一般的な形式の一つとされています。ただし、会話が長くなると要点がぼやけたり、話し手の個性が強すぎると読みにくくなる場合もあるため、適度な編集が必要です。記事で発信したいメッセージを明確にするため、質問の順番を入れ替えたり、大見出しや小見出しを設定して、それに沿った質問と回答を配置していくと、より伝わりやすい記事になります。
モノローグ形式(一人称形式)
モノローグ形式、または一人称形式は、インタビュアーが登場せず、インタビュイー自身が語るような形で記事を構成する形式です。この形式では、インタビュアーが取材で得た情報を基に、インタビュイーになりきってコラムやエッセイのように文章をまとめます。語り手の想いや背景が読者にダイレクトに伝わるため、ストーリー性や共感を重視したい場合に特に効果的です。メッセージ性が強くなり、インタビュイーの人柄を色濃く表現できるため、企業ヒストリーや経営者のヒストリーなど、深いメッセージを伝えたい企画に適しています。読者に語りかけるような書き方ができるため、親しみを持ってもらいやすいというメリットもあります。しかし、構成や話題の転換が難しく、書き手の文章力が問われる形式でもあります。インタビュイーの発言の意図を正確に汲み取り、本人が使いそうな言葉選びや言い回しを心がけることで、より人柄が伝わる記事に仕上がります。段落ごとに話題を整理し、補足情報や写真を自然に挿入することで、読みやすく印象的な記事になります。
ルポ形式(三人称形式)
ルポ形式、または三人称形式は、インタビュアーが第三者の視点から取材内容を客観的に再構成し、論理的に伝える形式です。この形式では、インタビュイーの言葉を要約し、その場の雰囲気や表情、仕草、背景情報などを織り交ぜながら記事を構成します。これにより、臨場感やインタビュイーの話を広い文脈で理解させることが可能となります。論理的で客観的な描写ができるため、記事に説得力を持たせやすく、地の文で詳細な説明を加えることができる点がメリットです。専門性の高い話題や、事実を整理して伝えたい場面に適しており、情報量が多くなりがちです。ただし、論評のような形になるため堅苦しい印象を与えやすく、会話内容をそのまま記事にするのではなく、読みやすく組み立てていく必要があるため、書き手の文章力が求められます。他の形式に比べて、インタビュイーの人柄を直接的に伝えにくいというデメリットも存在します。発言部分は引用符で明示し、見出しで話題を区切るなどの工夫を凝らすことで、読みやすさを高めることができます。
インタビュー記事作成の準備
質の高いインタビュー記事を作成するためには事前の準備が最も重要です。この段階で目的や読者層を明確にし対象者を徹底的にリサーチすることでスムーズなインタビューと読者に響く記事執筆が可能になります。質問事項の作成や記事の構成案の検討もこの準備期間に行うべき重要な作業です。
【インタビュー記事作成の準備】
記事の目的と読者層の明確化
対象者の徹底的なリサーチ
質問事項の作成と共有
記事の構成案の検討
記事の目的と読者層の明確化
インタビュー記事の作成において、まず初めに重要なのは、その記事の目的とターゲット読者を明確にすることです。どのような情報を誰に伝えたいのか、そして記事を読んだ読者にどのような行動を促し、どのような効果や成果を得たいのかというゴールを設定することが不可欠です。例えば、採用ブランディングを強化したいのであれば、求職者に対して会社や社員の魅力を伝えることを目的に設定します。これにより、記事の構成や質問内容、さらにはインタビュイーの選定まで、すべての要素が目的と読者ニーズに沿ったものとなり、より的確な訴求が可能となります。テーマを明確にすることで、取材の精度を高め、読者が求める情報を提供できる記事へと繋がります。
対象者の徹底的なリサーチ
インタビュー対象者の徹底的なリサーチは、質の高いインタビュー記事を作成するために非常に重要です。対象者の経歴、背景、専門分野、過去のインタビュー記事や発信済みの内容などを事前に詳しく調べておくことで、限られたインタビュー時間を最大限に活用できます。特に、Webサイトや過去の新聞記事、Web記事、YouTubeなどに掲載されている基本情報は必ず確認しておきましょう。既に語られている内容を繰り返して質問することは避け、それらの情報を前提に、さらに深掘りできる話題や、まだ誰も掘り起こしていない具体的なエピソードを引き出すための質問を構築することが重要です。「なぜそう思ったのか」「どういうところでそう感じたのか」といった理由や具体例を深掘りすることで、読者にとって有益で、かつインタビュイーの人柄が伝わるような記事につながります。事前リサーチを怠ると、「それくらい知っていてよ」とインタビュイーに不快な印象を与えてしまう可能性もあるため、注意が必要です。
質問事項の作成と共有
質問事項の作成は、インタビュー記事の質を大きく左右する重要な工程です。読者にとって有益な情報を中心に質問項目を検討し、記事の構成に落とし込んでいきましょう。例えば、1時間のインタビューであれば、5~7つの質問を準備するのが目安とされています。質問リストを作成する際は、事前に設定した記事の目的とターゲット読者を念頭に置き、インタビュイーの経歴や背景を深くリサーチした上で、具体的なエピソードを引き出せるような質問を心がけましょう。作成した質問事項は、インタビューの前にインタビュイーと共有しておくことが大切です。これにより、インタビュイーは質問内容を事前に把握し、回答を準備できるため、当日のインタビューがスムーズに進行します。また、事前に共有することで、インタビュイーから必要な資料やデータを提供してもらえる可能性もあり、記事の質を高めることに繋がります。質問のテンプレートを活用し、効率的に準備を進めることも有効です。
記事の構成案の検討
インタビュー記事の質は、綿密な構成案によって大きく向上します。構成案の検討は、単に文字起こしした内容を並べるのではなく、読者に伝わるストーリーとして再構築するために不可欠な工程です。まず、設定した記事の目的とターゲット読者層を念頭に置き、どのような情報を、どのような順序で伝えるのが最も効果的かを検討します。具体的には、導入部分で読者の興味を引きつけ、本文で深掘りした情報や具体的なエピソードを盛り込み、最後にまとめで記事全体の要点を提示する「起承転結」の流れを意識すると良いでしょう。インタビューで得られた内容を基に、読者にとって分かりやすく、論理的に話が展開されるように、話題の順番を入れ替えたり、関連する情報をまとめたりと、柔軟に構成を調整することが重要です。見出しや小見出しを設定することで、記事全体が整理され、読者が知りたい情報にアクセスしやすくなります。事前に大まかな構成案を作成し、インタビュイーに共有することで、当日の質問もより的確に行えるようになります。
インタビュー当日のポイント
インタビュー当日は、事前の準備が実を結ぶ大切な場面です。スムーズな進行はもちろんのこと、インタビュアーとしての立ち居振る舞いや、相手の言葉を最大限に引き出す工夫が求められます。ここでは、インタビューを成功させるための具体的なポイントを紹介します。

【インタビュー当日のポイント】
録音・撮影機材の準備
アイスブレイクの実施
話を引き出す質問の仕方
会話に集中する姿勢
録音・撮影機材の準備
インタビュー当日は、録音・撮影機材の準備が重要です。音声データを確実に記録するため、ICレコーダーなどの録音機材は複数台用意し、バッテリー切れに備えて充電も確認しておきましょう。予備の電池やモバイルバッテリーも忘れずに持参することをおすすめします。また、録音や録画を行う際は、必ずインタビュイーの許可を得てから開始するようにしてください。記事に掲載する写真撮影の許可が出ている場合は、カメラマンが同行していればインタビュー中に撮影を進めます。インタビュアーが撮影を兼ねる場合は、インタビューの前後で時間を確保し、ポートレートや取材風景など、記事の魅力を高める写真素材を撮影しましょう。インタビュー中の写真撮影では、インタビュイーの自然な表情や仕草を捉えることが、記事の臨場感を高める上で効果的です。音声データの質は文字起こしの効率にも直結するため、録音環境にも配慮し、ノイズの少ないクリアな音声を確保するよう心がけましょう。
アイスブレイクの実施
インタビューを開始するにあたり、アイスブレイクは非常に重要な役割を果たします。特に、インタビュイーが取材に慣れていない場合や、インタビュアーとの関係性がまだ浅い場合、いきなり本題に入ると緊張してしまい、スムーズな会話が難しくなることがあります。そこで、名刺交換の後などに、まずは軽い雑談から始めることで、場の雰囲気を和ませ、インタビュイーの緊張をほぐすことができます。共通の話題や最近の出来事、あるいはインタビュイーの趣味や興味のあることについて軽く触れるのも良いでしょう。アイスブレイクの時間は、インタビュアーとインタビュイーの間に信頼関係を築き、リラックスした雰囲気を作り出すための大切な機会です。これにより、インタビュイーは本音で話しやすくなり、より深く具体的なエピソードを引き出すことに繋がります。また、インタビュアー自身も落ち着いてインタビューに臨むことができるため、双方にとって有意義な時間となるでしょう。
話を引き出す質問の仕方
話を引き出す質問の仕方は、インタビュー記事の質を大きく左右するインタビュアーの重要なスキルです。インタビュイーからより深い情報や具体的なエピソードを引き出すためには、ただ質問を投げかけるだけでなく、いくつかの工夫が必要です。まず、インタビュイーの回答に対して、「どうしてそう思ったのか」「どういうところでそう感じたのか」など、理由や具体的な例を深掘りして聞くようにしましょう。事実だけでなく、その背景にある感情や思考を掘り下げることで、記事に深みと説得力が増します。また、質問の流れは時間軸を意識して行うのがおすすめです。例えば、サービス開発に関するインタビューであれば、「開発前」「開発のきっかけ」「開発中の苦労」「現在の状況」「今後の展望」といった時系列で質問を進めることで、話にストーリー性が生まれ、読者にとって読みやすい記事になります。予想外の展開になっても話を遮らず、本筋から外れた内容も記録しておくことで、思わぬ面白いエピソードや貴重な情報につながる可能性もあります。理解できなかったことは素直に聞き返すことも大切です。
会話に集中する姿勢
インタビュアーが会話に集中する姿勢は、インタビュイーから本音を引き出し、質の高いインタビュー記事を作成するために不可欠です。メモを取ることや機材の操作に集中しすぎてしまうと、インタビュイーは「話を聞いてもらえているのだろうか」と感じ、話しにくくなってしまう可能性があります。そこで、インタビュアーは、インタビュイーの目を見て、適度な相槌を打つことや、表情や仕草から相手の感情を読み取ろうと努めることが重要です。相手が話している最中に、次の質問を考えることに集中しすぎるのではなく、今話している内容を深く理解しようとすることで、インタビュイーは「この人は自分の話を真剣に聞いてくれている」と感じ、安心してより多くの情報や感情を共有してくれるでしょう。予想外の話題に発展した場合でも、話を遮らずに耳を傾け、時にはその流れに乗って深掘りすることで、記事に独自性のあるエピソードを盛り込むことができる可能性も高まります。このようなインタビュアーの傾聴の姿勢が、インタビュイーとの信頼関係を構築し、より内容の濃いインタビューへと繋がります。
記事執筆と公開までの流れ
インタビューが終われば、いよいよ記事執筆の段階です。ここからは、録音した内容を整理し、読者に伝わる文章へと再構築する作業が中心となります。写真や視覚的要素を効果的に活用しながら、校正・最終確認を経て、最終的に記事を公開し、必要に応じて拡散するまでの流れを解説します。
【記事執筆と公開までの流れ】
文字起こしと内容の整理
伝わる文章への再構築
記事構成とストーリー性の意識
校正と最終確認
記事の公開と拡散
文字起こしと内容の整理
インタビュー終了後、最初に必要な工程が文字起こしです。これは、録音したインタビュー音源を文章化する作業を指します。文字起こしには、素起こし、ケバ取り、整文の3種類があり、記事の目的に応じて使い分けることが重要です。素起こしは、相槌や言い間違い、意味のないつなぎ言葉なども含めて、音源をすべて忠実に書き起こす方法で、インタビューの臨場感をそのまま伝えたい場合に適しています。しかし、話し言葉をそのままテキストにすると、主語が途中で変わったり、一文が長くなったりと、読みにくい文章になることがあるため注意が必要です。そのため、文字起こしした内容をそのまま記事に使うのではなく、読者に伝わりやすい文章へ再構築する整文の作業が欠かせません。特に、その場にいない読者にとっては、分かりづらい文章になりがちです。最近では、AIを活用した文字起こしサービスやツールも多数登場しており、これらを活用することで、手作業で文字起こしするよりも大幅に時間を短縮し、効率的に作業を進めることが可能です。音声データの質が良いほど文字起こしの精度も高まるため、録音環境にも配慮することが重要です。
伝わる文章への再構築
文字起こしが完了したら、次にインタビュイーの言葉を単に羅列するのではなく、読者に「伝わる文章」へと再構築するライティング作業が始まります。インタビュー時の話し言葉は、そのまま記事にすると主語が不明確だったり、冗長になったりして読みにくい場合があります。そのため、発言の意図が変わらない程度に、不要な言葉を削り、主語や述語を補い、自然な日本語になるように編集することが大切です。読者がスムーズに読み進められるよう、意味がつながる文同士は自然な形で一文にまとめたり、難しい専門用語は平易な言葉に置き換えたり、補足説明を加えたりする工夫も必要です。また、インタビュイーの人柄や感情が伝わるように、文末表現や相槌を工夫することも効果的です。例えば、「!」や「~」を使うことで明るい雰囲気を表現したり、「そうそう!」といった相槌を適度に入れることで、その人らしさを出すことができます。ただし、過度に口語表現を減らしすぎると、臨場感や人柄が失われる可能性もあるため、バランスが重要です。記事の目的やターゲット読者層に合わせて、どのようなトーンで、どの程度言葉を整えるかを判断するライティングスキルが求められます。
記事構成とストーリー性の意識
伝わるインタビュー記事を作成するには、記事構成とストーリー性を意識したライティングが不可欠です。単に質問と回答を並べるだけでなく、読者が引き込まれるような物語の流れを作り出すことで、記事の面白さや読み応えが格段に向上します。記事の冒頭では、読者の興味を惹きつける書き出しを意識し、記事全体のハイライトやインタビュイーの魅力を簡潔に伝えることが重要です。本文では、時間軸に沿って「過去→現在→未来」という流れで情報を展開したり、特定のテーマについて深掘りすることで、話に論理的なつながりを持たせることができます。例えば、企業の成長背景をテーマにする場合、創業からの歴史、現在の課題と取り組み、そして今後の展望といった流れで構成すると、読者は自然にストーリーを追体験できるでしょう。また、インタビュイーの発言の中から特に印象的なフレーズやキーワードを見つけ出し、見出しや小見出しに効果的に配置することで、読者の関心を維持し、記事全体を読みやすくすることが可能です。質問の順番を入れ替えたり、関連性の高い情報をまとめたりして、読者が混乱しないよう構成を工夫することも大切です。最終的に、記事全体を通して読者に何を一番伝えたいのか、というメッセージが明確に伝わるようなストーリー設計を心がけましょう。
写真や視覚的要素の活用
インタビュー記事において、写真や視覚的要素の活用は、読者の興味を引きつけ、記事の魅力を高める上で非常に効果的です。特に、記事の顔となるアイキャッチ画像やサムネイルは、読者が記事を読むかどうかを判断する重要な要素となるため、インパクトのある写真を選びましょう。本文中にインタビュイーの表情や仕草が分かる写真を複数枚挿入することで、記事に臨場感が生まれ、読者はまるでその場にいるかのようにインタビュイーの人柄や雰囲気をイメージしやすくなります。例えば、笑顔の写真や真剣な表情の写真、ジェスチャーを交えている瞬間など、会話内容と連動した写真を使用すると、より効果的です。また、インタビューが行われた場所の風景や、関連する商品・サービスの写真、図解などを適宜挟むことで、読者の理解を深め、視覚的に飽きさせない工夫もできます。これらの写真や図解は、記事の構成に合わせて自然な形で配置し、文章の内容を補完する役割を持たせることが重要です。視覚的な要素を効果的に活用することで、読者の記憶に残りやすい、魅力的なインタビュー記事を制作することができます。
校正と最終確認
記事執筆が完了したら、公開前に必ず校正と最終確認を行います。この工程は、記事の品質を担保し、読者に正確な情報を届けるために非常に重要です。まず、誤字脱字、文法の誤り、不自然な言い回しがないかを確認します。次に、事実関係に誤りがないか、インタビュイーの発言内容が正確に反映されているかを入念にチェックしましょう。特に、インタビュー記事においては、インタビュイーの意図と異なる解釈をされないよう、細心の注意を払う必要があります。記事の初稿が完成したら、可能であればインタビュイー本人に最終チェックを依頼しましょう。この際、写真を含めた完成形の状態で確認してもらうのが理想的です。インタビュイーから「この内容は載せないでほしい」「表現を修正してほしい」といった要望が出ることもありますので、双方の意見を尊重しつつ、読者にとって有益で面白い読み物としてのクオリティを維持しながら調整を進めることが大切です。また、第三者にも確認してもらうことで、客観的な視点から改善点を見つけられる可能性があります。編集作業においては、記事全体の論理的な流れや一貫性、見出しと本文の整合性なども確認し、読者がスムーズに理解できるかを検証します。
記事の公開と拡散
校正と最終確認を経て記事が完成したら、いよいよ公開と拡散の段階へと進みます。記事を公開するプラットフォームは、自社のWebサイト、オウンドメディア、ブログ、または外部メディアへの掲載など、多岐にわたります。公開後は、より多くの読者に記事を届けるために、様々な方法で拡散を図ることが重要です。SEO対策として、適切なキーワードを設定し、メタディスクリプションを充実させることで、検索エンジンからの流入を促すことができます。また、ソーシャルメディア(X、Facebook、Instagramなど)でのシェアや、メールマガジンでの紹介、関連するニュースサイトやメディアへのプレスリリース配信なども効果的な拡散方法です。特に、Webサイトやブログでの掲載の場合、SNS連携機能を活用して簡単にシェアできるようにすることで、読者による自然な拡散も期待できます。記事のテーマや内容に応じて、関連性の高いコミュニティやフォーラムでの紹介も検討しましょう。記事が公開されたことをインタビュイーに伝え、協力して拡散を促すことも有効です。質の高いインタビュー記事は、一度公開された後も継続的に読まれ続ける資産となり、企業の認知度向上やブランディング、採用活動に貢献します。
面白いインタビュー記事を作るコツ
読者の心を掴み、最後まで読んでもらえる面白いインタビュー記事を作成するには、いくつかのコツがあります。単に情報を伝えるだけでなく、インタビュイーの個性や魅力、そして読者を引き込むストーリーテリングが重要です。ここでは、具体的なエピソードの盛り込み方や書き出しの工夫など、読まれる記事にするためのポイントを紹介します。

【面白いインタビュー記事を作るコツ】
対象者の個性を引き出す
具体的なエピソードを盛り込む
読者を引き込む書き出し
話題の切り替えと深掘り
対象者の個性を引き出す
面白いインタビュー記事を作成するためには、インタビュイーの個性を最大限に引き出すことが非常に重要です。インタビューは、単に質問に答えてもらうだけでなく、インタビュイーの考え方や人柄、感情を深く掘り下げる機会です。読者がその人物に親近感を抱き、共感できるような要素を記事に盛り込むことで、より魅力的なコンテンツになります。例えば、インタビュイーが普段使っている言葉遣いや、ちょっとした口癖、ユーモラスな表現などをあえて残すことで、その人らしさを出すことができます。また、インタビュイーの表情や仕草、話し方から感じ取れる人柄や雰囲気を、地の文で描写することも効果的です。記事の目的には直接関係のないような、人柄が伝わるエピソードや裏話などもバランス良く盛り込むと、記事の面白さが増し、読者の記憶に残りやすくなります。これらの取捨選択こそが、記事を執筆するライターの腕の見せ所と言えるでしょう。事前のリサーチでインタビュイーの多面的な情報を把握し、当日のインタビューでは深掘りする質問を通じて、その人ならではの魅力を引き出すことを意識しましょう。
具体的なエピソードを盛り込む
読者の心に響く面白いインタビュー記事を作るには、具体的なエピソードを豊富に盛り込むことが非常に重要です。事実や結果を淡々と羅列するだけでは、読者にとって単調な情報となり、共感や興味を引き出しにくい記事になってしまいます。インタビュイーの人柄や感情が伝わるような具体的な事例や体験談を多く盛り込むことで、読み物としての面白さが加わり、読者はより一層の親近感を抱いて読み進めてくれるでしょう。例えば、成功談だけでなく、失敗談やそこから学んだ教訓、決断の瞬間の葛藤など、人間味あふれるエピソードは読者の共感を呼びます。また、サービスや製品の導入事例インタビューでは、「導入前の課題」「導入の決め手」「導入後の具体的な効果」といった時系列に沿ったエピソードを盛り込むことで、読者は自身の状況と重ね合わせ、サービスの有効性をより具体的に理解できます。取材時には、インタビュイーが感じたことや思ったこと、意思決定の背景などをできるだけ具体的に聞き出す質問を心がけましょう。このような詳細なエピソードは、記事の独自性を高め、読者に「この記事を読んでよかった」と感じてもらえる価値あるコンテンツへと繋がります。
読者を引き込む書き出し
読者を引き込む書き出しは、インタビュー記事を最後まで読んでもらうための重要な要素です。冒頭のリード文は、記事全体のハイライトや最も伝えたいメッセージを簡潔にまとめる場所であり、読者に「もっと読みたい」と思わせるようなインパクトを与えることが求められます。インタビュー記事の書き出しは、その形式によっても異なりますが、対談形式やモノローグ形式の場合は、記事の概要やインタビュイーの紹介から始めるのが一般的です。ルポ形式の場合は、昔話からスタートしたり、結論から入るなど、構成によって書き出しのパターンは多様です。いずれの形式においても、読者の好奇心を刺激し、読み手のワクワク感を誘うような導入を心がけることが大切です。具体的には、インパクトのある言葉や意外性のある事実、あるいは読者が共感できるようなエピソードを盛り込むことが効果的です。また、インタビュイーの印象的な言葉や、人物の魅力を端的に表現する描写も、読者の興味を引きつけます。専門用語は避け、誰が読んでも概要が理解できるように平易な言葉で書くことが、冒頭文のポイントです。記事タイトルの答えが冒頭文に盛り込まれていると、読者はスムーズに読み進めることができます。
話題の切り替えと深掘り
インタビューにおいて、話題の切り替えと深掘りは、インタビュアーの腕の見せ所であり、記事の面白さを左右する重要なコツです。インタビュイーから話を引き出す際、単に用意した質問を順に投げかけるだけでなく、回答の内容に合わせて柔軟に質問を広げたり、特定のトピックを深く掘り下げたりする意識が求められます。具体的には、インタビュイーが語った内容に対して「なぜそう思ったのか」「具体的なエピソードはありますか」「その時、どんな気持ちでしたか」といった質問を重ねることで、表面的な回答だけでなく、その背景にある感情や具体的な体験を引き出すことができます。また、時間軸を意識した質問の展開は、話にストーリー性をもたらし、読者にとって読みやすい記事につながります。例えば、過去の経験から現在、そして未来への展望へと話を展開することで、インタビュイーの成長や変化の過程を浮き彫りにすることが可能です。時に、本筋から外れた話題が思いがけない面白いエピソードにつながることもあるため、話を遮らず、柔軟に耳を傾ける姿勢も大切です。インタビュアーは、深さと幅の両面から話題を掘り下げ、読者が最も知りたいであろう核心に迫る質問を投げかけることで、情報が深く、かつ多角的に展開される記事を作成できます。
インタビュー記事の事例
インタビュー記事は、その目的や掲載媒体によって多種多様な形式があります。ここでは、特にビジネスシーンで活用されることが多い「社員インタビュー」と「対談記事」の具体的な事例を通じて、それぞれの特徴と効果について解説します。
社員インタビュー
社員インタビューは企業の採用活動やブランディングにおいて非常に効果的な記事の事例です。社員個人の具体的な仕事内容ややりがい、入社理由、会社の雰囲気、キャリアパスなどを深掘りすることで、求職者は企業のリアルな働き方や文化を具体的にイメージできます。例えば、新卒採用においては、若手社員の成長エピソードや困難を乗り越えた経験などを紹介することで、読者である学生に共感を促し、入社への意欲を高める効果が期待できます。中途採用においては、入社後のギャップや前職との違い、スキルアップの機会などを具体的に語ってもらうことで、求職者の不安を解消し、企業への理解を深めることができます。社員一人ひとりの「生の声」を届けることで、企業の透明性や信頼性が高まり、採用ミスマッチの防止にも繋がります。また、社員インタビューは社内エンゲージメントの向上にも寄与し、社員のモチベーションアップや帰属意識の醸成にも繋がる側面もあります。求人サイトやプラットフォームで多く見られる形式であり、会社の魅力を多角的に伝える上で非常に有効なコンテンツです。

本記事では、社員インタビューを通じて企業の魅力を伝える方法を詳しく解説します。インタビューの企画・実施から、効果的な記事の作成・公開までの一連のプロセスを、具体的な事例を交えながらわかりやすく説明します。

本記事では、採用マーケティングの概要と主要な戦略について解説します。採用ブランディング、候補者とのコミュニケーション、データ活用など、採用成功に導く鍵となるポイントを詳しく紹介していきます。
対談記事
対談記事は、通常二人以上の人物が特定のテーマについて議論や意見交換を行う形式のインタビュー記事です。特に、経営者や社長といった企業のトップ層が対談する記事は、企業のビジョンや戦略、業界の展望などを深く掘り下げることができ、読者に高い専門性と信頼性を感じさせます。例えば、異なる企業の経営者同士が対談することで、それぞれのビジネス哲学や課題解決へのアプローチが比較され、読者にとって新たな視点や学びを提供できます。また、対談形式は、会話のキャッチボールを通して、それぞれの話し手の個性や人柄、思考プロセスが自然に伝わりやすいという特徴があります。これにより、読者は記事の内容だけでなく、対談する人物そのものにも興味を持ち、共感を抱きやすくなります。採用活動においても、経営者や先輩社員同士の対談記事は、企業の文化や風土、社員同士の関係性を伝える上で効果的です。Q&A形式に似ていますが、より議論を深めることを目的とし、それぞれの専門性や経験に基づいた意見が交わされることで、読者に深い洞察やインスピレーションを与えることができます。
まとめ
今回は、読まれるインタビュー記事の書き方について解説しました。インタビュー記事の作成は、事前準備から取材当日、そして執筆と公開に至るまで、様々な工程とポイントがあります。記事の目的と読者層を明確にし、入念なリサーチと構成案の検討を行うことで、記事の品質は大きく向上します。また、インタビュアーは、アイスブレイクで場の雰囲気を和ませ、話を引き出す質問の仕方でインタビュイーの個性を引き出すことが重要です。執筆においては、文字起こしした内容を単に羅列するのではなく、読者に伝わる文章へと再構築し、ストーリー性を意識したライティングを心がけましょう。写真や視覚的要素を効果的に活用し、入念な校正と最終確認を経て記事を公開することで、読者に響く面白い記事が完成します。本記事で紹介した書き方やコツを参考に、ぜひ質の高いインタビュー記事を作成し、自社のメディアやサイトのコンテンツ力を高めてください。キーワードの選び方にも工夫を凝らし、読者の検索意図に合致するよう意識することで、より多くの人に記事を届けることができるでしょう。
株式会社デパートでは、Webサイト制作を中心に、インタビュー記事をはじめとしたコンテンツ作成にも対応しています。
「記事の構成や書き方に悩んでいる」「読まれるインタビュー記事を作りたい」といった方がいれば、目的に合わせた記事制作をサポートいたします。また、記事の顔となるアイキャッチ画像やサムネイルなど、デザイン面のご相談も歓迎です。お気軽にご相談ください。
Contact
制作のご依頼やサービスに関するお問い合わせ、
まだ案件化していないご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
- この記事をシェア