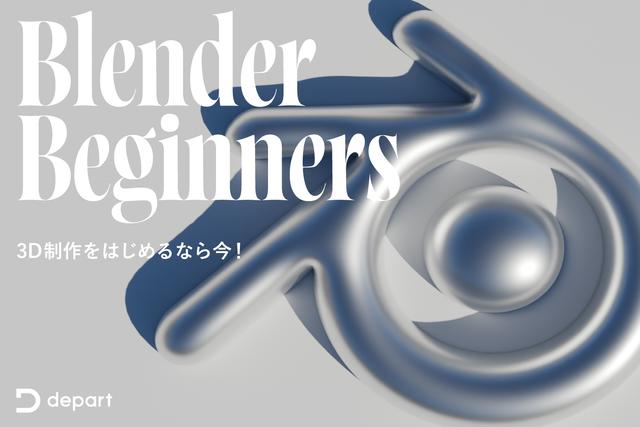- Share On
目次
目次
- システム移行の概要
- システム移行の定義
- システム移行が必要な状況
- システム移行のパターン
- システム移行の方式
- 一括移行
- 段階的移行
- 並行運用
- パイロット移行
- システム移行の手順
- 1. 移行元システムとデータの調査
- 2. 移行計画書の作成
- 3. 移行リハーサルの実施
- 4. 移行作業の実施
- 5. 新システムへのテストと運用開始
- システム移行のリスクと注意点
- データ移行のリスク
- 業務停止のリスク
- システム互換性の問題
- トラブル発生時の対応計画
- システム移行を成功させるポイント
- 詳細な移行計画
- 事前教育と情報共有
- 専門家への外部委託
- 綿密なテストと検証
- システム移行でよくある質問
- Q1. システム移行中に業務を停止させる必要はありますか?
- Q2. どのようなデータが移行対象となりますか?
- Q3. システム移行を外部に委託するメリットは何ですか?
- Q4. 移行後にシステムトラブルが発生した場合の対応策は?
- まとめ
システム移行とは、既存のシステムやソフトウェアを新しい環境へ移し替える作業全般を指します。業務効率の向上やセキュリティ強化、あるいは老朽化したシステムの刷新など、様々な目的で実施されます。
しかし、システムの複雑化に伴い、計画から本番化までの手順を誤ると、データ損失や業務停止といった失敗につながるリスクも少なくありません。
本記事では、システム移行を成功させるための具体的な手順と、押さえておくべき重要なポイントについて詳しく解説します。
システム移行の概要

システム移行とは、現在使用しているシステムから、異なる環境の新しいシステムへ切り替えることを指します。これは単にデータを移すだけでなく、業務プロセス全体に関わる重要なプロジェクトであり、その意味と種類、パターンを理解することが成功の鍵となります。
システム移行の定義
システム移行とは、既存のシステムやソフトウェアを新しいシステムや異なる環境へ移し替える作業のことです。英語では System Migration と呼ばれます。企業にとっては定期的に発生する重要な作業であり、迅速かつトラブルなく完了させるには、綿密な計画と新旧両方のシステムに関する深い知識が欠かせません。
ここで注意したいのは、「移行」と言っても対象がいくつかに分かれるという点です。
システム移行:古いシステムから新しいシステム全体への切り替え
データ移行:異なるデータベースやストレージへのデータ移動
業務移行:新システム上で業務を運用できるようにする準備
システム移行は「システム全体の切り替え」を指すため、データ移行や業務移行と混同しないように整理しておくと理解がスムーズになります。
システム移行が必要な状況
システム移行が求められる背景はさまざまですが、代表的な理由として次のようなものがあります。
ハードウェアの老朽化・保守期限切れ
機器の故障リスクが高まり、メーカーからの修理や部品調達が困難になる。
OSやミドルウェアのサポート終了
ベンダーによる障害対応やセキュリティ更新が打ち切られ、脆弱性を突いた攻撃を受けやすくなる。
レガシーシステムの限界
古い設計思想や製品に基づくため、
現代の業務要件に対応できない
他システムとの連携が難しい
といった課題を抱えやすい。
さらに、次のような企業戦略や外部要因によっても移行が必要になることがあります。
企業合併・買収に伴うシステム統合
新技術の採用による業務効率化・競争力強化
デジタルトランスフォーメーション(DX)推進
このように「守りの理由(老朽化・サポート終了など)」と「攻めの理由(DXや統合など)」の両面から、システム移行は発生します。単なるリスク回避にとどまらず、今後の成長戦略を支える重要な投資と位置付けることが大切です。
システム移行のパターン
システム移行には大きく分けて二つの代表的なパターンがあります。
オンプレミス環境への移行
自社内に新しいサーバーやネットワーク機器を導入し、既存システムを刷新する形です。セキュリティや運用ルールを自社で細かく管理できる一方で、ハードウェア調達や運用コストが課題となります。
クラウド環境への移行
AWSやAzure、Google Cloudといったクラウドサービスへ移行するパターンです。柔軟な拡張性や最新技術の活用が可能ですが、コストの見積もりやクラウド依存度への理解が必要となります。
また、これら以外にも多様なバリエーションが存在します。たとえば、
既存システムの一部のみを新環境に移す「部分移行」
新規にシステムを開発し、既存環境から必要なデータだけを移す「新規構築+データ移行」
といった方法です。
移行の方向性は「オンプレミスかクラウドか」という二択にとどまらず、業務システムの目的、求められる性能やセキュリティ、コスト制約などによって最適解は変わります。そのため、単なる環境の置き換えではなく「どの移行パターンが事業戦略に合うか」を慎重に検討することが重要です。
システム移行の方式
システム移行を成功させるには、方式を理解することが不可欠です。システム移行には、主に一括移行、段階的移行、並行運用といった手法があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。移行方式は、システム規模や複雑さ、重要度を考慮して慎重に決定する必要があります。
一括移行
一括移行は、ある時点で現行システムを完全に停止し、新しいシステムへ一斉に切り替える方式です。週末や連休など、長時間の停止が可能な期間を利用して入れ替えやデータ移行を行います。
メリット
一度に全てを移行できるため、コストや時間、手間を抑えやすいのが特徴です。また、現行システムをそのまま残すことで、失敗時に迅速に切り戻しできる安心感があります。
デメリット
システム全体を止める必要があるため、長時間の停止を伴います。移行後に大規模なトラブルが発生した場合、業務再開に大きなコストがかかるリスクもあります。
適用しやすいケース
長時間のシステム停止が許容され、コストを抑えたい場合に向いています。
段階的移行
段階的移行は、業務や機能、拠点といった単位ごとに分割し、順次切り替えていく方式です。
メリット
長時間の停止が不要で、移行後にトラブルが発生しても影響範囲を局所化できます。医療や金融など、止められない業務にも適しています。
デメリット
データやプログラムを細かく切り分ける必要があり、不整合のリスクが高まります。また複数回の移行を伴うため、全体の工数やコストが増えやすい傾向にあります。
適用しやすいケース
停止時間を確保できない場合や、リスクを分散して慎重に進めたい場合に有効です。
並行運用
並行運用は、新旧システムを一定期間同時に稼働させ、新システムの安定性を確認してから旧システムを停止する方式です。
メリット
新システムに不具合があっても旧システムが動いているため、業務影響を最小限に抑えられます。停止リスクを極力避けたい場合に安心できる方式です。
デメリット
両システムを同時に動かすため、二重入力や同期作業が発生し、担当者の負担やコストが増加します。さらに、データ不整合のリスクも高まるため、同期の仕組みづくりが欠かせません。
適用しやすいケース
業務を止められない場合や、リスクを最小限に抑えたい場合に適しています。
パイロット移行
パイロット移行は、一部のユーザーや部門に限定して新システムを導入し、効果やリスクを検証した上で全体展開する方式です。
メリット
限定的な範囲で試せるため、課題を事前に把握しやすく、全社展開時の失敗リスクを軽減できます。また、部分導入で得た知見を活かして移行をスムーズに進められます。
デメリット
検証期間を含むため、全体移行が完了するまでに時間がかかります。限定的な検証では把握できないリスクが残る可能性もあります。
適用しやすいケース
新システムを小規模で試し、リスクを抑えてから本格導入したい場合に適しています。
システム移行の手順

システム移行は計画から本番稼働まで複数の手順に分かれており、各ステップで適切なタスクと作業を行うことが成功の鍵となります。これらの工程を確実に進めることでスムーズなシステム移行を実現できます。
1. 移行元システムとデータの調査
システム移行を始める際に重要なのが、移行元システムとデータの詳細な調査です。これは移行対象を明確にし、その後の計画立案の基盤となります。
調査の主なポイントは以下の通りです。
システムの仕様や構成、利用中のOSやバージョン
定期的に稼働しているバッチ処理
データやファイルの形式、データ量
特にデータ量は作業負荷に直結するため、直近数年分だけを対象にするなど、移行対象を絞ることでコストを抑えられます。
新しいOSを採用する場合は、既存アプリケーションやデータベースの対応状況を事前に確認し、念のためバックアップを確保しておくことも欠かせません。また、不要なデータを整理してから移行に臨めば作業効率が高まり、移行後の運用もスムーズになります。
2. 移行計画書の作成
移行元システムとデータの調査が終わったら、次のステップは「移行計画書」の作成です。これはシステム移行プロジェクトを成功させるための設計図であり、「いつ・誰が・何をするか」を明確に示す重要な資料となります。
計画書に盛り込むべき内容は以下の通りです。
移行の目的と基本方針
移行方式(一括移行、段階的移行、並行運用など)
移行対象(データ・機能・ネットワーク構成など)
使用するツールやシステム構成
スケジュール(タイムラインとマイルストーン)
業務への影響と対策
プロジェクト体制と役割分担(責任者・作業者・トラブル対応係など)
特に作業を細分化し、マイルストーンを設定することで進捗管理がしやすくなり、遅延のリスクを減らせます。また、移行によって業務フローが一時的に変わる場合もあるため、業務担当者が理解しやすい形で説明しておくことも欠かせません。
計画が不十分だと、途中で判断が迷走したりリスク対応が遅れたりする恐れがあります。綿密な移行計画の策定こそが、プロジェクト成功の必須条件と言えるでしょう。
3. 移行リハーサルの実施
移行計画書を作成したら、本番移行の前に「移行リハーサル(移行テスト)」を行うことが欠かせません。これは、計画した手順やスケジュールに問題がないかを検証し、想定外のトラブルを事前に洗い出すための重要なプロセスです。
目的
移行作業が設定した時間枠内で完了できるかを確認する(時間計測)
準備した移行手順が実運用に耐えられるかを検証する(手順検証)
実施内容
可能な限り本番環境や実データに近い条件で移行を試行します。具体的には、環境設定 → データ受領 → データ投入 → 結果確認といった一連の流れを実際に行い、関係者間の作業受け渡しも含めてタイムチャートを検証します。
ポイント
システム規模や重要度に応じて複数回実施するのが望ましい
1回目で課題を洗い出し、2回目以降で解決策を反映させる
万一のトラブルに備えて、リカバリー策や切り戻し手順もあらかじめ準備しておく
これにより、本番時の不確定要素を大幅に減らし、想定外のトラブルにも落ち着いて対応できる体制を整えることができます。
4. 移行作業の実施
複数回のリハーサルを経て、計画書と手順書に問題がないと判断されたら、本番のシステム移行作業に進みます。作業は計画に沿って慎重に実施され、とくに中心となるのが現行システムから新システムへの「データ移行」です。
データ移行は量や品質によって複雑になりやすく、ETL(Extract, Transform, Load)ツールを使ってデータを抽出・変換・書き出す方法がよく採用されます。一つの誤りが後続に大きな影響を与えるため、手順書は誰が見ても理解できる形にまとめ、チェック体制を設けて作業ミスを防ぐことが重要です。
また、本番環境ならではの差異や予期せぬ課題が発生する可能性もあります。そのため、緊急時の連絡先やエスカレーションルートを明確にし、判断を迷わず上司や有識者に仰げる体制を整えておく必要があります。
さらに、移行作業が終わったからといって即座に運用を開始できるわけではありません。他システムとの連携確認や、切り替えのタイミング調整といった仕上げの工程にも注意が必要です。
5. 新システムへのテストと運用開始
移行作業が完了したら、次のステップは新システムのテストと検証です。ここで問題がないことを確認して初めて、本格的な運用を開始できます。
テストの目的
新システムが正常に稼働し、業務を滞りなく支えられるかを確認することです。単に動くかどうかだけでなく、想定外の状況でも対応できるかを検証する必要があります。
主な確認内容
通常の業務サイクルを新システム上で実行できるか
高負荷時の動作やリソース状況
障害発生時の切り替え手順が適切に機能するか
データ検証の重要性
移行したデータに欠損や形式の不備がないかを必ずチェックします。データが完全に移行されていない状態で稼働を始めると、業務に大きな影響を与える可能性があります。必要に応じて独自の検証スクリプトを作成し、移行データの完全性を確認できるようにしておくことが有効です。
運用開始時の留意点
テストを経て運用を開始しても、移行はそこで終わりではありません。運用担当者に重要事項を引き継ぎ、検証用スクリプトや手順を後から参照できる形で残しておくなど、安定稼働に向けた準備を整えることが大切です。
システム移行のリスクと注意点
システム移行は、企業の重要な情報システムに直接関わるため、様々なリスクを伴います。これらのリスクと注意点を事前に把握し、対策を講じることが、失敗を避けるために不可欠です。
データ移行のリスク
データ移行はシステム移行の中でも最も重要かつリスクの高い工程です。主なリスクは「データ損失・破損」「不整合」「業務への混乱」です。
データ損失や破損は、システム間の非互換性や人為的ミス、不完全な転送などが原因で発生します。特に基幹システムの移行では数千万件規模のデータを扱うこともあり、日中に処理を行うと他のシステムや通信に影響を与える可能性があります。そのため業務時間外での実行や分割移行が望まれます。
また、移行元と移行先のデータ構造が異なることも多く、スキーマ変更やマッピング処理に大きな工数が必要です。移行漏れや不一致を防ぐためには、事前のバックアップ取得とデータ検証の徹底が不可欠です。
業務停止のリスク
システム移行は業務停止を伴う可能性があり、とくに一括移行では基幹業務全体に影響が及ぶリスクが高まります。システム規模やデータ量によっては長時間の停止が必要になり、その間の機会損失や顧客への影響も考慮しなければなりません。
移行が失敗した場合、業務が滞りコスト増加にも直結します。これを防ぐには、事前に想定される業務影響を洗い出し、臨時的な運用方法を準備しておくことが重要です。
システム互換性の問題
新旧システム間の互換性も大きな課題です。OSやデータベース、クラウド環境が異なる場合、データ構造や形式が変わり、プログラム修正やSQL変更、マッピング作業が必要になります。
このとき、新旧両方のシステム仕様を深く理解していないと、不整合やNULL値の発生といった問題につながります。さらに、ネットワーク環境の変更も伴う場合は、既存アプリケーションが新しい設定で動作できるかの確認が不可欠です。
トラブル発生時の対応計画
どれだけ準備をしても、移行中のトラブルは避けられません。そのため、事前に「コンティンジェンシープラン(非常時対応計画)」を用意しておくことが大切です。
内容としては、旧システムへ戻す切り戻し手順、緊急時の連絡体制、一時的な業務継続方法などを明確にしておきます。特にバックアップの取得と切り戻しテストは必須です。
こうした対応計画を準備しておけば、移行中に問題が起きても迅速かつ冷静に対応でき、事業継続性を確保できます。
システム移行を成功させるポイント

システム移行の成功は、単なる技術的な作業に留まらず、入念な準備と計画、関係者間の連携、そして万全のテスト体制が不可欠です。システム移行を円滑に進め、失敗を回避するための重要なポイントを解説します。
詳細な移行計画
システム移行を成功させるためには、具体的で実行可能な移行計画が欠かせません。計画はプロジェクト初期から検討し、関係者全員で共有する必要があります。
計画には、移行の目的・範囲、採用する移行方式、使用ツール、スケジュール(マイルストーンや予備期間を含む)、業務への影響と回避策を盛り込みます。特に工数や費用を正確に見積もり、業務プロセスの変更点も分かりやすく整理することが重要です。計画は進捗に合わせて更新し、判断が迷走しないよう管理します。
事前教育と情報共有
移行を円滑に進めるには、技術面だけでなく利用者への教育と情報共有も不可欠です。
業務担当者が新システムをスムーズに使えるように、事前にトレーニングや操作マニュアルを整備します。また、発注者・ベンダー・利用部門など関係者間で定期的に情報を共有し、役割分担や緊急時の連絡体制を明確にしておくことで、混乱を防ぎ、移行後の定着もスムーズになります。
専門家への外部委託
システム移行は高度な知識と経験を要するため、社内リソースだけで対応が難しい場合は専門家への委託が効果的です。
外部の専門家は最適な移行方式の選定やリスク対策を支援し、作業を効率化します。特に基幹システムや大規模クラウド移行のような難易度の高い案件では、専門家の知見が失敗リスクを大幅に減らす強力な手段となります。
綿密なテストと検証
移行作業が終わったら、徹底したテストと検証が必要です。
通常業務の流れに沿ってシステムが正しく動作するかを確認し、負荷試験や障害時の切り替えテストも実施します。さらに、移行データの完全性をチェックするためにスクリプトやツールを活用し、品質を確実に担保します。
テストの目的は単に不具合を見つけることではなく、新システムが業務を安定して支えられるかを保証することです。
システム移行でよくある質問
システム移行に関してよくある質問と回答をQ&A形式でご紹介します。
Q1. システム移行中に業務を停止させる必要はありますか?
A1. 一括移行では一時的な停止が必要になることが多いですが、段階的移行や並行運用、パイロット移行を選べば停止時間を短縮、あるいはゼロにすることも可能です。
Q2. どのようなデータが移行対象となりますか?
A2. 顧客情報や取引履歴など現行システムのデータ全般が対象です。ただし全件ではなく、直近数年分だけを移行するなど絞り込みも可能です。
Q3. システム移行を外部に委託するメリットは何ですか?
A3. 専門家の知識と経験を活用できるため、最適な計画策定やリスク対策が行え、社内の負担を減らして成功率を高められます。
Q4. 移行後にシステムトラブルが発生した場合の対応策は?
A4. あらかじめ「コンティンジェンシープラン」を準備し、切り戻し手順や緊急連絡体制を明確にしておきます。定期的なバックアップや切り戻しテストも有効です。
まとめ
本記事では、システム移行の基本的な概念から、成功に導くための具体的な手順と注意点について詳しく解説しました。システム移行は、企業の成長や変化に対応するための重要なプロセスであり、単なる技術的な作業に留まらない複雑なプロジェクトです。
株式会社デパートでは、安全かつスムーズなシステム移行をご提案・サポートしています。まずはお気軽にご相談ください。
Contact
制作のご依頼やサービスに関するお問い合わせ、
まだ案件化していないご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
- この記事をシェア