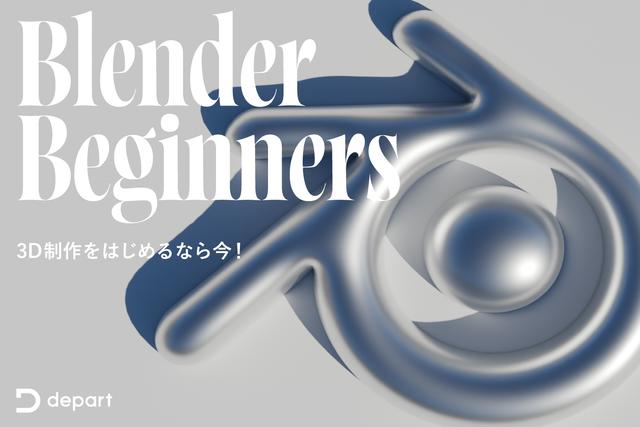- Share On
目次
目次
- なぜ今、統合報告書のWeb化(デジタル化)が求められるのか?
- 統合報告書をWebサイトで公開する5つのメリット
- メリット1:優れた検索性で必要な情報へスムーズにアクセスできる
- メリット2:動画やグラフで複雑な情報を分かりやすく伝えられる
- メリット3:常に最新のESGデータへタイムリーに更新できる
- メリット4:アクセス解析でステークホルダーの関心事を把握できる
- メリット5:関連コンテンツへの導線で企業理解を多角的に深める
- 伝わる統合報告サイトを制作するための4つのポイント
- ポイント1:企業の価値創造に至るストーリーを明確に描く
- ポイント2:マテリアリティ(重要課題)と具体的な取り組みを紐づける
- ポイント3:インフォグラフィックでKPIの進捗状況を可視化する
- ポイント4:スマートフォンでも快適に閲覧できるデザインにする
- Web化した統合報告書の価値を最大化する活用方法
- プレスリリースやSNSで特定ページを共有し情報を届ける
- 投資家との対話や採用活動でのコミュニケーションに役立てる
- まとめ
多くの企業が統合報告書をPDFで公開する中、その情報をWebサイトとして発信する動きが加速しています。 単にデジタル化するだけでなく、Webの特性を最大限に活かすことで、報告書の価値は大きく変わります。
優れた検索性やリッチなコンテンツ表現、データ活用といったWebサイトならではの利点は、ステークホルダーとのエンゲージメントをより深めることにつながります。
本記事では、統合報告書をWeb化するメリットや、伝わるサイトを制作・活用するためのポイントを解説します。
なぜ今、統合報告書のWeb化(デジタル化)が求められるのか?
投資家や顧客、従業員といったステークホルダーの情報収集は、スマートフォンやPCが中心となっています。分厚いPDFファイルは、特にモバイル環境での閲覧性が低く、目的の情報を見つけ出しにくいという課題を抱えています。
企業が伝えたい価値創造ストーリーやESGへの取り組みを、ステークホルダーが求める形で的確に届けるためには、Webサイトという最適なメディアを選択することが重要です。これにより、企業情報のアクセシビリティが向上し、より深い理解を促進できます。

今回はウェブアクセシビリティが重要視される理由を紹介したのちに、ウェブアクセシビリティ対応を行わない場合のリスクを解説します。
統合報告書をWebサイトで公開する5つのメリット
統合報告書をPDFからWebサイトへ移行させることで、従来の報告書が抱えていた多くの課題を解決できます。 Webサイトならではの機能や特性を活かすことは、単なる情報開示の効率化にとどまらず、ステークホルダーとの関係構築を強化する上で大きな利点をもたらします。
ここでは、優れた検索性や表現力、更新性、アクセス解析、他コンテンツとの連携という5つの具体的なメリットについて解説します。

【統合報告書をWebサイトで公開する5つのメリット】
優れた検索性で必要な情報へスムーズにアクセスできる
動画やグラフで複雑な情報を分かりやすく伝えられる
常に最新のESGデータへタイムリーに更新できる
アクセス解析でステークホルダーの関心事を把握できる
関連コンテンツへの導線で企業理解を多角的に深める
メリット1:優れた検索性で必要な情報へスムーズにアクセスできる
数百ページに及ぶこともあるPDF形式の統合報告書では、読者が特定の情報を探し出すのに手間がかかります。
一方、Webサイトとして公開すれば、サイト内検索機能によってキーワードを入力するだけで、関連ページへ瞬時にアクセス可能です。また、Googleなどの外部検索エンジンからも直接個別のページにたどり着けるため、例えば「企業名+TCFD」といった具体的な関心事を持つユーザーを的確に情報へ導けます。
これにより、投資家やアナリストが必要とするデータへのアクセス性が飛躍的に向上し、情報伝達の効率が高まります。
メリット2:動画やグラフで複雑な情報を分かりやすく伝えられる
Webサイトでは、テキストや静止画だけでは表現が難しい情報を、多様なコンテンツ形式を用いて分かりやすく伝えられます。
例えば、経営トップのメッセージを動画で配信すれば、その表情や声のトーンから、事業にかける情熱やビジョンをより直接的に訴求できるでしょう。また、事業モデルやバリューチェーンといった複雑な概念は、アニメーションを用いることで直感的な理解を促せます。
インタラクティブなグラフを導入し、ユーザーが操作することで指標を切り替えられるようにするなど、リッチなコンテンツ表現は読者のエンゲージメントを高めます。
メリット3:常に最新のESGデータへタイムリーに更新できる
年に一度発行される統合報告書では、情報が公開された時点ですでに過去のものとなっているケースが少なくありません。特に、投資家の関心が高いESG関連のデータやKPIの進捗状況は、常に最新の状態を保つことが望ましいです。
Webサイトであれば、年度の途中でも内容を随時更新できるため、新たな取り組みや目標達成といった情報をタイムリーに発信できます。情報の鮮度と透明性を高めることは、ステークホルダーからの信頼獲得に直結し、企業の誠実な姿勢を示すことにもなります。
この更新性の高さは、速報性が求められる現代の情報開示において大きな強みとなるコンテンツです。
メリット4:アクセス解析でステークホルダーの関心事を把握できる
冊子やPDFでは、どの情報が、誰に、どれだけ読まれたかを把握することは困難です。 しかし、Webサイトであればアクセス解析ツールを導入することで、ページごとの閲覧数、ユーザーの滞在時間、どのような検索キーワードで流入したかといったデータを詳細に分析できます。
例えば、特定のESG課題に関するページの閲覧数が多ければ、その分野への関心が高いと判断できます。 これらのデータに基づき、次年度の報告書で重点的に解説すべきコンテンツを特定したり、IR活動の戦略を練り直したりするなど、客観的な根拠に基づいたコミュニケーション改善が可能になるのです。
メリット5:関連コンテンツへの導線で企業理解を多角的に深める
統合報告サイトは、企業全体の情報資産をつなぐハブとしての役割を担います。 報告書内で言及されている個別の事業戦略やサステナビリティ活動について、より詳細な情報が掲載されているコーポレートサイトの該当ページへリンクを設定することで、読者は関心を持った分野を深掘りできます。
また、企業の理念や文化を紹介するコンテンツから採用情報ページへ誘導することも可能です。 このように、関連コンテンツへの導線を戦略的に設計することで、読者は断片的な情報ではなく、企業活動の全体像を多角的に理解できるようになり、エンゲージメントの向上が期待できます。
伝わる統合報告サイトを制作するための4つのポイント
統合報告書のWeb化によるメリットを最大化するには、単に冊子の内容をWebページに移植するだけでは不十分です。 ステークホルダーに企業の価値創造ストーリーを的確に伝え、深い理解を促すためには、Webの特性を活かした戦略的なサイト設計が欠かせません。
ここでは、成果につながる統合報告サイトを制作する上で特に重要となる、ストーリー設計、マテリアリティの紐づけ、情報の可視化、そして閲覧環境への配慮という4つのポイントについて解説します。
【伝わる統合報告サイトを制作するための4つのポイント】
企業の価値創造に至るストーリーを明確に描く
マテリアリティ(重要課題)と具体的な取り組みを紐づける
インフォグラフィックでKPIの進捗状況を可視化する
スマートフォンでも快適に閲覧できるデザインにする
ポイント1:企業の価値創造に至るストーリーを明確に描く
統合報告書の最も重要な役割は、企業が社会においてどのような価値を創造していくのか、その一貫したストーリーを伝えることです。
Webサイトを制作する際は、トップメッセージから事業概要、財務・非財務情報、ガバナンス体制といった各コンテンツが、この価値創造ストーリーという一本の軸で有機的につながるように情報構造を設計しなくてはなりません。ナビゲーションやページ間の内部リンクを工夫し、読者が迷うことなくストーリーを追えるように導くことが重要です。
個別の情報が散在するのではなく、企業の全体像が立体的に浮かび上がるような構成を目指します。
ポイント2:マテリアリティ(重要課題)と具体的な取り組みを紐づける
企業が特定したマテリアリティ(重要課題)は、それに対する具体的なアクションプランとセットで開示されて初めて意味を持ちます。
Webサイト上では、それぞれのマテリアリティに対して、関連する事業活動、具体的な目標(KPI)、そして足元の進捗状況や実績を明確に紐づけて提示することが不可欠です。
例えば、「人財育成」というマテリアリティを掲げるページには、研修制度の概要や従業員エンゲージメントスコアの推移といった具体的なコンテンツへのリンクを設置します。
この紐づけにより、企業が重要課題に真摯に取り組んでいる姿勢を具体的に示し、開示情報の説得力を高めます。
ポイント3:インフォグラフィックでKPIの進捗状況を可視化する
温室効果ガス排出量や女性管理職比率といったKPIの推移は、企業の戦略実行度を測る上で重要な指標ですが、数字の羅列だけではその意味合いが伝わりにくいものです。
Webサイトでは、こうした数値データをインフォグラフィックやインタラクティブなグラフを用いて視覚的に表現することが極めて効果的です。目標値と実績値を並べて表示したり、過去からの推移を折れ線グラフで示したりすることで、読者は進捗状況を直感的に把握できます。
複雑な情報を分かりやすく見せる工夫は、コンテンツの魅力を高め、ステークホルダーの理解を促進します。
ポイント4:スマートフォンでも快適に閲覧できるデザインにする
現在、ステークホルダーはPCだけでなく、スマートフォンやタブレットなど多様なデバイスを用いて情報にアクセスします。 そのため、統合報告サイトはレスポンシブWebデザインを採用し、あらゆる画面サイズで最適に表示されるように構築することが必須条件です。
小さな画面でも文字が読みやすく、タップしやすいボタン配置にするなど、ユーザーのストレスを軽減する配慮が求められます。 特に移動中などに情報を確認するユーザーも想定し、要点を素早く把握できるようなコンテンツ構成を意識することも重要です。 デバイスを問わない快適な閲覧体験の提供は、サイトからの離脱を防ぎます。

本記事では、レスポンシブデザインの基本概念から具体的な作り方、さらに導入における利点と課題までを詳しく解説します。

本記事では、UIとUXの基本的な違いを解説し、それぞれの役割や重要性について詳しく説明します。具体的な事例を交えながら、Webサイト改善のための実践的なヒントをお伝えします。
Web化した統合報告書の価値を最大化する活用方法
質の高い統合報告サイトを制作した後は、その価値を最大限に引き出すための活用フェーズが重要になります。サイトを公開して待つだけでなく、企業側から積極的に情報を届け、多様なステークホルダーとの対話に役立てることで、エンゲージメントはより一層深まります。
Webサイトが持つ「共有のしやすさ」や「アクセスの手軽さ」という利点を活かし、IRや広報、採用といった様々な企業活動の場面で戦略的に活用していく方法を紹介します。

プレスリリースやSNSで特定ページを共有し情報を届ける
Webサイトの大きな利点は、ページごとに固有のURLが存在するため、伝えたい情報をピンポイントで共有できることです。 例えば、中期経営計画の進捗について発表する際、その詳細を解説したページのURLをプレスリリースに記載したり、公式SNSで発信したりできます。
これにより、ステークホルダーは膨大な報告書の中から該当箇所を探す手間なく、直接的な情報アクセスが可能となります。 重要なトピックをタイムリーに、かつ効率的に届けるこの手法は、情報発信の効果を格段に高めます。
サイトのコンテンツを細分化し、共有しやすい単位で構成しておくことも重要です。
投資家との対話や採用活動でのコミュニケーションに役立てる
Web化された統合報告書は、様々なステークホルダーとの対話における強力なコミュニケーションツールとなります。
投資家との1on1ミーティングの場で、タブレットを用いてサイト上のグラフやデータを示しながら説明すれば、より具体的で説得力のある対話が実現できます。
また、採用説明会では、学生に企業のビジョンやサステナビリティへの取り組みを伝える際にサイトを提示することで、事業内容や企業文化への深い理解を促せます。
企業の魅力を多角的に伝えることで、共感を醸成し、エンゲージメントの高い人材獲得にも貢献するでしょう。
まとめ
統合報告書のWeb化は、情報開示の形式をPDFからWebサイトへ変えるという単純な置き換えではありません。
優れた検索性、リッチな表現力、タイムリーな更新性、そしてアクセス解析に基づく改善といったWebの特性を最大限に活用することで、企業とステークホルダー間のコミュニケーションを質的に向上させる戦略的な取り組みです。
価値創造ストーリーを軸に据えたサイトを構築し、多様なチャネルで積極的に活用することが、企業価値の継続的な向上に不可欠となります。
これからの情報開示においては、企業姿勢を効果的に伝えるための統合報告サイトの存在がより一層重要になるでしょう。
デパートではサステナビリティサイトの制作支援を行なっております。専門チームがサステナビリティサイト構築/改修のトータルプランを提案いたします。 統合報告書のWeb化に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。
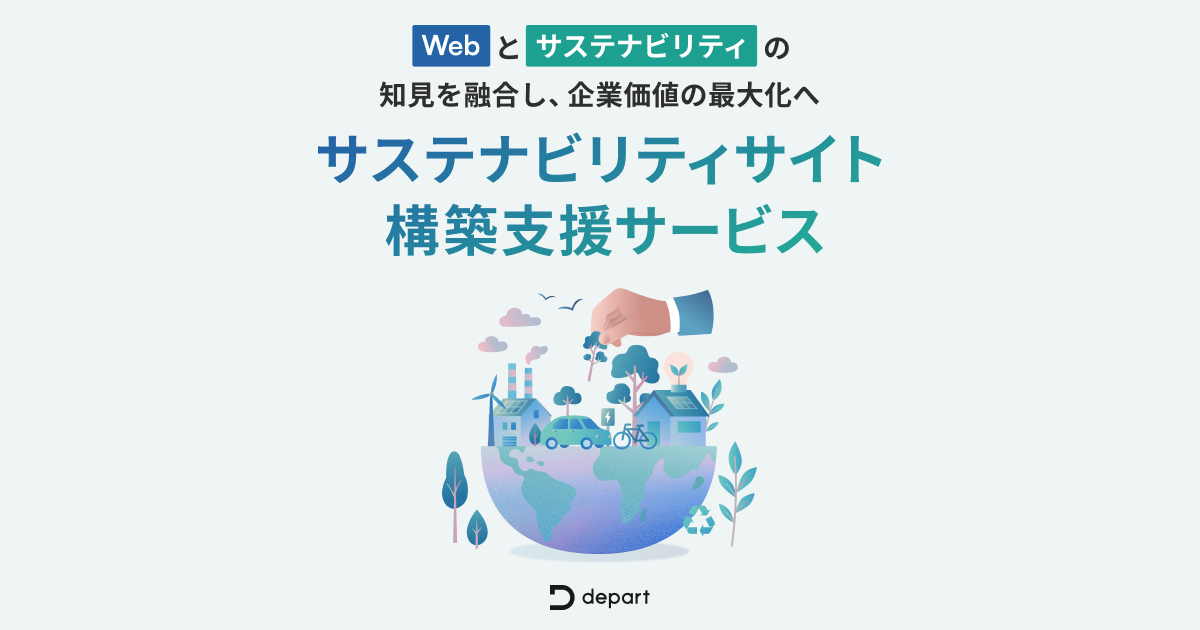
株式会社デパートで提供するサステナビリティサイト構築支援サービスでは、 Web制作とサステナビリティの知見を融合し、貴社のサステナビリティサイト構築に関連する、 戦略立案からサイト構築、そして継続的な運用・改善まで、全てお任せいただけます。

サスティナビリティサイトに関するご相談、 抱えられている課題など、お気軽にご相談ください。
Contact
制作のご依頼やサービスに関するお問い合わせ、
まだ案件化していないご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
- この記事をシェア