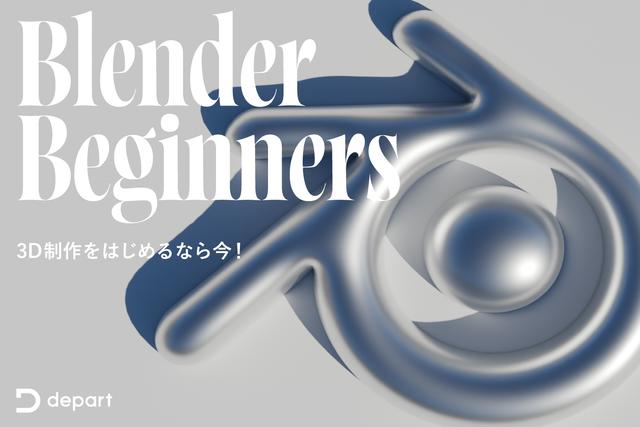- Share On
目次
目次
- そもそもサステナビリティサイトとは何か?
- なぜ今サステナビリティサイトの制作が重要視されるのか
- 企業のブランドイメージを向上させるため
- 投資家からの資金調達を円滑に進めるため
- 従業員のエンゲージメントを高める効果があるため
- 優秀な人材の採用競争で有利になるため
- サステナビリティサイトの制作手順
- 1. ヒアリング
- 2. 調査・コンサルティング(1〜2カ月)
- 3. 企画・要件定義(1〜2カ月)
- 4. 情報設計(1カ月)
- 5. 取材/原稿作成(1〜2カ月)
- 6. UX・デザイン(1〜2カ月)
- 7. 実装・公開(1〜2カ月)
- 8. 運用・改善
- 制作会社へ依頼する前に社内で準備しておくべきこと
- サステナビリティやSDGsに関する社内の理解を深める
- 自社の事業と社会課題の関連性を洗い出す
- サイトで伝えたいターゲットとメッセージを明確にする
- 失敗しないサステナビリティサイト制作の3つのポイント
- 実現可能で継続できる取り組みを掲載する
- 専門用語を避け誰にでも伝わる言葉を選ぶ
- 事実に基づかない誇張した表現は使わない
- 信頼できるサステナビリティサイト制作会社の選び方
- サステナビリティに関する専門知識や実績が豊富か
- 企業の魅力を引き出す企画提案力があるか
- デザイン性と情報伝達のバランス感覚に優れているか
- サステナビリティサイト制作にかかる費用と期間の目安
- よくある質問
- Q. どの情報をサイトに掲載すべきですか?
- Q. 統合報告書(年次レポート)とどう違うのですか?
- Q. データはどのくらいの頻度で更新すべきですか?
- Q. 多言語対応は必要ですか?
- Q. 外部評価(ESG格付けなど)は掲載したほうがいいですか?
- まとめ
近年、企業のWeb担当者や広報担当者、IR担当者、経営層、あるいはサステナビリティ推進部門の担当者の間で、サステナビリティサイト制作への関心が高まっています。企業価値が売上や利益だけでは測れない時代になり、環境・社会問題への取り組みは企業の重要な責務となっているため、その情報を発信するサステナビリティサイトは不可欠です。
本記事では、サステナビリティサイト制作の必要性から具体的な手順、制作会社選定のポイント、費用・期間の目安、そしてよくある疑問点まで、網羅的に解説します。 これらの情報を参考に、自社に最適なサステナビリティサイトの制作を進めていきましょう。
デパートではサステナビリティサイトの制作支援を行なっております。専門チームがサステナビリティサイト構築/改修のトータルプランを提案いたします。
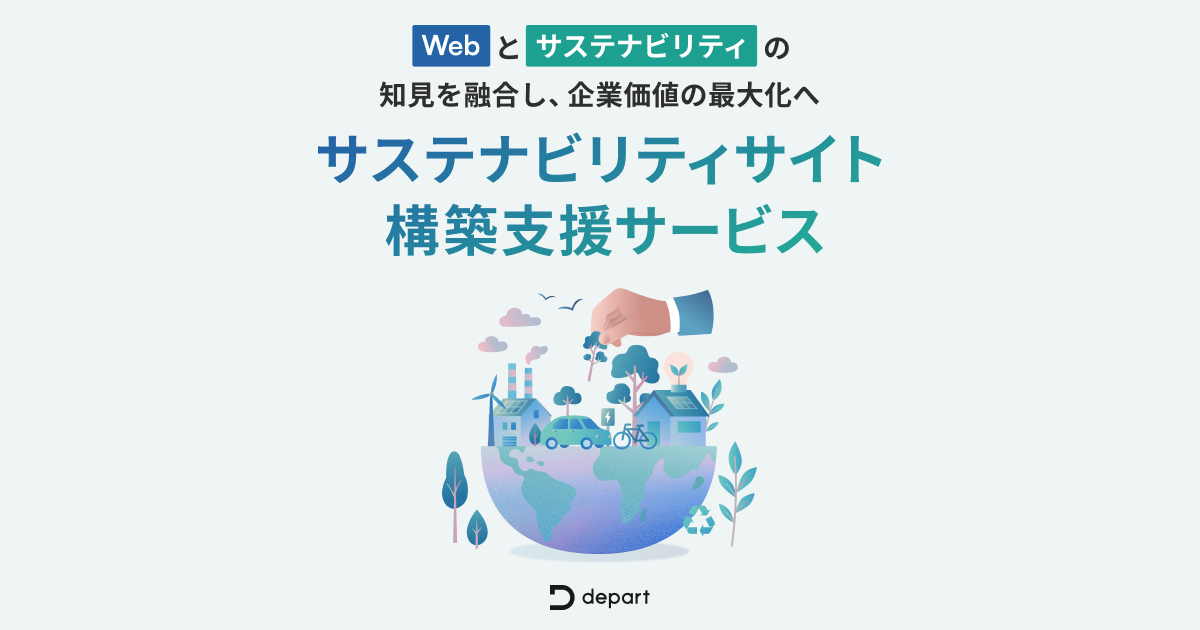
株式会社デパートで提供するサステナビリティサイト構築支援サービスでは、 Web制作とサステナビリティの知見を融合し、貴社のサステナビリティサイト構築に関連する、 戦略立案からサイト構築、そして継続的な運用・改善まで、全てお任せいただけます。

サスティナビリティサイトに関するご相談、 抱えられている課題など、お気軽にご相談ください。
そもそもサステナビリティサイトとは何か?

サステナビリティサイトとは、企業が持続可能性への取り組みや社会貢献活動に関する情報を集約し、ステークホルダーに向けて発信するWebサイトのコンテンツを指します。サステナビリティは「持続可能性」を意味し、環境・社会・経済の3つの側面から持続可能な発展を目指すという考え方に基づいています。単なる企業の利益追求だけでなく、地球環境問題や社会問題に対して企業がどのように向き合い、どのような具体的な取り組みを行っているかを伝える役割を担っています。 企業の理念や具体的な行動、目標などを多角的に伝えることで、社会との対話の場となる重要な情報発信ツールといえます。
なぜ今サステナビリティサイトの制作が重要視されるのか
近年、企業のサステナビリティサイトの制作が重要視されている背景には、地球環境問題や社会問題への関心の高まりがあります。企業がこれらの問題にどのように取り組んでいるかを示すことは、もはや企業の重要な責務であり、透明性を高め、持続可能なビジネス実践を促進するために不可欠な要素となっています。
企業のブランドイメージを向上させるため
サステナビリティへの取り組みを発信することは、企業の信頼性を高め、ブランドイメージを向上させる上で極めて重要です。社会や環境に配慮した企業活動は、ビジネス取引において有利に働き、顧客からの好印象にもつながります。 企業が継続的にサステナビリティ活動を行い、成果を上げることができれば、企業のブランドイメージの向上に直結すると言えるでしょう。SNSや広告などの拡散により、その認知拡大に比例し、評価も高まる傾向があります。
投資家からの資金調達を円滑に進めるため
近年、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資が世界的に拡大しており、投資家は企業の財務情報だけでなく、非財務情報、特にサステナビリティへの取り組みを重視して投資判断を行うようになっています。 サステナビリティサイトを通じて、企業のサステナビリティ経営の仕組みや戦略、運用状況、そして企業価値への影響を明確に伝えることは、投資家からの信頼を獲得し、資金調達を円滑に進める上で不可欠な評価基準となります。
従業員のエンゲージメントを高める効果があるため
サステナビリティサイトは、対外的な情報発信だけでなく、社内にも魅力的な影響をもたらします。サイト制作の過程で、自社の社会活動を再発見する機会が生まれ、従業員は自身の仕事の意義や企業への誇りを感じやすくなるでしょう。 これにより、従業員のエンゲージメントが向上し、企業の一員として社会貢献に携わる意識が高まる効果が期待されます。
優秀な人材の採用競争で有利になるため
近年、求職者は企業の利益だけでなく、社会貢献性や倫理観を重視する傾向が強まっています。特に若い世代は、環境問題や社会課題への関心が高く、自身のキャリアを通じて社会に貢献したいという意識を持つ人が増えています。
 引用:WWFジャパン 就活のカギは「環境」? 学生は企業の取り組みをどう見ているか
引用:WWFジャパン 就活のカギは「環境」? 学生は企業の取り組みをどう見ているか
https://www.wwf.or.jp/activities/lib/5668.html
サステナビリティへの積極的な取り組みをWebサイトで発信することは、企業の社会的な責任感を明確に示し、そうした価値観を持つ優秀な人材を引きつける上で、採用競争における有利な評価点となります。
サステナビリティサイトの制作手順
 サステナビリティサイトの制作は、企業の理念や取り組みを適切に伝えるために体系的な手順を踏むことが重要です。一般的な制作の流れは以下の通りです。
サステナビリティサイトの制作は、企業の理念や取り組みを適切に伝えるために体系的な手順を踏むことが重要です。一般的な制作の流れは以下の通りです。
それぞれ目安となる期間が記載されていますが、それぞれ並走して進むものですので、全体の期間については、記事末尾の「サステナビリティサイト制作にかかる費用と期間の目安」をご確認ください!
ヒアリング
調査・コンサルティング(1〜2カ月)
企画・要件定義(1〜2カ月)
情報設計(1カ月)
取材/原稿作成(1〜2カ月)
UX・デザイン(1〜2カ月)
実装・公開(1〜2カ月)
運用・改善
1. ヒアリング
制作の第一段階として、現状の課題や目指す情報開示のあり方について、企業からヒアリングを行います。この際、現状のサイトがある場合はその分析も実施し、課題を抽出します。 企業のビジネスとコミュニケーションの全体像を把握することで、サイトが公開され運用されていくまでの最適な土台を築いていきます。
2. 調査・コンサルティング(1〜2カ月)
専門家によるトレンド分析や有識者評価レポート、競合分析、ユーザビリティ診断、アクセス解析などを通じて、サステナビリティサイト構築に向けた現状と理想のギャップを明確にしていき、企画や戦略の構築につなげます。
3. 企画・要件定義(1〜2カ月)
ヒアリングで抽出された課題と目標や、調査結果に基づき、サステナビリティサイトで達成したい目標やあるべき姿を共有し、中長期的な視点も踏まえて必要なマイルストンを策定します。サイトリニューアルの場合は、社内コンセンサスを得るためのプロジェクト計画書作成支援も行われることがあります。 この段階で、サイトの戦略や具体的な要件を定義し、方向性を固めます。
4. 情報設計(1カ月)
定義された戦略と要件に基づき、サイト全体の情報構造を設計します。 どのような情報をどこに配置するか、ユーザーが求める情報にスムーズにアクセスできるかなどを考慮し、サイトマップやワイヤーフレームを作成します。 サステナビリティに関する情報は多岐にわたるため、分かりやすく整理された情報設計が重要です。
5. 取材/原稿作成(1〜2カ月)
情報設計に基づいて、掲載するコンテンツの制作を行います。 トップメッセージ、サステナビリティ基本方針、マテリアリティ(重要課題)、具体的な取り組み、レポート(数値データ)・資料、活動記録など、必要な情報を網羅的に作成します。 必要に応じて、社内担当者への取材や、写真・動画などの素材収集も実施します。
6. UX・デザイン(1〜2カ月)
コンテンツを効果的に伝えるためのUX(ユーザーエクスペリエンス)とデザインを検討します。ユーザーが快適に情報を閲覧できるよう、見やすさ、分かりやすさ、操作性を考慮したデザインを目指します。サステナビリティサイトの多くは、ユニバーサルデザインやウェブアクセシビリティの対応をすることで、なるべく誰しもが情報を閲覧できるようなデザインを作成する必要があります。 サステナビリティのメッセージに合ったトーン&マナーで、企業の個性を表現することも重要です。近年では、環境負荷の低いWebデザイン(サステナブルWebデザイン)も注目されています。
7. 実装・公開(1〜2カ月)
デザインとコンテンツが完成したら、いよいよWebサイトとして構築し公開する段階です。効率的な運用のため、CMS(コンテンツ管理システム)の導入は、公開後の運用・更新を容易にします。また、あらゆるユーザーが情報にアクセスできるよう、ウェブアクセシビリティへの配慮が重要です。公開前には、機能の動作確認や表示チェックはもちろんのこと、ウェブアクセシビリティの検証も含め、最終的な品質確認を徹底することが大切です。
8. 運用・改善
サイト公開後も、継続的な運用と改善が不可欠です。アクセス解析を通じてユーザーの行動を分析し、コンテンツの改善や新たな情報発信の企画に活かします。 サステナビリティに関する情報は常に変化するため、定期的な情報更新は企業の信頼性を高める上で非常に重要です。
制作会社へ依頼する前に社内で準備しておくべきこと
 サステナビリティサイト制作を外部の制作会社に依頼する際は、スムーズなプロジェクト進行と質の高いサイト構築のために、事前に社内で準備しておくべき点がいくつかあります。 これらの準備を行うことで、制作会社との連携が円滑になり、自社の意図を正確に伝えられます。
サステナビリティサイト制作を外部の制作会社に依頼する際は、スムーズなプロジェクト進行と質の高いサイト構築のために、事前に社内で準備しておくべき点がいくつかあります。 これらの準備を行うことで、制作会社との連携が円滑になり、自社の意図を正確に伝えられます。
サステナビリティやSDGsに関する社内の理解を深める
サステナビリティサイトを制作する上で、まず社内全体でサステナビリティやSDGs(持続可能な開発目標)に関する理解を深めることが不可欠です。SDGsは国連が提唱する17の目標と169のターゲットから構成されており、企業活動と密接に関連しています。社内での理解を深めることで、サイト制作の方向性が定まり、各部門からの情報収集や協力もスムーズに進むでしょう。
自社の事業と社会課題の関連性を洗い出す
次に、自社の事業活動がどのような社会課題と関連しているのかを具体的に洗い出すリサーチが必要です。これは、サステナビリティサイトで発信する主要なテーマ(マテリアリティ)を特定するために重要です。例えば、環境問題、労働環境、サプライチェーンにおける人権など、自社の事業が与える影響を多角的に分析し、具体的な取り組みにつなげるための基盤を築きます。
サイトで伝えたいターゲットとメッセージを明確にする
サステナビリティサイトは、株主・投資家、顧客、従業員、求職者など、多様なステークホルダーが閲覧します。それぞれのターゲット層に対して、どのようなメッセージを、どのようなトーンで伝えたいのかを明確に定義することが重要です。ターゲットとメッセージを明確にすることで、コンテンツの内容やデザインの方向性が定まり、より効果的なサステナビリティサイトを構築できます。
失敗しないサステナビリティサイト制作の3つのポイント
サステナビリティサイトを成功させるためには、単に情報を羅列するだけでなく、ステークホルダーに共感を与え、信頼を築くための工夫が必要です。 以下の3つのポイントを意識して制作を進めましょう。
デパートではサステナビリティサイトの制作支援を行なっております。サステナビリティの専門知識を持つチームが、企業の戦略策定から対応させていただきます。ぜひお問合せください。
実現可能で継続できる取り組みを掲載する
サステナビリティサイトに掲載する取り組みは、実現可能であり、継続的に実行できるものであることが重要です。一度きりの活動や、実態と乖離した内容は、かえって企業の信頼性を損ねる可能性があります。継続的な活動記録や具体的な成果を定期的に更新することで、企業の本気度と透明性を示すことができ、ステークホルダーからの信頼獲得につながります。
専門用語を避け誰にでも伝わる言葉を選ぶ
サステナビリティやSDGsに関する専門用語は多岐にわたりますが、サイトの読者は必ずしもこれらの用語に精通しているとは限りません。誰にでも理解できるよう、専門用語は避け、平易な言葉で説明すること、あるいは用語集などを設けて補足することが推奨されます。具体的な取り組みを分かりやすい表現で伝えることで、幅広い層のステークホルダーにメッセージが届きやすくなります。
事実に基づかない誇張した表現は使わない
サステナビリティサイトにおいて、事実に基づかない誇張した表現は厳禁です。企業の信頼性を損なうだけでなく、ステークホルダーからの不信感につながる可能性があります。客観的なデータや具体的な事例に基づいて、正確な情報を伝えることが最も重要です。透明性のある情報開示を心がけ、誠実な姿勢でサステナビリティへの取り組みを発信しましょう。
信頼できるサステナビリティサイト制作会社の選び方
サステナビリティサイトの制作は専門的な知識と経験を要するため、信頼できる制作会社を選ぶことが成功の鍵となります。 制作会社を選ぶ際は、以下の4つのポイントに注目しましょう。
サステナビリティに関する専門知識や実績が豊富か
サステナビリティサイト制作には、環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する深い専門知識が不可欠です。 制作会社がこれらの分野に関する最新の動向やガイドライン(GRIスタンダード、SASBなど)を理解しているか、また、これまでの制作実績として多様な業界のサステナビリティサイトを手がけているかを確認しましょう。 専門性の高い知識と豊富な実績は、信頼できる制作会社であるかどうかの評価基準となります。
企業の魅力を引き出す企画提案力があるか
サステナビリティサイトは、単なる情報開示の場ではなく、企業の魅力や独自の価値を伝えるブランディングツールでもあります。 企業の理念やビジョン、具体的な取り組みを深く理解し、それをステークホルダーに響くストーリーとして企画・提案できる力があるかを確認しましょう。 画一的なテンプレートではなく、企業ごとの「らしさ」を表現し、共感を呼ぶサイトを構築できるかが重要な評価点です。
デザイン性と情報伝達のバランス感覚に優れているか
サステナビリティサイトは、多くの情報を正確かつ分かりやすく伝える必要がありますが、同時に視覚的な魅力も重要です。 情報量が多くなりがちなサステナビリティコンテンツにおいて、複雑な情報を整理し、ユーザーが直感的に理解できるよう、デザインと情報伝達のバランスに優れた制作会社を選びましょう。 単に見栄えの良いデザインだけでなく、情報の優先順位付けや視覚的な誘導が適切に行われているかの設計力を評価することが大切です。
サステナビリティサイト制作にかかる費用と期間の目安
サステナビリティサイトの制作にかかる費用と期間は、サイトの規模や機能、コンテンツの量、デザインの複雑さなどによって大きく変動します。 ※ここではコンサルティングなどの費用は含まれていません。
シンプルな1ページ構成であれば、費用は100万円から、制作期間は最短1ヶ月半程度が目安となります。 多様なコンテンツや複雑な機能を盛り込む場合は、費用も期間も大幅に増加する可能性があります。 例えば、トップメッセージ、基本方針、具体的な取り組み、レポート、活動記録といった要素を網羅し、多言語対応やインタラクティブなコンテンツ、オリジナルデザインなどを加える場合、数百万円から数千万円の費用と、数ヶ月から半年以上の期間を要することも珍しくありません。
費用と期間については、事前に制作会社と詳細な要件定義を行い、明確な見積もりとスケジュールを確認することが重要です。 費用について、要件定義から概算作成など対応させていただきますので、ぜひ一度お問合せください。
よくある質問
Q. どの情報をサイトに掲載すべきですか?
サステナビリティサイトに掲載すべき情報は多岐にわたりますが、主要な要素としては、トップメッセージ、サステナビリティ基本方針と重点課題(マテリアリティ)、具体的な取り組み、レポート(数値データなど)・資料、そして活動記録(継続的な更新)が挙げられます。 これらの情報を網羅することで、企業のサステナビリティ経営に対する真摯な姿勢と具体的な成果をステークホルダーに伝えることができます。 また、事業を通じた環境・社会価値の創出と経営の持続可能性という2つの要素を理解できる情報を含めることが必須とされています。
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
Q. 統合報告書(年次レポート)とどう違うのですか?
統合報告書とサステナビリティサイトは、企業の情報開示ツールとして共通点も多いですが、目的と内容に違いがあります。 統合報告書は、財務情報と非財務情報を統合し、企業の長期的な価値創造プロセスや戦略を説明する年次レポートであり、主に投資家を主な対象としています。 一方、サステナビリティサイトは、企業のサステナビリティへの取り組みや社会貢献活動に特化した非財務情報を中心に、より広範なステークホルダー(顧客、従業員、求職者、地域社会など)に向けて発信するWebサイトです。サステナビリティサイトは、統合報告書で伝えきれない詳細な情報や、最新の活動状況をタイムリーに発信できるという点で補完的な役割を果たします。
Q. データはどのくらいの頻度で更新すべきですか?
サステナビリティサイトのデータ更新頻度は、企業の信頼性を保つ上で非常に重要です。活動記録は企業がサステナビリティに対する取り組みを継続的に行っていることを示すため、定期的な更新が推奨されます。 特に、具体的な取り組みの進捗状況や数値目標に対する達成度、新たな活動などは、常に最新の情報を掲載することが望ましいです。年次の報告書(統合報告書やサステナビリティレポート)の公開に合わせて、サイトの関連情報も更新するとともに、それ以外の期間でも、新しいニュースやイベント、受賞歴などがあれば随時追加していくことで、サイトの鮮度と情報価値を高めることができます。
Q. 多言語対応は必要ですか?
企業の事業展開がグローバルである場合や、多様な国籍のステークホルダーに情報を届けたい場合は、サステナビリティサイトの多言語対応は強く推奨されます。 特に、外国人旅行者はサステナブルな旅行への需要が高く、施設のSDGs対応に関心があるという調査結果もあります。Webサイトの多言語化は、企業のメッセージをより多くの人々に正確に伝え、国際的な信頼性を高める上で不可欠な要素です。 英語を始めとする主要言語への対応は、グローバルなコミュニケーションを円滑にし、幅広いステークホルダーとの関係構築に寄与します。
デパートのオフィシャルサイトには、自動翻訳ツールの「shutto翻訳」を導入しています。 サイト左下にある、言語切り替えのUIボタンからぜひ試してみてください。 「shutto翻訳」の詳細を知りたい方は、こちらからご相談ください。
Q. 外部評価(ESG格付けなど)は掲載したほうがいいですか?
外部評価(ESG格付けなど)は、サステナビリティサイトに掲載することを強く推奨します。これらの評価は、企業のサステナビリティへの取り組みが客観的に評価されていることを示し、特に投資家からの信頼性を高める上で非常に有効です。 例えば、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会が発表する「サステナビリティサイト・アワード」や、ゴメス・コンサルティングの「GomezESGサイトランキング」といった格付け結果は、企業のサステナビリティ情報開示の充実度を示す指標となります。 これらの情報を掲載することで、企業は透明性をアピールし、ステークホルダーからの評価向上に繋げられます。
まとめ
サステナビリティサイトは、単なる企業のWebサイトの一部ではなく、企業の持続可能性への取り組みや社会貢献活動を総合的に伝え、ステークホルダーとの信頼関係を築くための重要な情報発信拠点です。企業のブランドイメージ向上、優秀な人材の獲得、従業員エンゲージメントの強化、そして投資家からの資金調達といった多岐にわたるメリットをもたらします。 制作においては、社内での準備、実現可能で継続的な取り組みの掲載、平易な言葉遣い、事実に基づいた表現が成功の鍵となります。 また、サステナビリティに関する専門知識と実績、企画提案力、デザインと情報伝達のバランスに優れた制作会社を選ぶことが重要です。費用と期間は内容によって変動しますが、多言語対応や外部評価の掲載も視野に入れることで、より効果的なサイト構築が期待できます。
これらのポイントを踏まえ、貴社に最適なサステナビリティサイトを制作し、企業価値の向上を目指しましょう。デパートではサステナビリティサイトの制作支援を行なっております。専門チームがサステナビリティサイト構築/改修のトータルプランを提案いたします。
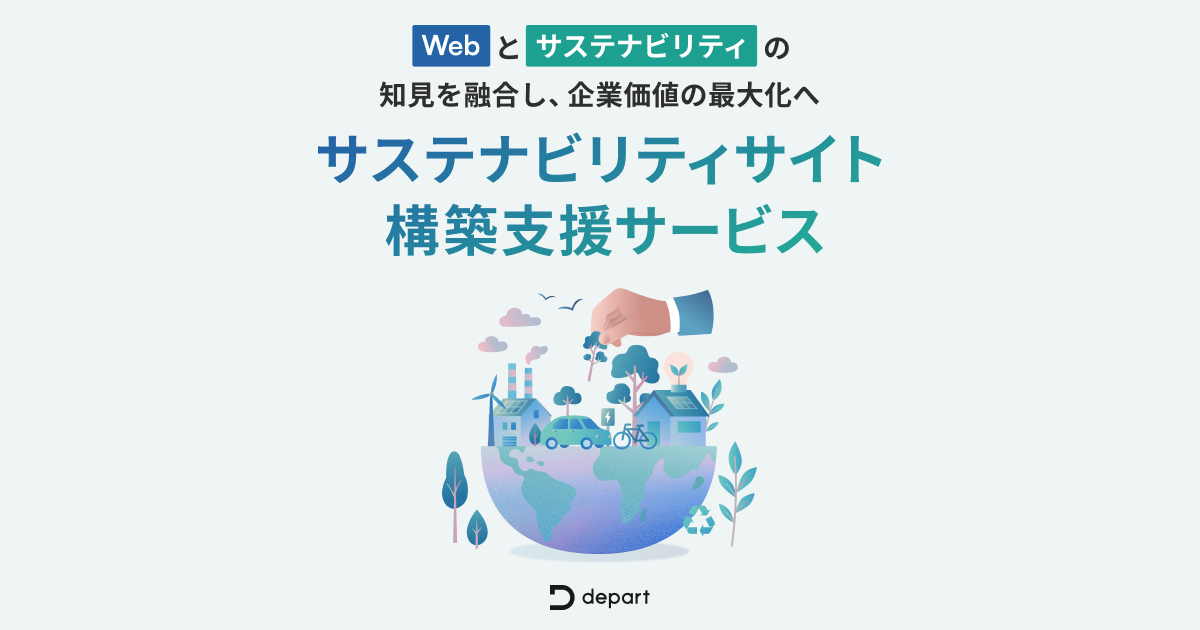
株式会社デパートで提供するサステナビリティサイト構築支援サービスでは、 Web制作とサステナビリティの知見を融合し、貴社のサステナビリティサイト構築に関連する、 戦略立案からサイト構築、そして継続的な運用・改善まで、全てお任せいただけます。

サスティナビリティサイトに関するご相談、 抱えられている課題など、お気軽にご相談ください。
Contact
制作のご依頼やサービスに関するお問い合わせ、
まだ案件化していないご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
- この記事をシェア