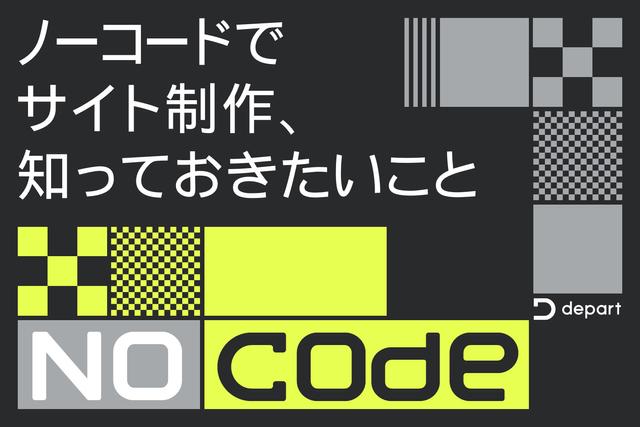- Share On
目次
目次
- APIとは?
- APIの基本イメージ
- なぜAPIが使われているのか?
- APIが支えるサービス連携のイメージ
- APIの仕組みを図解で理解する
- APIの通信イメージ
- APIの種類
- APIの設計スタイル(REST・GraphQL・SOAP)
- REST API
- GraphQL
- SOAP
- 実際に使われているAPIの例
- APIを導入・活用するときのチェックポイント
- 目的と利用範囲を明確にする
- 認証とアクセス制限の設計
- エラーとトラブル対応の仕組みを用意する
- ドキュメント整備と利用者サポート
- 知っておくと役立つポイント
- 1. 仕様変更は影響を確認する
- 2. ドキュメントは常に最新に保つ
- 3. テスト環境を分ける
- 4. エラー対応を仕組みにする
- 5. 外部APIの更新情報を追う
- 6. セキュリティ管理を徹底する
- 7. 稼働状況を定期的に確認する
- よくあるQ&A
- まとめ
Web制作やアプリ開発の打ち合わせでよく出てくる「API(エーピーアイ)」という言葉。 主にWebAPIを指していますが、APIとは「サービス同士をつなぐ決まりごと」のような存在。 私たちが日々使っている多くのWebサービスは、裏側でAPIによって連携しています。
この記事では、APIの仕組みと、APIについてのポイントなどを図解しながら解説していきますので、APIを理解する一助になれば幸いです。
APIとは?

APIとは “Application Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)” の略です。 要するに「アプリ同士がやりとりするための共通ルール」のことです。
たとえば、天気アプリが気象庁のデータを取得したり、地図アプリが店舗情報を表示したりする。 こうした裏側のやりとりをAPI経由で行っています。
APIは「サービス同士の翻訳係」
→ 違う言語(システム)、違うソフトウェアでも共通ルールで会話できる
決まりごとを守れば安全に連携できる
→ どんなデータを渡し、どんな形式で返すかを明示
仕組みを変えても影響を減らせる
→ 契約部分(API)が安定していれば、内部が変わっても問題なし
APIの基本イメージ

つまり、APIは「どんな質問をしたらどんな答えが返ってくるか」を決める窓口のようなものです。
なぜAPIが使われているのか?
現代のWebサービスは、すべてを自分で作るよりも、他社や他システムの機能をAPIを通して活用しています。
「地図を出したい」「ログイン機能を使いたい」「決済をしたい」など、目的に合わせて必要な部分を借りることで、自分たちで機能を構築・管理するよりも簡単に、多くのメリットをWebサイトへ付与することができます。
コストを抑えられる:すでにある機能を使える
スピードが上がる:ゼロから開発しなくていい
信頼性が高い:大手の安定した仕組みを利用できる
拡張性がある:別サービスと柔軟に連携できる
APIが支えるサービス連携のイメージ

このように、ひとつのWebサイトの裏側では、複数のAPIが同時に動いています。 そのおかげで、ユーザーは1つの画面で完結できる便利な体験を得られるのです。
APIの仕組みを図解で理解する
APIの基本的な流れは「リクエスト」と「レスポンス」です。 これは“質問して答えが返ってくる”やりとりのようなものです。
APIの通信イメージ

端末からリクエストを送る(質問する)
→ 「この情報をください」「これを登録してください」などの要求を送る。
WebサーバーからAPIと通信
→端末から受け取った要求を元にAPIへリクエストをする。
APIサーバーが情報を処理する
→ APIが受け取った内容をもとに内部で処理。
レスポンスを返す(答えが返ってくる)
→ 結果をJSONなどの形式で返す。
JSON(ジェイソン)は、よく使われるデータ形式で、「どの項目にどんな値が入っているか」がわかりやすく整理されています。
例:
{
"weather": "晴れ",
"temperature": 24
}APIの種類
APIにはいくつかの種類があります。 使われる目的や範囲によって、呼び方や公開レベルが異なります。
内部API(Internal API)
社内のシステム同士で利用。外部には非公開。
パートナーAPI(Partner API)
取引先や協力会社など限定された相手に提供。
公開API(Public API)
外部の開発者にも使えるように公開されたもの。
例:Google Maps API、Twitter APIなど。
内部で使うだけのAPIもあれば、他社に“サービスとして提供”するAPIもあります。 たとえば、地図や翻訳などは公開APIとして多くの企業が利用しています。
APIの設計スタイル(REST・GraphQL・SOAP)
APIの作り方にも“流儀”のようなものがあります。 代表的なのが「REST API」と「GraphQL API」です。
横にスクロールできます
スタイル | 特徴 | 向いている用途 |
|---|---|---|
REST | Webで最も一般的。GET・POSTなどのHTTPメソッドで操作する。 | シンプルなデータ取得・更新 |
GraphQL | 必要なデータだけを指定して取得できる。通信量が少なく効率的。 | モバイルアプリなど、データ通信を減らしたい場合 |
SOAP | XML形式でやり取りする古い方式。厳格なルールが特徴。 | 金融・官公庁など高い信頼性が必要な場面 |
REST API

REST(Representational State Transfer)は、もっとも広く使われている設計スタイルです。
「GET」「POST」「PUT」「DELETE」といったHTTPメソッドを使い、データの取得・登録・更新・削除といった操作を行います。 URL構造がわかりやすく、Webやモバイルアプリの開発で標準的に採用されています。 ブラウザからも動作を確認しやすく、扱いやすさと汎用性の高さが特徴です。
ポイント
シンプルで理解しやすい構造
幅広い言語・環境で対応可能
大規模サービスでも安定して運用できる
GraphQL

GraphQLは、Facebookが開発した比較的新しいAPI設計の考え方です。 一度のリクエストで、必要なデータだけをまとめて取得できます。
RESTのように「複数のエンドポイントを順番に呼ぶ」必要がなく、クライアント側(アプリなど)が欲しい情報を柔軟に指定できます。 通信量を減らせるため、モバイルアプリや回線が不安定な環境に向いています。
ポイント
必要な項目だけ取得できる(過不足がない)
通信回数が減り、動作が軽い
クライアント側での制御がしやすい
SOAP

SOAP(Simple Object Access Protocol)は、XML形式でやり取りする方式です。
昔からある手法で、金融・医療・行政など、高い信頼性や厳格な仕様を求められるシステムに使われています。 セキュリティやトランザクションの取り扱いが細かく定義されており、RESTやGraphQLよりも堅牢ですが、その分だけ開発や保守の負担が大きくなります。
ポイント
XML形式で厳密に構造化された通信
企業システムなど、信頼性が最優先の場面に向く
柔軟性よりも“確実に動く”ことを重視
実際に使われているAPIの例
APIは身の回りの多くのサービスに組み込まれています。
ここではよくある利用シーンをいくつか紹介します。
地図を表示する機能
→ Google Maps APIを使って地図を埋め込み。
SNSログイン
→ GoogleアカウントやLINEアカウントでの認証API。
天気情報を表示
→ 気象データ提供サービスのAPIを利用。
ECサイトの配送状況確認
→ 宅配会社のAPIで追跡番号から状況を取得。
AI翻訳機能
→ DeepL APIやGoogle翻訳APIで文章を自動翻訳。
こうして見ると、私たちが日常的に触れている多くのサービスが、APIによって支えられていることがわかります。
APIを導入・活用するときのチェックポイント

APIは便利ですが、設計や運用の段階で注意しておきたい点もあります。 導入前の確認として、以下の観点を押さえておくと安全です。
目的が明確か(どんなデータ・機能をやり取りしたいのか)
利用範囲を整理しているか(社内限定・外部提供など)
認証やアクセス制限を設けているか
エラー時の対応方法を決めているか
ドキュメント(使い方説明)が整っているか
バージョン管理ができているか(古いAPIを残すか)
APIは一度作って終わりではなく、「安定して提供し続けること」も大切です。
それぞれの観点を少し詳しく見ていきましょう。
目的と利用範囲を明確にする
APIを導入する際、最初に整理したいのが「なぜ作るのか」「誰が使うのか」という部分です。 ここを決めておかないと、後から機能が増えすぎたり、想定外の使われ方をしてしまうことがあります。
たとえばECサイトの場合、「在庫・注文管理API」は社内用、「商品検索API」は外部公開用、といったように目的によって使い分けます。
最初に目的と範囲を明確にしておくことで、セキュリティや設計方針のブレを防げます。
認証とアクセス制限の設計
APIはインターネット上の“入り口”です。 誰でも使える状態のままだと、不正アクセスや過剰なリクエストの原因になることがあります。
安全に運用するために、認証とアクセス制御の仕組みをあらかじめ整えておきましょう。
APIキーやトークンを発行し、利用者を特定する
利用回数制限(レートリミット)を設定してサーバー負荷を防ぐ
IPアドレスやドメイン単位でアクセスを制限する
通信にはHTTPSを使用し、データを暗号化する
SNSログインなどに使われる「OAuth認証」も、APIの代表的な認証方式です。 特に外部公開する場合は、アクセス制限の仕組みを早い段階から設計しておくことが重要です。
エラーとトラブル対応の仕組みを用意する
APIはネットワークや外部サービスに依存するため、予期しないエラーが起こることもあります。 そうしたトラブル時に、どのような対応を行うかを設計段階で決めておくと安心です。
エラーコードとメッセージを明確に返す(例:404, 500など)
障害発生時の通知方法を決める(開発者向けステータスページやメール)
メンテナンスや更新時に、利用者へ告知できる仕組みを用意する
APIを提供する側にとって、エラー時の対応ルールは信頼性を支える要素です。 「どう落ちるか」まで含めて設計しておくと、サービス全体の安定感が高まります。
ドキュメント整備と利用者サポート
どんなに便利なAPIでも、仕様が不明瞭だと使ってもらえません。 そのため、開発者や社内担当者が迷わず利用できるよう、ドキュメントを整備しておきましょう。
エンドポイントの一覧と概要
利用可能なパラメータや型の説明
リクエスト・レスポンスのサンプル(JSONなど)
制限事項や更新履歴の記載
社内利用であっても、NotionやConfluenceなどにまとめておくと便利です。 外部向けの場合は「開発者向けポータルサイト」を用意する企業も増えています。
知っておくと役立つポイント
APIを使う・運用する際は、細かな実装よりも「どう管理し、どう安定させるか」が重要です。
主なポイントを7つにまとめました。
1. 仕様変更は影響を確認する
APIは他の仕組みとつながっているため、変更が思わぬ不具合を生むことがあります。 更新前に影響範囲を洗い出し、テストを行うことが大切です。
2. ドキュメントは常に最新に保つ
仕様や利用ルールは変更のたびに更新します。 古い情報のまま放置すると、APIが正しく使われなくなります。
3. テスト環境を分ける
本番用と同じAPIを直接操作すると事故につながります。 開発・検証・本番を分けて運用しましょう。
4. エラー対応を仕組みにする
エラーコードやログを確認し、原因をすぐ特定できる状態を保ちます。 発生を防ぐより、「早く気づいて直す」ことが安定運用の鍵です。
5. 外部APIの更新情報を追う
外部サービスのAPIは定期的に仕様が変わります。 提供元のドキュメントやお知らせを定期的にチェックしましょう。
6. セキュリティ管理を徹底する
APIキーやトークンは機密情報です。 共有ドキュメントに記載せず、不要になったキーはすぐ削除します。
7. 稼働状況を定期的に確認する
APIの応答速度やエラー率を定期的に確認します。 異常を早期に検知できる体制を整えておくと安心です。
APIを安定して使うためには、「設計・更新・監視」を小まめに行うことが最も効果的です。 作って終わりではなく、動かし続ける仕組みを意識しておくと、長く安全に運用できます。
よくあるQ&A
Q:APIを使うとセキュリティが心配です。
→ 認証・暗号化・アクセス制限などで安全に運用できます。
外部提供APIには「APIキー」が必ずあり、誰でも自由に使えるわけではありません。
Q:自分のサイトにもAPIを組み込めますか?
→ もちろん可能です。Google Mapsなどの公開APIは誰でも利用できます。
制作会社に依頼する場合は「API連携を前提に設計してほしい」と伝えるとスムーズです。
Q:プログラミング言語によってAPIの使い方は変わりますか?
→ 多少の書き方は違いますが、仕組みは同じです。
TypeScriptでもPythonでも「リクエストを送って、レスポンスを受け取る」流れです。
Q:APIを公開するにはどうすればいい?
→ サーバー側で仕様を決め、ドキュメントを整備します。
社内・外部問わず、使う人が理解できる設計が重要です。
まとめ
APIとは、「サービス同士が共通ルールでやり取りするための仕組み」という一言に尽きます。
最近では、AIやIoT(モノのインターネット)にもAPIが必要不可欠で、ChatGPTや翻訳、画像生成などAPIを通じて利用されているケースが多いです。
APIの基本を理解しておくと、制作・運用・改善の会話で「どこがつながっているのか」「何ができるのか」をスムーズに判断できます。
株式会社デパートでは、APIを含むシステム開発に関して一貫して対応可能です。 安全で効率的なAPI開発や、それを利用したモダン開発なども承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
Contact
制作のご依頼やサービスに関するお問い合わせ、
まだ案件化していないご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
- この記事をシェア