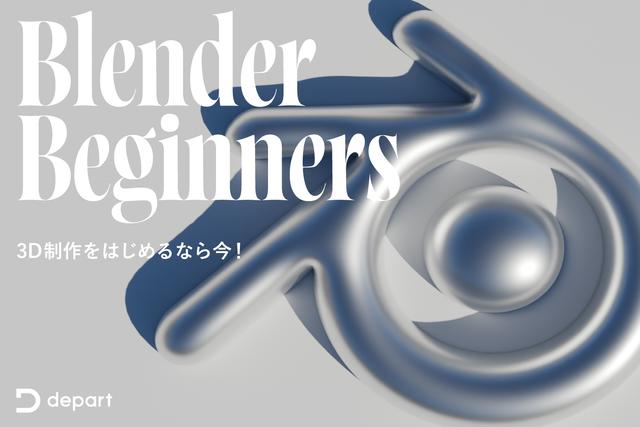- Share On
目次
目次
- サステナビリティサイトとは?
- CSRサイトとの違い
- なぜ今、サステナビリティサイトが重要視されるのか?
- サステナビリティを巡る社会の動向
- 企業価値を測る指標としてのESG情報
- 多様なステークホルダーとのコミュニケーション
- サステナビリティサイトで伝えるべき内容
- ターゲットとなるステークホルダーを明確にする
- 投資家・株主
- 顧客・取引先
- 地域社会・NPO/NGO
- 従業員・求職者
- 価値創造ストーリーと具体的な取り組み
- サステナビリティサイト・アワード2025の概要
- 調査期間
- 調査項目
- 調査対象
- 評価方法
- 表彰企業
- 表彰企業一覧(順不同)
- 評価されるサステナビリティサイトに必要なこと―ASC調査講評から考える
- 経営戦略とサステナビリティの関連性が明確
- 継続的な改善と第三者からのフィードバックの活用
- 次世代を見据えた情報設計
- 貴社のサステナビリティサイトは、時代の変化に「アジャスト」できていますか。
現代の企業経営において、サステナビリティへの取り組みは単なる社会貢献活動ではなく、事業成長と企業価値向上に不可欠な要素となっています。それに伴い、企業のサステナビリティに関する考え方や活動を統合的に発信する「サステナビリティサイト」の役割は、ますます重要性を増しています。
本記事では、サステナビリティサイトの重要性から、国内で権威ある「サステナビリティサイト・アワード2025」の情報をもとに表彰企業の紹介と、評価されるサイトに共通する要素まで、最新の動向を踏まえながら解説します。
サステナビリティサイトとは?
サステナビリティサイトとは、企業が持続可能な社会の実現に向けてどのような方針を掲げ、環境・社会・ガバナンス(ESG)の各側面で具体的にどのような活動を行っているかを、株主や投資家、顧客、従業員といった多様なステークホルダーに向けて総合的に情報発信する専門のWebサイトです。
企業の経営戦略とサステナビリティの統合を明確に示し、事業を通じた社会課題解決への貢献と、それに伴う経済的価値の創造という「価値創造ストーリー」を伝える役割を担うこともあります。
単なる情報開示の場に留まらず、ステークホルダーとのコミュニケーションを促進し、企業価値を高めるための戦略的ツールとして位置づけられています。

CSRサイトとの違い
CSR(企業の社会的責任)は、寄付・ボランティアといった本業とは別の社会貢献活動や法令遵守などの「守り」の活動に主眼が置かれる傾向にありましたが、サステナビリティは、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の3つの側面から、事業活動そのものを通じて社会課題を解決し、長期的な企業価値向上を目指す経営のあり方を示します。
そのため、サイトで発信する情報も、経営戦略と不可分な重要課題(マテリアリティ)への取り組み、サプライチェーン全体での人権や環境への配慮、気候変動が事業に与えるリスクと機会など、事業の根幹に関わる内容が中心となります。
CSRが企業の「責任」を果たす側面に光を当てるのに対し、サステナビリティは事業による「価値創造」の側面を強調する点が大きな違いです。
なぜ今、サステナビリティサイトが重要視されるのか?
気候変動や人権問題など地球規模の課題が深刻化する中、企業の社会的役割に対する期待はかつてなく高まっています。
投資の世界ではESG投資が急速に広まり、企業の非財務情報が投資判断を大きく左右するようになりました。 ESGは、もはや無視できない重要な投資テーマです。
また、消費者や求職者も、企業のサステナビリティへの姿勢を製品選択や就職先決定の重要な基準と捉えています。
このような環境変化の中で、サステナビリティサイトは、多様なステークホルダーからの要請に応え、信頼関係を構築し、自社の企業価値を的確に伝えるための不可欠なコミュニケーション基盤として重要視されているのです。
サステナビリティを巡る社会の動向
国際社会では、SDGs(持続可能な開発目標)やパリ協定といった共通の目標が掲げられ、企業にもその達成に向けた行動が強く求められています。これに伴い、各国で情報開示に関するルール作りも進んでいます。
例えば、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言は気候変動関連の情報開示のグローバルスタンダードとなり、多くの企業がこれに沿った情報開示を始めています。
さらに、サプライチェーンにおける人権侵害を防ぐための人権デューデリジェンスの法制化が欧州を中心に進むなど、企業が取り組むべき課題は具体的かつ広範になっています。
こうした社会の動向は、企業がサステナビリティへの取り組みを加速させ、その過程と成果を透明性高く開示する必要性を高めています。
企業価値を測る指標としてのESG情報
現代の資本市場では、財務情報だけでは企業の真の価値を測れないという認識が広まっています。 気候変動による物理的リスクや社会からの評判リスクなど、従来は評価が難しかった非財務的な要因が、企業の長期的な収益性や持続可能性を大きく左右するためです。
そこで、企業の環境、社会、ガバナンスへの取り組みを評価するESG情報が、新たな企業価値評価の指標として定着しました。 世界中の機関投資家がESG投資の残高を急速に拡大しており、投資先を選定する際に企業のESGデータを厳しく審査します。
そのため、企業にとってサステナビリティサイトは、自社のESGへの取り組みを網羅的かつ具体的に開示し、資本市場からの適正な評価を獲得するための重要なプラットフォームとなっています。
多様なステークホルダーとのコミュニケーション
サステナビリティサイトは、投資家だけでなく、企業を取り巻くあらゆるステークホルダーとの対話の基盤となります。 顧客は、製品やサービスが環境や人権に配慮して作られているかを重視するようになりつつあり、今後はさらに多くの消費者が企業の倫理的な姿勢を購買判断に反映させるようになるでしょう。 従業員や求職者にとっても、企業のパーパスや社会貢献への取り組みは、エンゲージメントやロイヤリティを高め、働く企業を選ぶ際の重要な動機付けとなります。 また、地域社会やNPO/NGOといった市民社会からの信頼を得るためにも、事業活動が環境や地域に与える影響について誠実に情報を開示し、対話する姿勢が不可欠です。 サステナビリティサイトは、これら多様なステークホルダーの関心に応え、エンゲージメントを深めるためのハブとして機能します。
デパートではサステナビリティサイトの制作支援を行なっております。専門チームがサステナビリティサイト構築/改修のトータルプランを提案いたします。ぜひお問い合わせください。
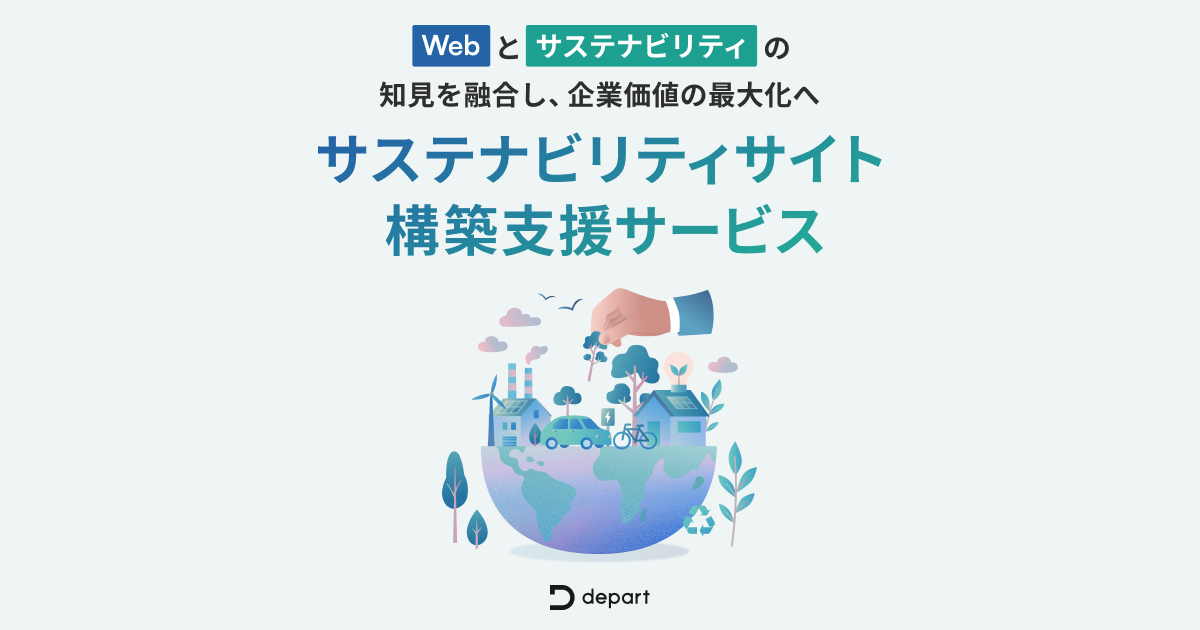
株式会社デパートで提供するサステナビリティサイト構築支援サービスでは、 Web制作とサステナビリティの知見を融合し、貴社のサステナビリティサイト構築に関連する、 戦略立案からサイト構築、そして継続的な運用・改善まで、全てお任せいただけます。
サステナビリティサイトで伝えるべき内容
効果的なサステナビリティサイトを構築するには、まず誰に(ターゲット)、何を(コンテンツ)、どのように(構成)伝えるかを戦略的に設計することが重要です。
企業のサステナビリティに関する情報は多岐にわたるため、すべての情報を無秩序に掲載するだけでは、伝えたいメッセージが埋もれてしまいます。
ターゲットとなるステークホルダーの関心事を的確に捉え、それに応える形で、自社の理念から具体的な活動、そして成果に至るまでの一貫したストーリーを分かりやすく示す構成が求められます。

ターゲットとなるステークホルダーを明確にする
企業のサステナビリティに関する情報ニーズは、ステークホルダーの立場によって大きく異なります。 そのため、それぞれの関心や期待に合わせた情報を提供することが、効果的なコミュニケーションには不可欠です。
投資家・株主
投資家や株主は、企業の長期的な企業価値とリスク管理体制を評価するため、客観的で比較可能なデータを重視します。
特に、TCFD提言に基づく気候変動シナリオ分析、マテリアリティ(重要課題)の特定プロセスとそれに対するKPI(重要業績評価指標)、取締役会によるサステナビリティ課題への監督体制といったガバナンスに関する情報への関心が高い傾向にあります。
また、GRIやSASBといった国際的な開示基準に準拠した詳細なESGデータや、財務情報以外のいわゆる非財務情報も、投資判断の精度を高める上で有益な情報と見なされます。
これらの情報を専門のセクションに集約し、データダウンロード機能を設けるなどの工夫が有効です。
顧客・取引先
顧客や消費者は、製品やサービスの背景にある企業の倫理観や環境への配慮を重視する傾向を強めています。
そのため、製品のライフサイクル全体におけるCO2排出量削減の取り組み、リサイクル素材の利用、児童労働や強制労働を排除した倫理的なサプライチェーンの構築といった情報が求められます。
一方、取引先(サプライヤー)に対しては、サステナビリティ調達方針を明示し、遵守を求めることが重要です。
自社の取り組みを開示することは、同じ価値観を持つ顧客や取引先からの支持を得て、ビジネス関係を強化することにも寄与します。
ストーリーテリングやインフォグラフィックを用いて、専門知識がない層にも分かりやすく伝える工夫が効果的です。
地域社会・NPO/NGO
企業が事業拠点を置く地域社会は、雇用創出や経済的貢献を期待する一方で、事業活動に伴う環境負荷や地域文化への影響を懸念しています。
工場からの排水や騒音に関する環境データ、地域住民との対話集会の実施報告、地域の清掃活動や文化支援といった具体的な貢献活動を開示することで、信頼関係を構築できます。
また、人権や環境問題に取り組むNPO/NGOは、企業の活動を専門的かつ批判的な視点から監視する重要なステークホルダーです。彼らからの指摘事項への対応状況や、協働プロジェクトの実績などを誠実に公開する姿勢は、企業の社会的責任に対する真摯な態度を示すことになります。
従業員・求職者
従業員は、自社が社会に対してどのような価値を提供しているのかを知ることで、仕事への誇りとエンゲージメントを高めます。
特にミレニアル世代やZ世代の求職者は、企業のパーパスやサステナビリティへの取り組みを就職先選びの重要な判断基準としています。
ダイバーシティ&インクルージョンの推進状況、従業員の健康と安全を守るための制度、スキルアップを支援する研修プログラム、公正な評価制度といった、働きがいに関する情報発信は極めて重要です。
社員インタビューや職場風景の動画などを通じて、具体的な取り組みと企業のカルチャーを伝えることで、人材の獲得競争において優位性を築くことができます。
価値創造ストーリーと具体的な取り組み
サステナビリティサイトで重要な要素の一つが、企業の存在意義(パーパス)を起点として、社会課題の解決と事業成長の両立を示す「価値創造ストーリー」です。この要素は統合報告書にも掲載されることが多く、サステナビリティサイトの構成要素として取り入れることで情報の一貫性が高まります。
このストーリーは、自社の事業がどの社会課題(マテリアリティ)の解決に貢献できるのかを明確にし、そのための長期ビジョンと具体的な戦略を示すことで構成されます。
ストーリーに説得力を持たせるためには、マテリアリティごとに具体的な目標(KPI)を設定し、その進捗状況をデータに基づいて定量的に報告することが不可欠です。
トップメッセージで経営陣のコミットメントを力強く表明し、各事業部門の具体的な活動事例を紹介することで、ストーリーはより立体的で信頼性の高いものとなります。
デパートではサステナビリティサイトの制作支援を行なっております。 専門チームがサステナビリティサイト構築/改修のトータルプランを提案いたします。ぜひお問い合わせください。
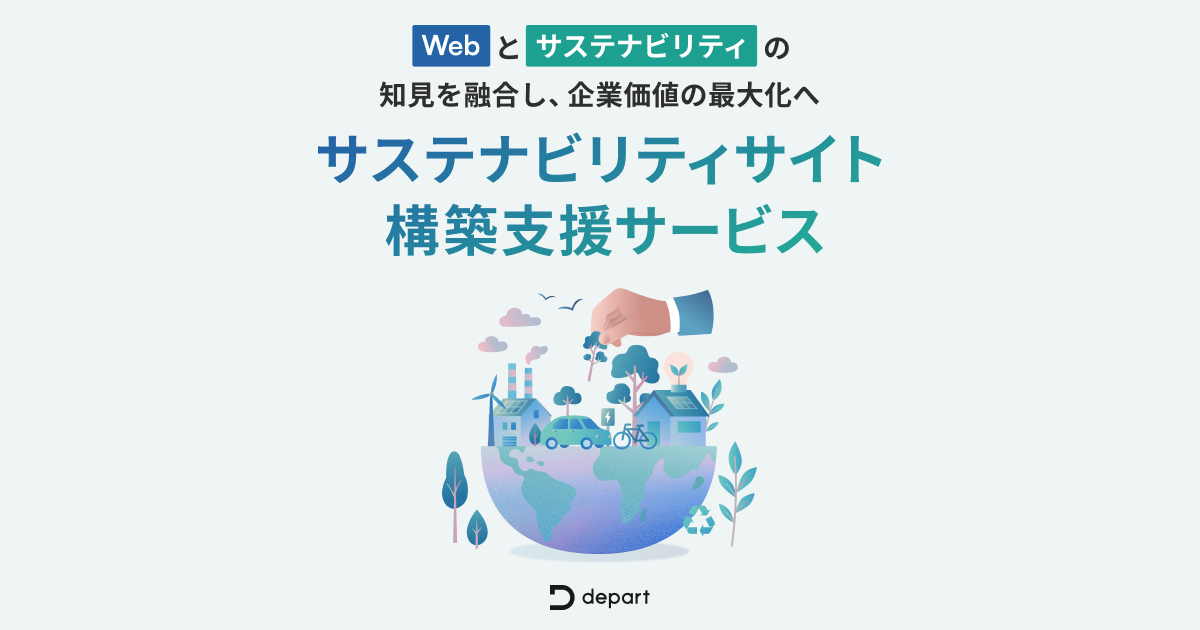
株式会社デパートで提供するサステナビリティサイト構築支援サービスでは、 Web制作とサステナビリティの知見を融合し、貴社のサステナビリティサイト構築に関連する、 戦略立案からサイト構築、そして継続的な運用・改善まで、全てお任せいただけます。
サステナビリティサイト・アワード2025の概要
サステナビリティサイト・アワードは、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会が(以降、ASCと略称します。)上場企業のサイト運営実態調査を目的として調査および格付けし毎年発表しています。
企業のサステナビリティ担当者にとっては、自社サイトの現在地を客観的に把握し、他社の優れた事例から改善に向けたヒントを得るための貴重なベンチマークとなります。
このアワードの結果は、企業のサステナビリティ情報開示のトレンドを反映しており、社会的な要請の変化を読み解く上でも有用な情報源です。
サステナビリティサイト・アワード2025の情報は、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会(ASC)の記事を引用しています。 https://sustainability.or.jp/sustainability_website_awards2025/
調査期間
「サステナビリティサイト・アワード2025」における評価対象サイトの調査は、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会により2024年7月1日から2024年12月28日までの期間に実施されました。(期間内で内容変更があった場合は更新前の状態で評価している場合あり)
調査項目
<全体項目>
横にスクロールできます
1. ガバナンス | サステナビリティ関連のリスクと機会を管理するプロセスおよび推進体制の開示がある |
|---|---|
2. 戦略 | サステナビリティ関連のリスクと機会が、組織の事業・戦略におよぼす影響についての開示がある |
3. リスク管理 | サステナビリティ関連リスクについて特定・評価・管理に関する開示がある |
4. 指標と目標 | サステナビリティ関連のリスクと機会を評価・管理するための指標・目標の開示がある |
5. タイムライン | 短・中・長期の時間軸ごとにおける、戦略・目標および活動・成果に関する開示がある |
6. インパクト | 経済的および社会的な活動・成果・変化に関する定量的な開示がある |
7. ストーリーライン | 「財務と非財務」など各情報のつながりが考慮され開示に一貫性がある |
8. オリジナリティ | 独自性があり自社の「強み」「らしさ」が表現できている |
9. アクセシビリティ | あらゆるステークホルダーに配慮されたWebデザインである |
<個別項目>
横にスクロールできます
1. パーパス | 理念体系および企業文化など組織理解のための情報が十分にある |
|---|---|
2. マネジメント | 推進体制、関連する各方針、中長期目標などが明確に開示されている |
3. マテリアリティ | マテリアリティ特定過程および項目・KGI/KPIに関する情報がある |
4. トップメッセージ | トップ(CEO)のコミットメントに関する情報が十分にある |
5. エンゲージメント | ステークホルダーが特定されそのエンゲージメントに関する情報がある |
6. 価値創造プロセス | 経済的および社会的な企業固有の価値創造に関する情報がある |
7. 環境 | 気候変動対応、生物多様性および環境領域全般に関する網羅的な情報およびデータがある |
8. 社会 | 人的資本、人権、品質管理および社会領域全般に関する網羅的な情報およびデータがある |
9. 組織統治 | コーポレートガバナンス全般に関する網羅的な情報およびデータがある |
調査対象
本調査の対象は、日本の全上場企業約4,072社です。各社のコーポレートサイト内に設けられている「サステナビリティ」「CSR」「ESG」「環境・社会への取り組み」といった名称の専門コンテンツ全体が評価範囲に含まれます。 Webページだけでなく、サイト上で公開されている統合報告書やサステナビリティレポート、各種データブックなどのPDFファイルに記載された情報も評価の対象となります。
このように、国内の主要企業を網羅し、多様な形式の開示情報を対象とすることで、調査の包括性と客観性が担保されており、日本企業全体のサステナビリティ情報開示のレベルを示す信頼性の高い指標となっています。
評価方法
評価方法は、サステナビリティ情報で開示すべきとされる独自設定した主要要素を軸に情報充実度評価を実施。ISSB等の国際開示ガイドラインで重視される枠組みである4つの開示構成要素「ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標」を包括的な評価要素とした。サイト/ページの特性とあるべき姿を考慮しダブルマテリアリティ視点を取り入れている。
調査対象企業へのヒアリングやアンケート調査はなく、専門知識を持つアナリストらが目視で全サイトの公開情報のみを調査し評価基準にそって評価。ユーザビリティ評価をするためにAI等のプログラムによる情報収集・評価は行なっていない。評価は絶対評価であり他社との定量比較による評価は行なっていない。
ホールディングス(連結会社等含む)が調査対象の場合はホールディングス自体のサイトを評価。関連会社等へのリンクや情報開示がある場合はそれらの情報を考慮。個別項目の定量的な比較分析はしていない。財務評価による加点・減点はしていない。 サイトはマルチステークホルダー向けのWebコンテンツの想定であるため、必ずしも投資家およびESG評価機関の目線では評価していない。なお、行政処分等を受けたもしくはステークホルダーへの影響力が大きい不祥事を起こしたと判断される企業は調査時に選考から除外している場合がある。
表彰企業
「サステナビリティサイト・アワード2025」では、総合評価に基づき、ゴールド(最優秀賞)、シルバー(優秀賞)、ブロンズ(優良賞)の各賞が授与されました。
これらの受賞企業は、経営戦略とサステナビリティを高度に統合し、多様なステークホルダーに対して網羅的かつ分かりやすい情報開示を実践しています。今年の表彰企業は以下の通りです。
表彰企業一覧(順不同)
横にスクロールできます
| 企業名 |
|---|---|
ゴールド(最優秀賞) | 日本電気、三菱地所、サントリーホールディングス |
シルバー(優秀賞) | KDDI、住友林業、旭化成、日産化学、日本電信電話、JFEホールディングス、三井金属工業、UACJ、ブラザー工業、三井不動産、TDK、日東電工、大日本印刷、東京エレクトロン |
ブロンズ(優良賞) | セイコーエプソン、参天製薬、ソフトバンク、大成建設、ニッスイ、レゾナック・ホールディングス、信越化学工業、日本触媒、住友ベークライト、UBE、DOWAホールディングス、サントリー食品インターナショナル、ブリヂストン、オリエンタルランド |
評価されるサステナビリティサイトに必要なこと―ASC調査講評から考える
アワードを受賞した企業のサイトは、いずれも単なる情報の羅列に終わらず、自社の事業活動と社会課題解決を結びつけた独自のストーリーを効果的に伝えています。
ステークホルダーが求める情報に容易にアクセスできるような設計上の工夫や、信頼性を高めるための客観的なデータ開示など、多くの企業にとって参考となる要素が随所に見られます。
これらの視点を制作プロセスに取り入れることで、単なる情報開示の場を超え、ステークホルダーからの評価を高め、企業価値向上に貢献する戦略的なコミュニケーションツールとしてのサイトを実現に繋がるのではないかと思います。
ここでは、サステナビリティサイトの評価を行う「ASCの調査講評」を元に、高い評価を得るために必要なポイントを考えてみました。
「ASC調査講評」の原文は以下よりご覧ください。
https://sustainability.or.jp/sustainability_website_awards2025/
経営戦略とサステナビリティの関連性が明確
サステナビリティサイトは、もはや単なるCSR活動の報告の場ではありません。事業を通じた社会課題の解決が、いかに企業の競争力強化や持続的な成長につながるかを明確に示すことが重要です。
ASCの講評では、「最近のサイトでは、統合報告書では目立っていた『事業を通じた社会課題解決』から『事業を通じた企業価値向上』という傾向が見られる」と指摘されています。これは、サステナビリティの取り組みを事業戦略と切り離すのではなく、事業の機会やリスクとして捉える必要があることを意味します。
また、講評では「サイトも『サステナビリティ関連開示』から『サステナビリティ関連“財務”開示”』を意識したコンテンツ構成に変化しつつある」とも述べられています。有価証券報告書などで開示される財務情報との整合性を確保することで、ステークホルダーからの信頼性が向上します。
継続的な改善と第三者からのフィードバックの活用
サイトの品質は一度の作成で決まるものではありません。継続的な改善と、外部からの客観的な視点を取り入れることが不可欠です。
ASCの講評にあるように、「変化の大きな時代の対策は『一年でも早く動き始める』のみです」。サイトの大きな更新は年に1回程度であるため、「試行錯誤の回数を増やすために1年でも早く動き出すしかない」のです。
また、「サイトにおいても積極的にフィードバックを受けましょう。フィードバックを受けずに品質を上げることはできません」と、フィードバックの重要性が強調されています。統合報告書などと同様に、自社従業員や専門家、制作会社からの第三者からの客観的な意見を取り入れることで、情報の分かりやすさや網羅性を高めることができます

次世代を見据えた情報設計
今後、サステナビリティ情報の利活用はさらに進化します。それに備えた情報設計も、評価されるサイトの重要な要素となります。
講評では、「ユーザビリティ/アクセシビリティの観点から、今後は『AIによる情報取得のしやすさ』も評価項目に加える」 と述べられています。これは、人間にとって使いやすいユーザビリティ・アクセシビリティに加え、機械(AI)も情報を効率的に読み取れるように設計することの重要性を示しています。
AIが企業サイトのデータを収集・分析する時代がすでに到来しているため、以下の点が求められます。
横にスクロールできます
ユーザビリティ | 誰もが情報を探しやすく、理解しやすいデザインになっているか。 |
|---|---|
アクセシビリティ | 障がいを持つ人々を含む、多様なユーザーがサイトを利用できるか。 |
機械(AI)による利用のしやすさ | AIが正確かつ効率的に情報を読み取れるよう、構造化されたデータや検索しやすいキーワード、適切なタグ付けなどがされているか。 |
評価されるサステナビリティサイトは、単に情報を羅列するのではなく、戦略的な意図を持って設計され、継続的な改善が行われ、未来の技術動向にも配慮していると言えるでしょう。
貴社のサステナビリティサイトは、時代の変化に「アジャスト」できていますか。
サステナビリティを巡る社会の要請や、投資家をはじめとするステークホルダーの期待は、常に変化し、その水準はますます高度化しています。 過去の成功体験や従来の開示フォーマットに固執することなく、常に最新の動向を捉え、自社の情報発信のあり方を柔軟に見直していく姿勢が不可欠です。
本記事で紹介したアワード受賞企業の先進的な事例やサイト改善のポイントを参考に、自社のサイトが時代の変化に対応できているかを定期的に点検し、継続的な改善を実践していくことが、持続的な企業価値の向上に繋がります。
株式会社デパートは、サスティナビリティサイト制作を通じて、お客様の企業価値向上を支援します。サステナビリティの専門知識とWeb制作技術を併せ持つ専門チームが、貴社の現状に合わせて最適なサイト構築をご提案します。 ぜひお気軽にお問い合わせください。
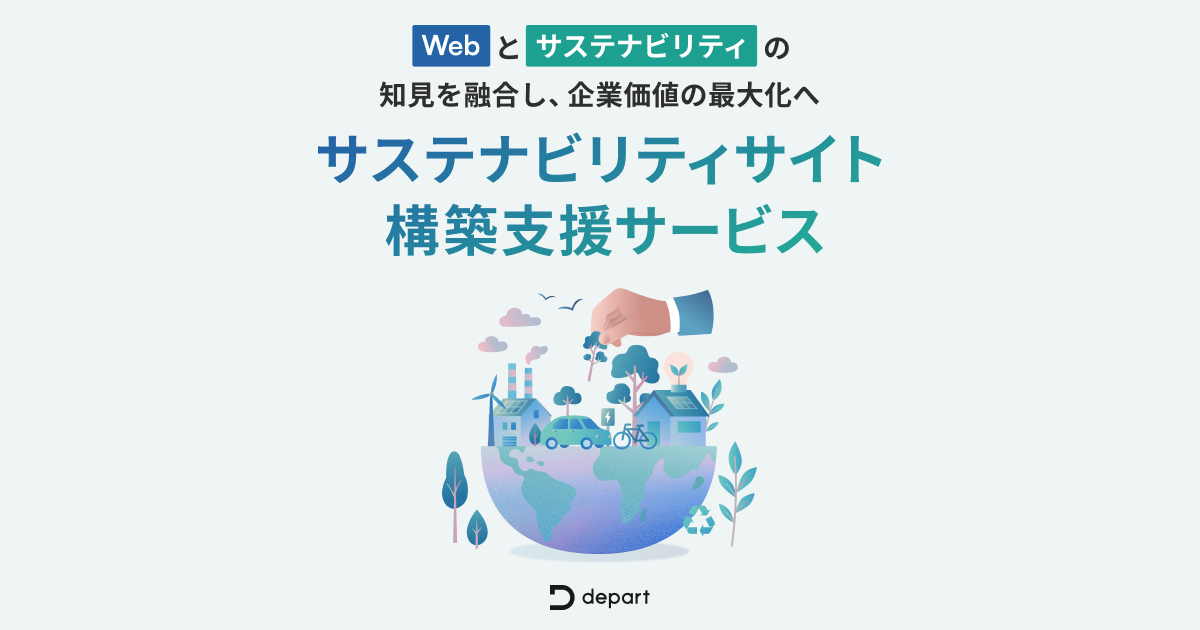
株式会社デパートで提供するサステナビリティサイト構築支援サービスでは、 Web制作とサステナビリティの知見を融合し、貴社のサステナビリティサイト構築に関連する、 戦略立案からサイト構築、そして継続的な運用・改善まで、全てお任せいただけます。

サスティナビリティサイトに関するご相談、 抱えられている課題など、お気軽にご相談ください。
Contact
制作のご依頼やサービスに関するお問い合わせ、
まだ案件化していないご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
- この記事をシェア