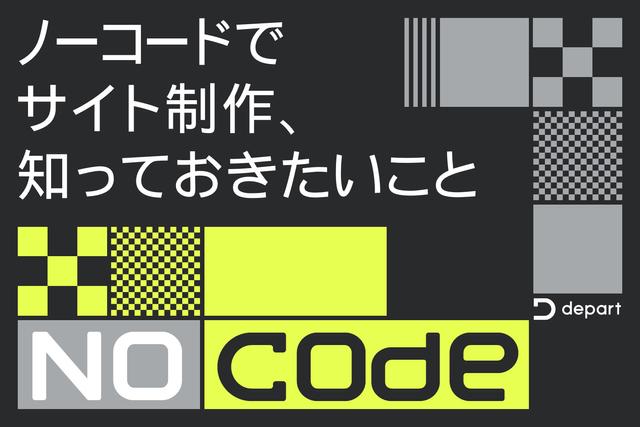- Share On
目次
目次
- サイト制作に使える補助金・助成金とは?
- ●Webサイト・ホームページ制作に使える補助金や助成金
- ●業務の効率化や売上向上のためのITツール導入支援
- 補助金と助成金の違い
- 2025年新たに登場【中小企業新事業進出補助金】
- 小規模事業者をサポートする【小規模事業者持続化補助金】
- イノベーションを促進する【ものづくり補助金】
- 製品・サービス高付加価値化枠
- グローバル枠
- 地方自治体による補助金・助成金の活用
- 例:東京都の補助金・助成金
- 例:様々な地域の補助金・助成金
- 中小企業を支援する【IT導入補助金】
- 通常枠
- 複数社連携IT導入枠
- インボイス枠(インボイス対応類型)
- インボイス枠(電子取引類型)
- セキュリティ対策推進枠
- Webサイト・ホームページ制作の補助金や助成金を申請する流れ
- 補助金を探す
- 申請に必要な書類を作成する
- 補助金を申請する
- 採択となったら、交付申請を行う
- 事業実施後の報告と補助金の支給
- Webサイト・ホームページ制作で補助金・助成金を活用する際の注意点
- 採択されない場合もある
- 申請書類は正確に揃える必要がある
- サイト制作だけでは補助金を申請できない
- 補助金は後払いで支給される
- リニューアルは補助対象外のケースが多い
- 不正利用が発覚した際の対応
- まとめ
現在、企業のデジタル化が進む中で、ホームページやWebサイトの制作が重要な戦略の一つとして捉えられています。しかし、制作費用が課題となり、実際に取り組むのが難しいと感じる場合もあるでしょう。そんな時に活用したいのが、国や地方自治体が提供している補助金や助成金です。このような制度を上手に利用することで、ホームページやWebサイト制作にかかる費用の一部を軽減することが可能です。
さらに、これらの助成金や補助金は単に経費の節約だけでなく、中小企業や個人事業主がデジタル化を進め、事業を拡大するための大きな助けとなるでしょう。今後の事業発展を考える上で、これらの補助金や助成金制度を理解し、適切に活用することでさまざまな可能性が広がります。この記事を通して、申請の可能性を検討し、企業の成長にお役立ていただけると幸いです。
サイト制作に使える補助金・助成金とは?

現在、企業のデジタル化が進んでいる中で、国や地方自治体が提供する補助金や助成金は、サイト制作の費用を軽減するための大変有用な手段となります。これらの制度を利用することで、ホームページやWebサイトの制作費をサポートし、企業が抱える様々な課題とされる企業ブランディング、採用活動や業務DXなど、デジタル戦略を図る手助けとなります。 その補助金や助成金の種類は様々です。少し詳しく見ていくことにしましょう。
今回、Webサイト・ホームページ制作に使える補助金や助成金を以下のようにピックアップしてみました。 活用する目的によって、申請すべき制度が様々ありますので、参考にしてみてください。
●Webサイト・ホームページ制作に使える補助金や助成金
2025年新たに登場【中小企業新事業進出補助金】
小規模事業者をサポートする【小規模事業者持続化補助金】
イノベーションを促進する【ものづくり補助金】
地方自治体による補助金・助成金の活用
●業務の効率化や売上向上のためのITツール導入支援
中小企業を支援する【IT導入補助金】
※本記事の内容は2025年4月時点のものです。最新情報は各種支援制度の公式サイトを参照してください。
補助金と助成金の違い
ちなみに、補助金と助成金の違いについても理解しておくことが必要です。 補助金は、主に政策目的を達成するために設けられた制度で、申請者の事業内容や成果に基づいて選定されます。支給には競争が伴い、応募者全員が必ずしも受け取れるわけではありません。そのため、対象となる事業計画や申請書の質が重要なポイントとなります。 一方で助成金は、特に雇用の促進や労働環境の改善といった特定の目的に基づいて支給され、申請要件を満たしている場合、高確率で受給を受けることができます。審査の基準は補助金に比べて比較的緩やかで、対象となる条件を満たせば申請者全員が受け取れるケースが多いのが特徴です。
このように、補助金と助成金には性質や対象となる目的に違いがありますが、どちらもサイト制作における費用面での負担軽減に役立つ貴重な制度です。それぞれの申請条件を事前にしっかり調査し、自社の状況に合致したものを積極的に活用することが成功への鍵となります。
2025年新たに登場【中小企業新事業進出補助金】
事業再構築補助金というコロナ渦に創設された補助金制度があります。新型コロナウイルスの影響を受けた事業者が新しい事業モデルに転換する際に活用できる支援制度として、補助額が高額な点が注目されていました。 しかし、コロナ禍も落ち着き以前の日常を取り戻す流れにある今、一時的な資金調達手段としての役割は終了し新たな補助金が新設されます。それが、中小企業新事業進出補助金です。 ※事業再構築補助金は2025年3月の第13回公募をもって新規申請は終了となりました。
中小企業新事業進出補助金は、中小企業や小規模事業者が新しい事業に挑戦したり、業態を転換したりする際に支援する制度です。制度の背景には、近年の物価高や人手不足など、厳しい経営環境の中で、中小企業の「稼ぐ力」を強化するために、政府は予算・税制・制度を活用した支援を行っています。その目的は、企業が利益を増やし、賃上げの原資を確保できるようにすることです。本制度を運営する「独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)」は、この補助金を 「中小企業が既存事業とは異なる分野へ挑戦し、新しい市場や高付加価値事業へ進出することを支援し、生産性向上と賃上げにつなげる事業」 と位置付けています。
Webサイトとしては、デジタル化が加速する中で、広告宣伝費としての活用が事業再構築の鍵となっています。Webサイトやホームページの制作は、顧客との接点を増やし、ビジネス拡大のためのオンライン販売チャンネル拡充に貢献します。また、Webサイトはブランド力の向上や新たな顧客層へのアプローチを実現する重要なツールとなり得ます。このように、補助金を活用してWebサイトを効果的に構築することで、企業は持続的な成長を目指すことができます。
●Webサイト・ホームページ制作に関連する支援例
※事業再構築補助金の事例
外国人対応にも注力したECサイトの構築によるインバウンドの獲得事業
特定技能の在留資格を持つ外国人に特化した求人サイトの運営事業
地域素材を使った新商品開発・製造及び、ECサイトで新市場へ進出
支援例はこちらから
●補助対象者
企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等
●補助対象
建物費、構築物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費
●補助率
1/2
●補助額
従業員数20人以下:2,500万円(3,000万円)
従業員数21~50人:4,000万円(5,000万円)
従業員数51~100人:5,500万円(7,000万円)
従業員数101人以上:7,000万円(9,000万円)
※補助下限750万円
※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。)
●申請スケジュール
現在調整中とのこと、最新スケジュールはこちらから
引用元: 中小企業新事業進出補助金 リーフレット
小規模事業者をサポートする【小規模事業者持続化補助金】
小規模事業者持続化補助金は、日本商工会議所が推進する制度であり、小規模事業者の経営を安定させ、持続的な発展を支援することを目的としています。この補助金を活用することで、販路の開拓や生産性の向上、業務の効率化につながり、経営基盤の強化を図ることが可能です。また、この制度は助成金として機能し、特に小規模事業者にとって必要な資金を確保するうえで重要な役割を果たします。適切な計画を立ててこの助成金を活用することで、事業の成長を後押しし、より安定した経営環境を実現することが期待できます。
実施回によっても、申請条件や内容が様々ですので、2025年公募の小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第17回公募を例にとってご紹介します。 より細かい条件は、こちらで確認ができます。
●Webサイト・ホームページ制作に関連する支援例
地元企業向けECサイト運営代行とそれに伴う動画撮影・制作内製化
新事業の販路拡大のためのWebサイトと広告制作
販路開拓のためのウェブサイト等のリブランディング事業
支援例はこちらから
●補助対象者
下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下
宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下
●補助対象
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費
●補助率
2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は 3/4)
●補助額
50万円
※上記金額に、インボイス特例対象事業者は50万円の上乗せ、賃金引上げ特例対象事業者は150万円の上乗せ、両特例対象事業者は200万円の上乗せ。
●申請スケジュール
横にスクロールできます
公募要領公開 | 申請受付開始 | 申請受付締切 | 事業支援計画書(様式4)の発行締切 |
|---|---|---|---|
2025年3月4日(火) | 2025年5月1日(木) | 2025年6月13日(金)17:00 | 2025年6月3日(火) |
最新スケジュールはこちらから
引用元: 暫定版 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第17回公募 公募要領
イノベーションを促進する【ものづくり補助金】
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が新製品・新サービスの開発や生産プロセスの改善を行う際に、その費用を支援するための制度です。この補助金の目的は、イノベーションを促進し、企業の競争力を高めることにあります。具体的な支援内容は、設備投資や技術導入、新たな製品開発にかかる費用の一部を補助する形で提供されるため、資金調達の面で大きな助けとなります。
●Webサイト・ホームページ制作に関連する支援例
●補助対象者
中小企業、小規模企業者、小規模事業者(個人事業主)、特定事業者、特定非営利活動法人、社会福祉法人
●申請スケジュール
横にスクロールできます
公募要領公開 | 申請開始日 | 申請締切日 |
|---|---|---|
2025年2月14日(金) | 2025年4月11日(金)17:00 | 2025年4月25日(金)17:00 |
最新スケジュールはこちらから
引用元: ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト 公募要領
ものづくり補助金には、以下の2つの申請枠が設定されています。
製品・サービス高付加価値化枠
グローバル枠
それぞれの枠について解説していきます。
製品・サービス高付加価値化枠
この申請枠は、中小企業や小規模事業者が新たな市場に進出し、製品やサービスの高付加価値化を図ることを目的としています。具体的には、革新的な製品やサービスの開発や、それを支えるための設備投資、システム構築などの経費を補助します。これにより、企業は新しい事業モデルを確立し、競争力を向上させることが期待されます。この制度を活用することで、企業は持続的な成長を狙う戦略を強化し、自社のビジネスを次のステージへと導くことができます。
●補助対象
機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
●補助率
中小企業1/2、小規模企業・小規模事業者及び再生事業者2/3
●補助額
従業員数5人以下:750万円
6~20人:1,000万円
21~50人:1,500万円
51人以上:2,500万円
※補助下限額 100万円
グローバル枠
グローバル枠は、国内企業が海外市場へ展開する際の支援を目的とした補助金制度です。 海外への直接投資に関する事業、海外市場開拓(輸出)に関する事業、インバウンド対応に関する事業、海外企業との共同で行う事業を、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援するものです。 この枠は、海外進出を目指す企業に対して、特に新しい製品やサービスの開発、国際的なマーケティング戦略、そして必要な体制の構築にかかる経費を補助します。補助対象となるのは、海外市場調査や現地パートナーとの連携、国際展示会への出展費用など多岐にわたります。この制度を活用することで、企業は新たなビジネスチャンスを創出し、競争力の向上を図ることができます。事業計画や申請内容が、国際的な視点を持ったものとして評価されるため、戦略的に内容を策定することが重要です。
●補助対象
機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 (グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費
●補助率
中小企業1/2、小規模企業・小規模事業者2/3
●補助額
3,000万円
※補助下限額 100万円
地方自治体による補助金・助成金の活用
国の補助金制度に加えて、地方自治体が独自に運営している補助金・助成金制度も存在します。 地方自治体の補助金制度は、国の補助金に比べて支給額が少なめではあるものの、サイト制作費だけでなく、周辺機器の購入やコンテンツのリニューアル費用までカバーできるものもあります。また、助成金として支給されるケースでは、申請条件を満たせば審査なしで受給できるため、補助金よりも利用のハードルが低いこともあります。 ただし、補助金・助成金制度を実施している自治体は限られており、支給額や要件は自治体ごとに異なります。そのため、最新の情報を各自治体のホームページで確認することが重要です。
ここから、自治体の補助金・助成金の例を一部ご紹介します。
例:東京都の補助金・助成金
東京都では、中小企業の支援を目的とした豊富な補助金制度が整備されています。特定の業界や分野に特化した助成金も用意されています。これらの補助金を利用することで、必要な経費を抑えながら、競争力のあるビジネスモデルを構築することが可能となります。
東京都【インバウンド対応力強化支援事業補助金】
引用元: https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/welcome-foreigner/
横にスクロールできます
補助対象者 |
|
|---|---|
補助対象 | インバウンド対応力強化のために新たに実施する事業
など |
補助金額 | 補助対象経費の2分の1以内 |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで【当日消印有効】 |
足立区【ホームページ作成・更新補助金】
横にスクロールできます
補助対象者 | 区内中小企業 |
|---|---|
補助対象 |
|
補助金額 |
※対象経費の2分の1を補助 |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日) |
中央区【ECサイト活用補助金】
引用元: https://www.city.chuo.lg.jp/a0016/shigoto/kigyoushien/hojokin/user_shoukan_time_20210301.html
横にスクロールできます
補助対象者 | 区内中小企業 |
|---|---|
補助対象 |
|
補助金額 | 補助対象経費の2分の1(限度額5万円) |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで |
中央区【中小企業のホームページ作成費用を補助します】
引用元: https://www.city.chuo.lg.jp/a0016/shigoto/kigyoushien/hojokin/shoukan.html
横にスクロールできます
補助対象者 | 区内中小企業・個人事業主 |
|---|---|
補助対象 |
|
補助金額 | 一般枠:対象経費の総額の2分の1(限度額30万円・千円未満の端数は切り捨て) |
申請期間 | 令和7年5月1日(木曜日)から令和8年1月30日(金曜日)必着 |
例:様々な地域の補助金・助成金
もちろん、東京以外でも様々な自治体で、サイト制作に関わる支援制度が用意されています。時期や目的によって、情報は日々変化していきますので、自社が所在する都道府県市区町村のサイトで情報を収集したり、窓口にて相談してみてください。
大阪府岸和田市【「がんばる岸和田」企業経営支援補助金】
引用元: https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/43-hanrokaitaku.html
横にスクロールできます
補助対象者 | 市内で創業を予定している、市内で創業後5年未満の事業者 |
|---|---|
補助対象 | 開業時広告宣伝費用
など |
補助金額 | 交付上限額:1事業者1年度につき、10万円 ※1事業者1回限り。 |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)必着 |
神奈川県海老名市【ホームページ制作・リニューアル事業】
引用元: https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/shoko/chusho/1003742.html
横にスクロールできます
補助対象者 | 市内で操業している中小企業者(個人事業主を含む。)及び中小企業者で構成する団体 |
|---|---|
補助対象 | ホームページの制作又はリニューアルを支援します。 |
補助金額 | ホームページの制作又はリニューアルの委託に要する費用2分の1(上限:15万円) |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から、先着順で受け付けします。 |
愛知県小牧市【中小企業ECサイト導入支援補助金】
引用元: https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/40668.html
横にスクロールできます
補助対象者 |
など |
|---|---|
補助対象 | 自社ECサイトの開設、及び改修に係る外部委託費用 |
補助金額 | 補助対象経費の1/2 |
申請期間 | 補助対象事業の完了した日から起算して30日以内又はその年度の3月31日までのいずれか早い日までに |
中小企業を支援する【IT導入補助金】
基本的に、Webサイトやホームページ作成に関連する費用は、IT導入補助金の補助対象外です。企業情報を掲載するホームページはこれに該当しないためです。ECサイト制作費用もまた、以前は補助対象でしたが2024年度からは対象外となったようです。 しかし、IT導入補助金が目的とする業務効率化や事業成長ために、ECサイトに導入するクラウドツールやソフトウェアは対象になる場合があります。また、サイバー攻撃に備えた情報セキュリティを強化する申請枠なども設けられているため、企業課題と照合しながら検討してみてはいかがでしょうか。
 引用元: IT導入補助金制度概要 IT導入補助金のしくみ より
引用元: IT導入補助金制度概要 IT導入補助金のしくみ より
中小企業や小規模事業者が業務の効率化や売上向上を目指してITツールを導入する際に、その費用の一部を支援するための制度です。この補助金の大きな特徴として、クラウドツールや業務用ソフトウェアなど、ITツールの導入にかかる経費が補助の対象となる点が挙げられます。 2025事業※では、最低賃⾦引上げへの対応促進に向けて最低賃⾦近傍の事業者の補助率を増加。更に、IT活⽤の定着を促す導⼊後の”活⽤⽀援”の対象化やセキュリティ対策⽀援を強化されています。
2025年3月31日から、IT導入補助金2025の受付が開始されました。
https://it-shien.smrj.go.jp/news/30039
IT導入補助金2025では、以下の4つの申請枠が設定されています。
通常枠
インボイス枠(インボイス対応類型・電子取引類型)
セキュリティ対策推進枠
複数社連携IT導入枠
それぞれの枠について解説していきます。
通常枠
IT導入補助金の通常枠は、中小企業や小規模事業者が業務効率化を目指してITツールを導入する際の費用を支援する制度です。この通常枠では、ソフトウェアの購入費やクラウド利用費(最大2年分)および導入関連費用が補助対象となります。ハードウェアの購入費は対象外となりますので注意が必要です。決められた業務プロセス1種類以上を保有するソフトウェアを申請することが要件となります。 補助率は対象事業者や導入プロセスの数によって異なります。
●補助対象者
中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業のほか、製造業や建設業等も対象)
小規模事業者
こちらより、自社が申請対象者なのか確認することができます。
●補助対象
ソフトウェアソフトウェア購⼊費、クラウド利⽤料(最⼤2年分)
導⼊関連費(オプション)機能拡張やデータ連携ツールの導⼊、セキュリティ対策実施に係る費⽤
導⼊関連費(役務の提供)導⼊・活⽤コンサルティング、導⼊設定・マニュアル作成・導⼊研修、保守サポートに係る費⽤
※ハードウェアの購入費は対象外
●補助率
中⼩企業:1/2
最低賃⾦近傍の事業者:2/3
●補助額
ITツールの業務プロセスが1プロセス以上:5万円以上150万円未満
ITツールの業務プロセスが4プロセス以上:150万円以上450万円以下
●申請スケジュール
横にスクロールできます
締切日 | 交付決定日 | 事業実施期間 | 事業実績報告期限 | |
|---|---|---|---|---|
1次締切分 | 2025年5月12日(月)(予定) | 2025年6月18日(水)(予定) | 交付決定~2025年12月26日(金)17:00(予定) | 2025年12月26日(金)(予定) |
2次締切分 | 2025年6月16日(月)(予定) | 2025年7月24日(木)(予定) | 交付決定~2026年1月30日(金)17:00(予定) | 2026年1月30日(金)(予定) |
3次締切分 | 2025年7月18日(金)(予定) | 2025年9月2日(火)(予定) | 交付決定~2026年2月27日(金)17:00(予定) | 2026年2月27日(金)(予定) |
最新スケジュールはこちらから
複数社連携IT導入枠
複数の中小企業や小規模事業者が連携してITツールを導入する際に利用できる補助金制度が存在します。この枠組みでは、業務上で関係のある「サプライチェーン」や特定地域で事業を行う「商業集積地」に属する事業者同士が共同作業を通じて生産性向上を目指す取り組みが支援対象となります。 さらに、補助金を活用することで、機能的なシステムの導入を通じて業務の効率化を図れるだけでなく、市場における競争力の向上も目指せます。複数の事業者が連携することで、一社では実現が難しい大規模なプロジェクトへの取り組みが可能になります。 例えば、サイト制作においても、アクセス解析が可能なシステムの導入や、その導入に伴う外部専門家への相談費用が補助の対象となります。
●補助対象者
商工団体等(例)商店街振興組合、商工会議所、商工会、事業協同組合 等
当該地域のまちづくり、商業活性化、観光振興等の担い手として事業に取り組むことができる中小企業者または団体(例)まちづくり会社、観光地域づくり法人(DMO)等
複数の中小企業・小規模事業者等により形成されるコンソーシアム
こちらより、自社が申請対象者なのか確認することができます。
●補助対象
(1)基盤導⼊経費
ITツール:会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトに限る 【クラウド利⽤料は最⼤2年分】
ハードウェア:PC・タブレット、レジ・券売機等
(2)消費動向等分析経費
ITツール:消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、電⼦地域通貨システム、キャッシュレスシステム、⽣体認証決済システム 等 【クラウド利⽤料は1年分】
ハードウェア:AIカメラ、ビーコン、デジタルサイネージ 等
(3)参画事業者のとりまとめに係る事務費、専⾨家費
●補助率
(1)基盤導⼊経費:1/2〜3/4、4/5(インボイス枠インボイス対応類型と同様)
(2)消費動向等分析経費:2/3以内
(3)事務費、専⾨家費:2/3以内
●補助額
補助上限額:(1)と(2)をあわせて3,000万円、(3)は200万円
●申請スケジュール
横にスクロールできます
締切日 | 交付決定日 | 事業実施期間 | 事業実績報告期限 | |
|---|---|---|---|---|
1次締切分 | 2025年6月16日(月)(予定) | 2025年7月24日(木)(予定) | 交付決定~2026年1月30日(金)(予定) | 2026年1月30日(金)(予定) |
最新スケジュールはこちらから
インボイス枠(インボイス対応類型)
インボイス枠のインボイス対応類型は、インボイス制度に対応した会計ソフトや受発注ソフト、決済ソフト、PC・ハードウェアなどを導入する際の経費の一部を補助するための申請枠です。この制度は、請求書の電子化や発行・管理を通じて業務を効率化することを目的としており、特に中小企業や小規模事業者が対象となっています。導入の際には、ソフトウェアの新機能や、データ連携、セキュリティ対策ツールのオプションを含んだ作成プロセスに関わる費用も補助対象として認められます。ECサイトにインボイス制度対応の決済ソフトを導入するケースなどが考えられます。
●補助対象者
中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業のほか、製造業や建設業等も対象)
小規模事業者
こちらより、自社が申請対象者なのか確認することができます。
●補助対象
(1)ソフトウェア、オプション、役務
ソフトウェア購⼊費、クラウド利⽤料(最⼤2年分)、オプション(セキュリティソフト等)、役務費(導⼊⽀援費、保守費等)
※インボイス制度に対応し、「会計」・「受発注」・「決済」の機能を有するものに限る。
(2)ハードウェアソフトウェア・クラウドサービスの使⽤に資する機器(PC・タブレット、レジ・券売機等)の購⼊費⽤、設置費⽤
●補助率・補助額
会計・受発注・決済ソフト
横にスクロールできます
補助率 | 3/4以内、4/5以内※1 | 2/3以内 |
|---|---|---|
補助額 | 50万円以下※2 | 50万円超〜350万円以下※3※4 |
PC・ハードウェアなど
横にスクロールできます
補助対象 | PC・タブレットなど | レジ・券売機など |
|---|---|---|
補助率 | 1/2以内 | 1/2以内 |
補助額 | 10万円以下 | 20万円以下 |
※1 中小企業は3/4以内、小規模事業者は4/5以内
※2 「会計」・「受発注」・「決済」のうち1機能以上を有することが機能要件
※3 補助額50万円超の際の補助率は、補助額のうち50万円以下については3/4(小規模事業者は4/5)、50万円超については2/3
※4 「会計」・「受発注」・「決済」のうち2機能以上を有することが機能要件
●申請スケジュール
横にスクロールできます
締切日 | 交付決定日 | 事業実施期間 | 事業実績報告期限 | |
|---|---|---|---|---|
1次締切分 | 2025年5月12日(月)(予定) | 2025年6月18日(水)(予定) | 交付決定~2025年12月26日(金)17:00(予定) | 2025年12月26日(金)(予定) |
2次締切分 | 2025年6月16日(月)(予定) | 2025年7月24日(木)(予定) | 交付決定~2026年1月30日(金)17:00(予定) | 2026年1月30日(金)(予定) |
3次締切分 | 2025年7月18日(金)(予定) | 2025年9月2日(火)(予定) | 交付決定~2026年2月27日(金)17:00(予定) | 2026年2月27日(金)(予定) |
最新スケジュールはこちらから
インボイス枠(電子取引類型)
インボイス枠(電子取引類型)は、インボイス制度へ対応した受発注システムを商流単位で導入する企業を支援する補助金です。本制度の目的は、電子的な取引を推進し、効率的でスムーズな事業運営を実現することにあります。この補助金は、取引関係における発注者がインボイス制度対応のITツール(受発注ソフト)を導入し、取引先である中小企業や小規模事業者などの受注者に対して無償でアカウントを提供し、その利用を可能にする仕組みを支援します。これにより、発注者と受注者の双方で効率的な取引が可能となり、業務全体の効率化が期待されます。
●補助対象者
中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業のほか、製造業や建設業等も対象)
小規模事業者
その他の事業者(⼤企業も可)
こちらより、自社が申請対象者なのか確認することができます。
●補助対象
ITツールの導⼊費⽤(クラウド利⽤料最⼤2年分)
●補助率
中⼩企業・⼩規模事業者等が申請する場合:2/3以内
⼤企業等が申請する場合:1/2以内
●補助額
350万円以下
●申請スケジュール
横にスクロールできます
締切日 | 交付決定日 | 事業実施期間 | 事業実績報告期限 | |
|---|---|---|---|---|
1次締切分 | 2025年5月12日(月)(予定) | 2025年6月18日(水)(予定) | 交付決定~2025年12月26日(金)17:00(予定) | 2025年12月26日(金)(予定) |
2次締切分 | 2025年6月16日(月)(予定) | 2025年7月24日(木)(予定) | 交付決定~2026年1月30日(金)17:00(予定) | 2026年1月30日(金)(予定) |
3次締切分 | 2025年7月18日(金)(予定) | 2025年9月2日(火)(予定) | 交付決定~2026年2月27日(金)17:00(予定) | 2026年2月27日(金)(予定) |
最新スケジュールはこちらから
セキュリティ対策推進枠
セキュリティ対策に特化した補助金として「セキュリティ対策推進枠」が設けられています。この枠では、サイバー攻撃に備えた情報セキュリティの強化を目的に、セキュリティソフトや関連サービスの利用費用が補助対象となります。特に、情報漏洩やデータ管理の重要性が増す今、こうした対策を導入することは企業の信頼性向上に直結します。本補助金を申請する際には、利用するセキュリティソフトが情報処理推進機構(IPA)による「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービスのうち、IT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に登録されたサービスを導入する際、サービス利用料(最大2年分)が補助されます。
●補助対象者
中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業のほか、製造業や建設業等も対象)
小規模事業者
こちらより、自社が申請対象者なのか確認することができます。
●補助対象
ITツールの導⼊費⽤(サービス利⽤料の最⼤2年分)
※本事業において補助の対象となるITツールは、独⽴⾏政法⼈情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービスのうち、本事業においてIT導⼊⽀援事業者が提供し、かつ事務局に事前登録されたサービスを指す。
●補助率
補助率 中⼩企業が申請する場合:1/2以内
⼩規模事業者が申請する場合:2/3以内
●補助額
5万円〜150万円以下
●申請スケジュール
横にスクロールできます
締切日 | 交付決定日 | 事業実施期間 | 事業実績報告期限 | |
|---|---|---|---|---|
1次締切分 | 2025年5月12日(月)(予定) | 2025年6月18日(水)(予定) | 交付決定~2025年12月26日(金)17:00(予定) | 2025年12月26日(金)(予定) |
2次締切分 | 2025年6月16日(月)(予定) | 2025年7月24日(木)(予定) | 交付決定~2026年1月30日(金)17:00(予定) | 2026年1月30日(金)(予定) |
3次締切分 | 2025年7月18日(金)(予定) | 2025年9月2日(火)(予定) | 交付決定~2026年2月27日(金)17:00(予定) | 2026年2月27日(金)(予定) |
最新スケジュールはこちらから
引用元:
サービス等⽣産性向上IT導⼊⽀援事業『IT導⼊補助⾦2025』の概要
Webサイト・ホームページ制作の補助金や助成金を申請する流れ

補助金や助成金を申請する際は、いくつかのステップを踏む必要があります。公式サイトや補助金情報の専門サイトを積極的に活用し、最新情報を取得しながら自社の事業内容や経営方針に合致する制度を選んでいきましょう。
補助金を探す
補助金や助成金を見つけるためには、効率的な情報収集が重要です。まず、各自治体や経済産業省が公開している公式サイトをチェックすることが基本となります。これらの公式情報は正確で最新のものが提供されているため、見逃さずに確認しましょう。また、商工会議所や業界団体も有益な情報源となります。これらの団体では、中小企業向けの補助金や助成金に関する情報を定期的に発信していることが多いため特に注意が必要です。
さらに、補助金や助成金に特化したサポートを提供する専門のコンサルタントを活用することで、情報収集と申請プロセスの効率を大幅に向上させることが可能です。特に、サイト制作に関する助成金を探している場合には、その分野に詳しい専門家のアドバイスを受けることで、有利な条件を見つけやすくなります。これらの方法を組み合わせることで、必要な資金援助を効率的に見つけることが期待できます。
申請に必要な書類を作成する
補助金の申請に際しては、必要書類を整えることが欠かせません。今回ご紹介している支援制度について、一つ一つ説明するのは現実的ではないので割愛しますが、必ず公式サイトにて最新の正確な情報を得るようにしてください。
具体的には、事業計画書や経費の明細、法人登記簿謄本、申請者の身分証明書などが求められます。特に事業計画書は、どのように補助金を活用して事業を展開するかを示す重要な文書であり、提出先の要件に応じて詳細を記載する必要があります。また、申請前に必ず提出先のホームページや関連Webサイトを確認し、求められる書類の最新情報を入手しましょう。情報が頻繁に更新される場合もあるため、正確かつ最新の内容に基づいて書類を準備することが申請成功の鍵となります。 時間を要しますが書類の作成や確認を怠らず、支援を受ける目的のためにもプロセス全体を慎重に進めていくことが重要です。
補助金を申請する
今一度申請書類は正確に準備し、必要な書類が揃っているか確認しましょう。書類の不備は審査の遅延や不採択につながるため注意が必要です。
申請方法は主に、書面による郵送か電子申請かを選ぶことになります。
電子申請を利用するには、gBizIDの取得が必要です。補助金申請における本人確認や法人確認をスムーズに行うことができます。まず、gBizIDを取得しておくことで、申請時の手続きが円滑になります。
申請後は、審査基準に基づいて早めに結果を確認し、採択されれば次のステップへ進みます。事業実施後には報告書を作成し、助成金が適切に使用されたことを示す必要があります。これらのプロセスを踏むことで、よりスムーズに補助金を活用できるでしょう。
採択となったら、交付申請を行う
採択の通知を受け取った後は、交付申請を行う段階に進むことになります。交付申請が認められたら、正式に「交付決定」となりますので、必ず忘れずに交付申請のステップを確実に実行しましょう。この段階での的確な進行が、スムーズな事業実施につながるでしょう。
事業実施後の報告と補助金の支給
補助金が交付された後は、実施した事業に関する報告が必要です。この報告は、補助金や助成金が正しく使用されたかを確認するための重要なプロセスとなります。具体的には、実績報告書を作成・提出し、事業において補助金がどのように使用されたかを明確に示すことが求められます。補助金が適正に活用されたかが審査され、報告が受理されれば補助金が支給されます。また、これらの報告手続きを適切に行うことで、次回以降の補助金や助成金の申請を円滑に進めるチャンスが広がります。事業実施後のフォローアップを怠らず確実に進めることが成功への鍵となります。
Webサイト・ホームページ制作で補助金・助成金を活用する際の注意点
サイト制作における助成金や補助金の活用は、多くの企業にとってコストを抑えながら質の高いWebサイトを構築するための魅力的な選択肢です。ただし、これらを効果的に活用するためにはいくつかの注意点があります。計画を立てる際はそれらを十分に把握しておく必要があります。計画的かつ適正に支援を活用することで、サイト制作に関する費用負担を軽減し、ビジネスの成長に繋げることが期待できます。
採択されない場合もある
補助金や助成金の申請は必ずしも採択されるわけではありません。各補助金や助成金には明確な審査基準が設定されており、申請内容がその要件を満たしていない場合、却下される可能性があります。そのため、申請前には自社の事業内容や計画がその基準に適合しているかを十分に検討することが重要です。資料に不備があったり、情報が不足している場合は、それだけで審査基準に満たないとされ、採択されないと思っていた方が良いと考えます。
そのため、仮に採択されなかった場合でも事業運営に支障をきたさないよう、別の資金調達方法や支援プランを併用しておくことが賢明です。このような事前準備によってリスクを最小限に抑えることができます。
申請書類は正確に揃える必要がある
補助金の申請には多くの書類が必要です。この書類は正確に、しかも適切に揃えて提出しなければなりません。上記でもお伝えしましたが、不備や誤記がある場合、審査が遅れる原因になるだけでなく、最悪の場合には不採択となる可能性もあります。特に事業計画書や経費明細書は、申請内容を裏付ける重要な書類であり、内容をしっかりと確認したうえで提出することが求められます。
サイト制作だけでは補助金を申請できない
補助金の対象として認められるには、サイト制作そのものだけでは不十分な場合があります。多くの補助金では、単独の制作費用ではなく、事業全体の効率化や新規事業の創出に寄与する内容であることが求められます。したがって、事業計画に基づいた総合的な提案が必要です。単にサイトを作成するだけでは評価されないことが多いため、事業目標や戦略を明確にしておくことが効果的です。
補助金は後払いで支給される
多くの補助金制度や助成金制度では、事業が実施された後に支給される後払い方式となっています。そのため、サイト制作費の補助対象となる費用についても、まずは自社・自己の資金で支払いを済ませた後に補助金や助成金が支給される仕組みです。このような後払い制度では、事業を実行するための資金を事前に確保しておくことが重要です。もし資金繰りに不安がある場合は、銀行や金融機関からの融資を含めた資金調達方法を検討する必要があります。補助金や助成金を活用する際には、後払い制度の特性やスケジュールを十分に理解し、資金計画をしっかりと立てることが必須です。
リニューアルは補助対象外のケースが多い
新規のWebサイトやホームページ作成に対する補助金は存在しますが、既存サイトのリニューアルや改修については補助対象外となる場合が多いです。多くの補助金制度は、主に販路開拓や業務効率化を目的としており、単なる会社概要や事業内容の紹介にとどまるホームページ制作は対象外になる可能性が高いです。
ただし、サイトリニューアルも対象になる自治体の制度があったり、事業計画内容次第では申請が通る場合もありますので、よく制度をリサーチすることが重要です。
不正利用が発覚した際の対応
補助金や助成金を不正に利用した場合、返還請求や法的措置が取られることがあります。不正事例としては、申請内容を偽る行為や、実際には実施していない事業に対して助成金を受け取る行為などが挙げられます。不正利用が発覚した場合、企業や個人の信頼を大きく損ねるだけでなく、今後の助成金や補助金の申請が制限される可能性もあります。透明性の高い運営を心掛けることが重要です。申請時には正確な情報を記載し、受給後はサイトや公式な資料を活用して進捗を公開し、申請内容と実施内容が一致していることを証明するよう努めましょう。また、受給後においても、資金の適切な管理や実施内容が規定に沿っているかどうかを細かく確認することが不可欠です。
まとめ
Webサイト・ホームページ制作費に関する補助金や助成金の利用は、中小企業や個人事業主にとって、事業成長を支える重要な資金調達手段の一つです。これらを効果的に活用することで、制作コストを大幅に抑えながら、効果的なプロモーションやオンラインでの集客を実現することが可能となります。 特に近年、オンライン化が進む中で、持続可能なビジネスモデルを実現するためには、戦略的にWebサイトを活用することが非常に重要です。支援制度を賢く活用することで、費用を適切にを抑えながら競争力を高め、事業の成功につなげていくことを目指しましょう。
今回ご紹介した補助制度を活用するのであれば、より一層事業に成果をもたらすためにも、クオリティの高いサイト制作が必要になります。株式会社デパートでは、事業計画内容をご共有いただき、どのようなサイト戦略にすべきか、からご一緒させていただいております。まずはお気軽にご相談ください。
Contact
制作のご依頼やサービスに関するお問い合わせ、
まだ案件化していないご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
- この記事をシェア