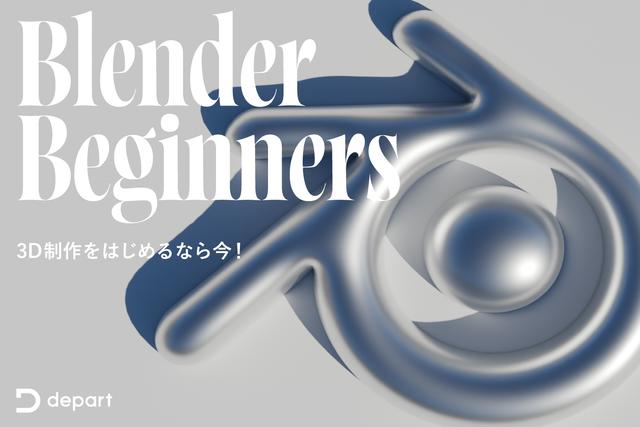- Share On
目次
目次
- CMSとは
- 【比較】CMSは大きく分けて3つある
- 1.クラウド型
- 2.パッケージ型
- 3.オープンソース型
- CMSを利用するメリット
- 専門的な知識が必要ない
- PC以外の端末にも対応できる
- ページごとに分業できる
- CMSを利用するデメリット
- セキュリティ面の不安がある
- CMS自体の操作を覚える必要がある
- 応用が利きにくい
- 会社に合ったCMSを選ぶポイント
- 機能や操作性が複雑ではないか
- 予算内で運用できるか
- よく使われているおすすめのCMS
- WordPress
- Movable Type
- Drupal
- 汎用型のおすすめCMS
- FREECODE
- Connecty CMS on Demand
- BlueMonkey
- HeartCore
- 用途特化型のおすすめCMS
- CMSHub
- ShareWith
- Company Cloud
- ferret One
- まとめ
当記事では「Webサイトの構築にCMSを使いたいがどれを選んだらいいか分からない」「WordPressは難しくて挫折しそう」とお悩みの方に、CMSの概要やメリットを解説しつつ、用途別のおすすめCMSを比較できるよう11選ご紹介します。
ブランディングや人材採用など、企業の存在を世間へアピールするには、コーポレートサイトやオウンドメディアの存在が欠かせません。しかし、必要性を理解している一方、人材不足が災いしてWebサイトのリニューアルやオウンドメディアの立ち上げを断念している方も多いのではないでしょうか。その課題を解決するためにCMSをうまく取り入れましょう。
CMSとは
CMS(Contents Management System)とは、Webサイトの構築や管理、運用を行うシステムやツール群です。最大の特徴は、HTMLやCSSなどプログラミングスキルがなくてもWebサイトを構築できるところにあります。
【比較】CMSは大きく分けて3つある
CMSはツールの仕様によって以下の3タイプに大別されます。
クラウド型
パッケージ型
オープンソース型
ここからは、上記3つそれぞれの特徴を解説します。
1.クラウド型
クラウド型とは、インターネット上で作成・運用を完結するタイプです。サーバーやソフトウェアを自身で用意する手間がかからないため、初期コストを比較的安く抑えられます。
ほかのタイプに比べるとWebサイトの自由度が低いことがデメリットですが、ある程度ひな形ができあがっているため知識がなくても完成度の高いWebサイトを作成できます。
2.パッケージ型
パッケージ型とは、CMSソフトウェアを販売している企業からライセンスを購入し、自社のサーバーに導入するタイプです。
営利目的を想定した仕様なため、比較的規模の大きいWebサイトを運用する際に用いられるケースが多いです。自社内に環境を設置することから「オンプレミス型」とも呼ばれます。
3.オープンソース型
オープンソース型とは、インターネット上に無償公開されているソースコードやプログラムの設計図を利用して、自分でWebサイトを構築するタイプです。オープンソース型は個人ブログからECサイトまで、当人のスキル次第でサイトのUIやシステムの仕様を自在に構築できます。
CMSを利用するメリット
ここからは、CMSの利用でどんなメリットを享受できるのか解説します。CMSは趣味でブログを作りたい個人から、企業のWeb担当者まで幅広い層にとって有益なツールです。
専門的な知識が必要ない
CMSはプログラミングに精通していなくてもWebサイトを簡単に構築・運用できます。CMSがない場合、HTMLやCSS、PHPなどプログラミング言語の使用は避けられません。
PC以外の端末にも対応できる
CMSは、種類によってスマートフォンやタブレット端末からも操作可能です。本来Webサイトの構築・運用はPCで行うものですが、CMSを用いればサイトで使う画像データやコンテンツのテキスト情報をデータベースに保存し、別のデバイスから操作できます。
ページごとに分業できる
CMSは複数人で同時アクセスできる共通プラットフォームなため、ページや分野ごとで各担当者に作業を分けられます。専門知識が必要ないため、システムの仕様やプログラムをいちいち担当者へ聞く必要もありません。
例えば、ファッション雑誌の編集部でオウンドメディアを立ち上げる場合、CMSを使えばIT部門を設立せずとも、編集部に所属する者だけでメディアを運用できます。
CMSを利用するデメリット
ここからは、CMSに存在するデメリットについて解説します。CMSは誰でも気軽にWebサイト運用を始められる便利なツールですが、Webに関する知識やリテラシーがまったくない状態で始めるには少々リスキーです。
セキュリティ面の不安がある
CMSはWebの知識に疎い人でも使えることから、セキュリティの脆弱性を突いたサイバー攻撃の標的にされることがあります。CMSを標的としたサイバー攻撃には、以下の手法が例として挙げられます。
サプライチェーン攻撃(セキュリティの甘い会社の侵入を契機に関連会社に不正アクセスする手法)
ランサムウェア攻撃(ウイルスを仕込んだメールやWebページを契機に侵入し、データの復旧と引き換えに身代金を要求する手法)
SQLインジェクション(お問い合わせフォームに悪質なプログラムを組み込んだテキストを送信し、機密データの入手やデータの改ざんを行う手法)
特に近年では企業やWebサイトの規模を問わずに攻撃する傾向があるため、Webサイトの運営に際しては小規模であってもセキュリティ対策は必要です。
CMS自体の操作を覚える必要がある
CMSは初心者でも扱えるよう操作性が重視されたツールですが、Webに関する最低限の知識や管理画面の操作方法を知っておかなくてはなりません。例えば「ヘッダー」や「フッター」といったワードはCMSでも頻繁に使用されます。
応用が利きにくい
CMSはWeb制作に必要な機能をボタン1つで作成できますが、機能の範疇を超えたアレンジにはプログラミングスキルが必要です。特にテンプレートを使っている場合は、できる範囲が大幅に限定されます。
会社に合ったCMSを選ぶポイント
CMSを使うと決めても、タイプ・機能・操作性・自由度はツールによってさまざまです。Webサイトを作るには、運用の用途や担当者のスキルレベルに応じて、適したCMSを選ばなければなりません。ここからは、自社に合ったCMSを見つけるポイントを解説します。
機能や操作性が複雑ではないか
CMSに搭載されている機能やツールの操作性は、担当者のITリテラシーのレベルに合わせたものを選びましょう。例えば、Webに関する知識がない場合は、直感的に操作できるCMSがおすすめです。
知識やWebサイト運営の経験がある場合は高度なツールを、専門知識がなく初めてWebサイトを運営する場合は直感的に操作できるツールを選ぶのが賢明です。
予算内で運用できるか
Webサイト運営の事業に割かれている予算に適したCMSを選びましょう。例えば、クラウド型やオープンソース型ならランニングコストを安く抑えられますが、パッケージ型だとある程度の費用を見積もらなければなりません。
自社にサーバーがない状態でWebサイトを運営するには、以下の維持コストも発生します。
レンタルサーバー代
ドメイン費用
SSL費用
Webサイトを制作して運営するなら、予算と維持コストのバランスを勘案しなければなりません。
よく使われているおすすめのCMS
初めてWebサイトを開設して運営する場合、周囲の企業が使っているツールを選ぶのも1つの手段です。ここでは、Webサイト運営の現場でよく使われているCMSを2つご紹介します。
WordPress

画像引用元:https://wordpress.com/ja/
WordPressとは、拡張機能やデザインのテンプレートが豊富な、基本無料のオープンソース型CMSです。国内では、Webサイト運営において圧倒的なシェアを誇っています。
WordPressのメリットは以下の通りです。
直感的で簡単な操作性
SEO対策に強い
マルチデバイスに対応
一方、以下のデメリットが存在します。
メーカーサポートがない
サーバーやドメインなど自力でのインフラ構築が必要
静的サイト(表示内容が変化しないWebサイトのこと)よりも表示速度が遅い
基本無料かつテーマが豊富なので、初心者が選ぶCMSとしておすすめです。
Movable Type

画像引用元:https://www.sixapart.jp/movabletype/
Movable Typeとは、セキュリティ対策と表示速度を得意とする、営利目的や公的機関に人気のあるパッケージ型・クラウド型CMSです。
パッケージ版とクラウド版で料金体制が異なり、パッケージ型なら買い切り99,000円(税込)、クラウド型の場合は月額5,500円〜(税込)のコストが必要です。また、別バージョンの「Movable Type.net」というWebサービス版もリリースされており、こちらは月額2,750円〜(税込)で利用できます。
Movable Typeのメリットは以下の通りです。
1つのCMSで複数のWebサイトを構築できる
表示速度が速い
セキュリティに強い
一方、以下のデメリットには注意しなければなりません。
営利目的なら有償ライセンスの購入が必要
プラグインが少ない
導入ハードルが高い
Movable Typeはセキュリティ面やメーカーサポートが手厚い分、中規模〜大規模のWebサイト運営におすすめです。
Drupal

画像引用元:https://www.drupal.org/
Drupalは、規模が大きいWebサイトの構築や多言語機能に長けているオープンソース型CMSを使いたい方に適しているCMSツールです。企業はもちろん、政府や教育機関のWebサイトにも導入されている実績があります。
Drupalのメリットは以下の通りです。
標準で100近い言語に対応している
Web ガバナンスの統制に向いてる
一方で、以下のデメリットが存在します。
日本人利用者が少なく情報量が少ない
拡張モジュールの中には有料のものがある
Drupalは、拡張モジュールが多く拡張性に優れているCMSです。しかし、日本語による解説が少ないため専門的に活用できるユーザーが少なく、ほかのCMSよりもスキルが必要なツールといえるでしょう。
汎用型のおすすめCMS
長期でWebサイトを運営していると、事業の拡大やWeb業界の変化からサイトデザインを大幅に変更、または大型リニューアルする場合があります。将来的なアップデートを想定する場合、自由度が高いCMSがおすすめです。ここでは、汎用型のCMSを5選ご紹介します。
FREECODE
FREECODEとは、SEO対策やセキュリティ強度が強みの、クラウド型CMSです。導入に際して初期ライセンス費用85,000円〜(税別)と、月額料金13,500円〜(税別)のコストがかかります。用途別のモデルプランも別途用意されているため、目的と予算に合わせた選択も可能です。
FREECODEを利用するメリットは以下の通りです。
幅広い料金プラン
無料のスキルアップセミナーやマニュアルのPDFなどアフターサポートが充実
サーバーセキュリティが強固
一方、以下のデメリットには注意しなければなりません。
導入・維持コストが高い
専門性が高く操作が複雑
FREECODEは高度な機能を有している分、知識とスキルが求められるため、ある程度Webサイト運営の経験がある中級〜上級者向きといえます。
Connecty CMS on Demand
Connecty CMS on Demandは、データマネジメントとWebサイト運営を兼用できるクラウド型CMSです。主に大企業向けのプラットフォームとしてリリースされています。330,000円〜(税込)のライセンス費用と月額利用料60,000円〜(税込)が主な費用です。
Connecty CMS on Demandのメリットは以下の通りです。
大規模サイトに必要な機能を網羅
多言語対応でグローバル運用が可能
静的・動的サイトを両立できる
一方、以下の点がデメリットといえます。
導入コストが高い
小規模サイトでは機能を持て余す
総じてハイコスト・ハイパフォーマンスなのがConnecty CMS on Demandの特徴です。求められるスキル水準も高いため、上級者・大規模サイト運営向けのCMSといえます。
BlueMonkey
BlueMonkeyは、シンプル設計と手厚いサポートが特徴のクラウド型CMSです。主に中小企業の利用を想定した仕様で、導入に際しては月額料金39,600円〜(税込)と、Webサイト制作費用1,650,000円〜(税込)が発生します。
BlueMonkeyのメリットは以下の通りです。
初心者でも扱いやすい操作設計
サポートが手厚い
サイトデザインを委託できる
一方、以下のデメリットには注意しなければなりません。
初期コストが高額
機能に制限がある
必要に応じて別途オプション費用がかかる
BlueMonkeyはCMSの提供と同時にWebサイト制作も任せられるため、運営を早期にスタートしたい企業に向いています。
HeartCore
HeartCoreは、WebサイトだけでなくアプリケーションやSNSとの連携が可能なパッケージ型CMSです。サイト運営に必要な機能がオールインワンで入っているため、多種多様な用途に活用できます。購入に際しては導入支援も同時に行うため、料金は基本的に要問い合わせです。
HeartCoreのメリットは以下の通りです。
金融業界の導入実績があるほどの強固なセキュリティ
既存サイトやコンテンツの移行を委託できる
一方で、以下のデメリットが存在します。
料金が要問い合わせ
小規模サイトでは機能を持て余す
操作に慣れが必要
HeartCoreは、Webサイト運営に必要な機能とセキュリティが一括で準備できる分、導入費用は比較的高額です。したがって、中規模以上のサイト運営向きといえるでしょう。
用途特化型のおすすめCMS
Webサイトの用途が定まっていて、かつ今後も同じ用途でのみ使用する場合、なにかの機能に特化したCMSをおすすめします。ここからは、用途特化型CMSのおすすめ4選をご紹介します。
CMSHub
CMSHubは「HubSpot」が提供するCMSです。マーケティング・セールス・カスタマーサービス・CMS・オペレーションなどの各分野に特化した製品を、無料のCRMツールをベースにして展開しています。
ドラッグ&ドロップの直感的な操作と柔軟なテーマ変更が可能で、慣れていない方でも使いやすいCMSとしての機能が充実している特徴があります。HubSpot CRMのデータを活用した施策やテスト、分析などの機能を標準搭載しておりWebマーケティングにも強いサービスといえるでしょう。料金は月額0~144,000円まで利用できる機能によってさまざまです。
CMSHubのメリットは以下の通りです。
専門知識がない人でも扱えるシンプルな操作設計
Webサイト訪問者のデータを追跡可能
セキュリティ対策やメンテナンス、更新はHubSpot側で対応
ただし、以下のデメリットには注意しましょう。
プランによっては利用料金が高い
デザインの細かなカスタマイズはできない
CMSHubは、Webマーケティングに力を入れたい方や顧客情報を一元管理したい方などに向いています。
ShareWith
ShareWithは、直感操作とセキュリティ強度が特徴のクラウド型CMSです。主にコーポレートサイトの制作に特化した機能が充実しています。料金はライセンス費用750,000円〜と、月額料金120,000円〜がかかります。
ShareWithのメリットは以下の通りです。
専門知識がない人でも扱えるシンプルな操作設計
自動バックアップや24時間体制のサーバー監視など万全のセキュリティ体制
自動更新機能が標準搭載
ただし、以下のデメリットには注意しましょう。
デザインのカスタマイズはできない
導入・維持コストが高い
ShareWithは、IR発信や問い合わせフォームなどコーポレートサイトを作成したい企業や学習面のハードルを下げたい方に向いています。
Company Cloud
Company Cloudは、コーポレートサイトの支援に特化したクラウド型CMSです。初期費用は30,000円〜と月額料金50,000円〜と、同ジャンルのCMSに比べ低コストで導入できます。
Company Cloudのメリットは以下の通りです。
直感的に操作性で誰でも扱える
マーケティングにも使える
コンテンツ制作がスピーディー
一方、以下のデメリットには注意しなければなりません。
機能の追加にはオプション費用がかかる
デザインの変更や機能の拡充に時間がかかる
主にコーポレートサイトの運営にかかる負担を軽減したい方やサイトのリニューアルをしたい方に向いているCMSです。
ferret One
ferret Oneは、BtoB分野のマーケティング支援に特化したクラウド型CMSです。初期費用100,000円と、月額料金100,000円〜で利用できます。
ferret Oneのメリットは以下の通りです。
リードの獲得につながる機能が充実
AIアシスタント機能でアイデアの創出にも貢献
コンテンツ制作・集客・広告イベント・顧客データ管理など包括的にカバーできる
一方、月額料金が高いため、長期的な目線では高コストな点には気をつけなければなりません。主にITベンダーやコンサルタントで活用されます。
まとめ
自社専用のWebサイトを構築・運営するには、CMSの活用がおすすめです。基本的に専門知識のある人材がいなくても扱える仕様なため、人材不足に悩んでいる企業やスピーディーにサイト運営を始めたい方に適しているでしょう。
株式会社デパートでは、コーポレートサイトの立ち上げからコンテンツ戦略支援までWebに関わる課題解決の相談を受け付けています。自社の要件に合ったツールの選定や最適なサイトデザインの構築で悩んでいる担当者様は、お気軽にご相談ください。
Contact
制作のご依頼やサービスに関するお問い合わせ、
まだ案件化していないご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
- この記事をシェア