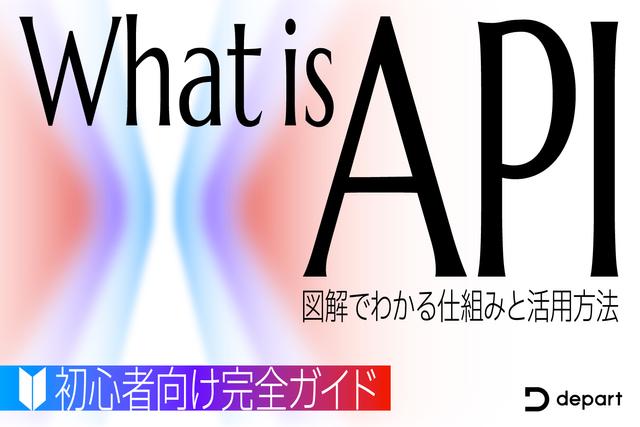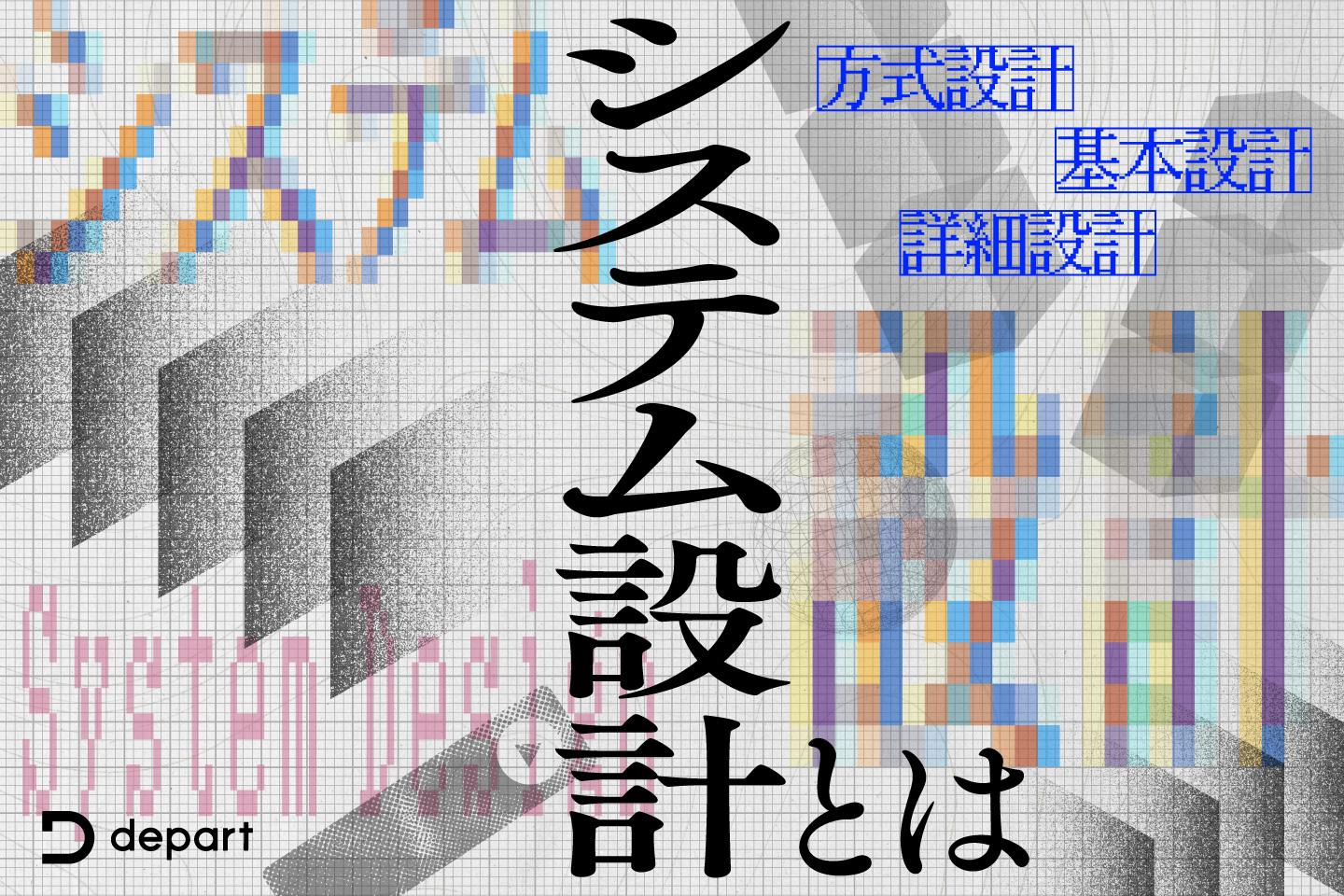
- Share On
目次
目次
- システム設計とはシステム開発の骨格を決める重要な工程
- システム開発における設計工程の全体像
- 【STEP1】方式設計:システムの技術的な基盤を定める
- ハードウェアやソフトウェアの構成を決める
- ネットワークの全体構成を設計する
- 【STEP2】基本設計(外部設計):ユーザーが直接触れる部分を作る
- 画面のレイアウトや操作方法を設計する
- システムで扱うデータの構造を定義する
- 外部システムとの連携方法を明確にする
- 【STEP3】詳細設計(内部設計):プログラミングの「設計図」を作成する
- プログラム内部の処理の流れを具体化する
- 機能ごとのモジュールの役割を細かく決める
- システム設計で失敗しないための4つのポイント
- 各工程で作成する成果物を事前に定義しておく
- 設計書のフォーマットを標準化し品質を均一にする
- 仕様変更があった場合は関連ドキュメントへ即時反映する
- 定期的なレビューで関係者間の認識を合わせる
- まとめ
- 要件定義からシステム設計、開発なら株式会社デパートにおまかせ
- システム設計・開発サービスをご紹介
システム設計とは、システム開発における要求を具体的な形にするための設計図を作成する重要な工程です。 この設計の工程は、大きく分けて「方式設計」「基本設計」「詳細設計」という種類に分かれており、この流れに沿って進めるのが一般的なやり方です。
この記事では、システム設計の全体像であるフローや手順、考え方について、その意味を含めてわかりやすく解説します。
システム設計とはシステム開発の骨格を決める重要な工程
システムの設計は、要件定義で決定した顧客の要求を、実際に開発できる仕様に落とし込む目的があります。 このステップでは、サービスの目的や範囲を基に、実装すべき機能や性能、セキュリティといった項目を具体化していくのが主な内容です。 ここで作成される設計の品質が低いと、開発の途中で手戻りが発生し、プロジェクト全体の進め方に大きな影響を及ぼします。
そのため、システムの骨格を定める観点から、非常に重要な工程と位置づけられています。 安定したサービスを提供するメリットを得るには、設計に必要な要素を洗い出し、適切なステップで進めることが求められます。
システム開発における設計工程の全体像
システム開発のプロセスは、顧客が何を求めているかを分析する要求分析から始まります。 次に、その要求を基に、開発するシステムの仕様や満たすべき要件を明確にする要件定義という工程に進みます。 この要件定義で作成される要件定義書は、後の設計工程の土台となる重要なドキュメントです。
システム設計は、この要件定義と、プログラマーが実際にコードを書く実装工程の間に位置づけられます。 つまり、要件定義書に記述された要件を、どのようにして技術的に実現するのかを具体的に定義し、開発者への橋渡しをする役割を担っています。
【STEP1】方式設計:システムの技術的な基盤を定める

方式設計は、システムの土台となる技術的な基盤やルールを定める工程です。 この段階では、システムの全体構成であるアーキテクチャの構築や、開発に使用するプログラミング言語、フレームワーク、各種ツールなどを選定します。
特に、性能や可用性、セキュリティといった非機能要件を要件定義書から深く掘り下げて検討し、システム運用における課題やリスクを未然に防ぐためのログ設計なども行います。
ハードウェアやソフトウェアの構成を決める
方式設計の段階では、システムを安定して稼働させるためのハードウェア構成を設計します。これには、サーバーの性能や台数、データの保存先となるストレージの種類や容量の決定などが含まれます。 また、システムを動かす基盤となるOS(オペレーティングシステム)や、データベース管理システム、Webサーバーといったミドルウェアなどのソフトウェアも選定しなくてはなりません。 将来的なシステムの拡張性や要求される性能を考慮しながら、ハードとソフトウェアの最適な構成を決定することが、この工程の目的です。これにより、安定したシステム稼働の基盤が築かれます。
ネットワークの全体構成を設計する
システムを構成するサーバーやデータベース、各種機器をどのように接続し、通信させるかを定義するのがネットワーク設計です。 具体的には、サーバー間の通信経路や、外部のインターネットとの接続方法、大量のアクセスを分散させるためのロードバランサーの配置、そして不正なアクセスを防ぐファイアウォールの設置場所などを決定します。
セキュリティの確保や、安定した通信速度の維持といった観点から、安全かつ効率的なデータ通信を実現するためのネットワーク構成を詳細に検討し、システムの全体像を固めます。
【STEP2】基本設計(外部設計):ユーザーが直接触れる部分を作る

基本設計は、ユーザーの視点からシステムの機能や操作性を設計する工程であり、ユーザーから見える部分を設計することから「外部設計」とも呼ばれます。 このステップでは、要件定義で定められた内容を基に、ユーザーが直接操作する画面のレイアウトや、システムが提供する具体的な機能を定義する機能設計を行います。
開発者ではなく、主に発注者やユーザーが内容を確認し、要求が満たされているかを判断するための重要な設計段階です。
画面のレイアウトや操作方法を設計する
基本設計の一部である画面設計では、ユーザーがシステムを利用する際に直接目にする画面の構成やデザイン、操作方法を具体的に定義します。 例えば、入力フォームやボタンといった部品の配置、画面から別の画面へ移る際の遷移ルール、エラーが発生した際のメッセージ表示方法などを明確にします。 また、システムから印刷される請求書や報告書といった帳票のフォーマットもこの段階で設計されることが一般的です。
ユーザーが直感的に操作でき、迷うことなく使えるようなレイアウトを設計することが、システムの満足度を高める上で欠かせません。
システムで扱うデータの構造を定義する
システムが機能するためには、様々なデータを管理する必要があります。 この工程では、システム内で扱うデータ項目を洗い出し、それらの構造を論理的に定義します。 具体的には、どのような情報をどのような形式でデータベースに保存するのか、またデータ同士がどのように関連し合っているのかを明確にします。
このデータの関連性を視覚的にわかりやすく表現するために、一般的にER図(Entity-RelationshipDiagram)が用いられます。 データの整合性を保ち、効率的なアクセスが可能となるようにデータベースの構造を定義することが目的です。
外部システムとの連携方法を明確にする
開発対象のシステムが単体で完結せずに他の外部システムと情報をやり取りする場合、その具体的な連携方法を設計する必要があります。 この外部インターフェース設計では、API(Application Programming Interface)を利用するのか、あるいは特定のフォーマットのファイルを介して連携するのかといった技術的な方式を決定します。
さらに、送受信するデータの形式、通信手順、連携を実行するタイミングなど、詳細な仕様を定義し、システム間のスムーズなデータ交換を実現するための方法を明確にします。
【STEP3】詳細設計(内部設計):プログラミングの「設計図」を作成する

詳細設計は「内部設計」とも呼ばれ、基本設計で定義した機能や仕様を、プログラマーが実際にプログラミングできるレベルまで具体的に落とし込む工程です。 この設計書は、システム内部の動き、つまりユーザーからは見えない部分の処理ロジックを記述するため、開発者向けの「設計図」と位置付けられます。
実装の品質を左右するため、豊富な経験や能力が求められ、未経験のエンジニアにとっては難しい部分も多くあります。
プログラム内部の処理の流れを具体化する
詳細設計では、基本設計で定義された一つひとつの機能を実装するために、プログラム内部における具体的な処理の流れを設計します。 オブジェクト指向開発のアプローチを取る場合、システムの構成要素を「クラス」として定義し、それらの関係性や構造をクラス図を用いて視覚的に表現します。
また、各クラスがどのようなデータを持ち、どのような処理(メソッド)を実行するのかを明確化します。 開発で利用するフレームワークの規約に従いながら、効率的で保守性の高いコーディングが可能になるよう、具体的な処理ロジックを組み立てていきます。
機能ごとのモジュールの役割を細かく決める
詳細設計では、システム全体をより小さな機能の集まりに分割し、それぞれを独立した部品である「モジュール」として設計するアプローチが一般的です。 このモジュール分割によって、各機能の役割と責任範囲が明確になり、複数の開発者による並行作業や、後の機能改修が容易になります。
各モジュールが担当する具体的な処理内容や、他のモジュールとデータをやり取りするためのインターフェース(情報の受け渡し口)などを細かく定義し、再利用しやすく独立性の高い部品として組み立てていくことが、保守性の高いシステム構築につながります。
システム設計で失敗しないための4つのポイント

システム設計の品質は、その後のプログラミングやテストといった開発工程の効率化、さらにはプロジェクト全体のスケジュールや工数に直接的な影響を与えます。 設計段階での考慮漏れや誤りは、後工程での大規模な手戻りを引き起こす原因となりかねません。
ここでは、設計の品質を高め、プロジェクトを成功に導くためのおすすめの方法論を4つの例を挙げて紹介します。
各工程で作成する成果物を事前に定義しておく
プロジェクトを開始する前に、方式設計、基本設計、詳細設計といった各工程で作成すべき成果物を具体的に定義しておくことが失敗を防ぐポイントです。 例えば、基本設計では画面仕様書や帳票一覧、ER図を成果物とし、詳細設計ではクラス図やシーケンス図を作成するといったように、必要な設計書の種類を関係者間で事前に合意します。
要件定義書の内容を基に、どのようなシステムの設計書が必要になるかを洗い出すことで、作業の抜け漏れを防止し、後工程へのスムーズな引き継ぎが可能になります。
設計書のフォーマットを標準化し品質を均一にする
プロジェクトに参加する設計者が複数名いる場合、設計書のフォーマットを標準化することで、ドキュメントの品質を均一に保つことが可能です。 事前にテンプレートを用意し、記載すべき項目や図の書き方といったルールを標準として定めておくことで、担当者による記述レベルのばらつきや記載漏れを防ぎます。
標準化されたフォーマットは、レビュー担当者が内容を理解しやすくなるため、チェック作業の効率化にも貢献します。 これにより、誰が見てもわかりやすい、一貫性のある設計書の作成が実現します。
仕様変更があった場合は関連ドキュメントへ即時反映する
システム開発プロジェクトにおいて、仕様の変更は避けられない事象です。 重要なのは、設計変更が発生した際に、関連する全てのドキュメントへその内容を速やかに反映させることです。 設計書と実際のプログラムの内容に食い違いが生じると、テスト工程での不具合や、将来の保守作業における混乱の原因となります。
変更管理のルールを定め、設計書や仕様書のバージョン管理を徹底し、常に最新の状態を維持することが、プロジェクトメンバー間の認識のズレを防ぎ、システムの整合性を保つ上で不可欠です。
定期的なレビューで関係者間の認識を合わせる
設計書の作成後、次の工程に進む前にレビューの機会を設けることは、設計の品質を担保する上で極めて重要です。 レビューには設計担当者だけでなく、プロジェクトマネージャーや開発者、テスト担当者など、異なる立場の関係者が参加し、多角的な視点から内容を検証します。
これにより、設計の誤りや要件の解釈違い、考慮漏れなどを早期に発見できます。 また、関係者間で設計内容に対する認識を合わせることで、後工程での手戻りを未然に防ぎ、プロジェクト全体を円滑に進行させる効果が期待できます。
まとめ
システム設計は、顧客の要求を定義する要件定義と、実際にプログラムを構築する実装工程とをつなぐ、システム開発の中核的なプロセスです。 方式設計でシステムの技術的な土台を固め、基本設計でユーザーから見える部分の振る舞いを定義し、詳細設計で内部の具体的な処理ロジックを組み立てます。
この一連の流れを丁寧に進めることで、無駄な手戻りをなくし、スムーズな開発を実現できます。 Webサービスや業務アプリなど、どのようなシステムを構築する場合でも、各工程の役割を正しく理解し、計画的に設計を進めることが成功の鍵となります。
要件定義からシステム設計、開発なら株式会社デパートにおまかせ
株式会社デパートでは、要件定義からシステム設計、開発を一貫して対応可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
システム設計・開発サービスをご紹介
Contact
制作のご依頼やサービスに関するお問い合わせ、
まだ案件化していないご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
- この記事をシェア