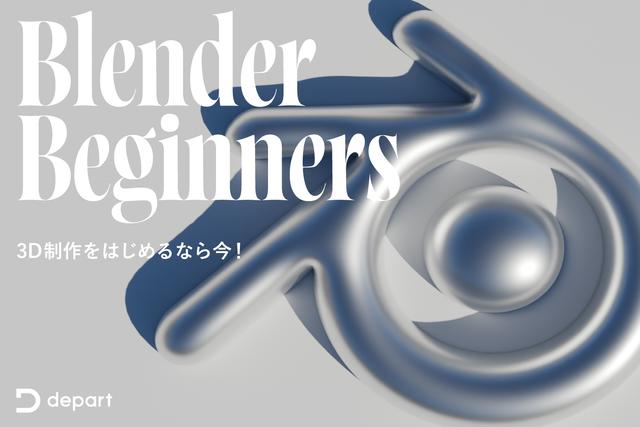- Share On
目次
目次
- Webサービスの定義
- WebサイトとWebアプリケーションとの相違点
- Webサービスの種類
- コミュニケーション関連サービス
- 情報提供型サービス
- ショッピング関連サービス
- 決済関連サービス
- マッチング関連サービス
- 相談対応サービス
- オンライン会議用サービス
- 業務効率化ツール
- ストレージサービス
- Webサービス制作のプロセス
- ステップ1:戦略の構築
- ステップ2:企画書(RFP)の作成
- ステップ3:要件の定義
- ステップ4:基本設計の構築
- ステップ5:詳細設計のステップが必要
- ステップ6:構築
- ステップ7:テスト運用
- ステップ8:サービスの公開
- ステップ9:公開後の管理と効果測定
- Webサービスの企画を成功させるためのポイント
- 課題を具体的に捉える
- ユーザー目線で考える
- 調査に時間をかける
- Webサービスを制作会社に外注するときのポイント
- 明確な目的と目標を共有する
- 制作会社の実績を確認する
- 綿密な要件定義を行う
- 徹底した進行管理を行う
- まとめ
Webサービスとは、インターネットを通じて利用者に機能や情報を提供するサービス全般を指します。本記事では、Webサービスとはどのようなものか、WebサイトやWebアプリとの違い、具体的な企画から開発までのプロセス、成功させるためのポイントや外注時の注意点まで、網羅的に解説します。
Webサービスの定義
Webサービスとは、インターネット上で提供されるサービス全般を指す言葉です。一般的にはWebブラウザを通じてアクセス・利用できるサービスのことを意味し、具体的にはECサイトやコミュニケーションサービスなどが挙げられます。ユーザーがクライアント(PCやスマートフォンなどの端末)でWebブラウザを通してリクエストを送信すると、Webサーバーがこれを受信し処理を行い、その結果をクライアントへレスポンスとして返す仕組みです。このレスポンスがクライアント側のブラウザで処理され、結果が表示されることでWebサービスが提供されます。Webサービスは単一の技術ではなく、セキュリティ技術やメッセージ技術、インターフェース記述技術など、様々な技術を組み合わせた複合的な仕組みによって成り立っており、多様な機能を提供しています。また、Webサービスは技術やプラットフォームに依存しないため、異なる言語で構築されたアプリケーション同士をWeb上で連携させるメディエーターとしても機能します。
動作の流れは以下のように定義可能です。
横にスクロールできます
・ユーザーが自身の端末(クライアント)でブラウザを通してリクエストを送信する ・サーバーがリクエストを受信し、処理を行い、クライアントへレスポンスを送信する ・レスポンスがクライアント側のブラウザで処理され、結果が表示される |
WebサイトとWebアプリケーションとの相違点
Webサービスには、WebサイトやWebアプリケーション(Webアプリ)も含まれる広範な概念ですが、WebサイトとWebアプリには明確な違いがあります。Webサイトは主に情報を提供する目的で作成され、ユーザーはコンテンツを閲覧したり検索したりといった基本的な操作が中心となります。いわゆるホームページと呼ばれるものはWebサイトの一種であり、静的なページが多く、ユーザーができる操作は限られているのが特徴です。一方、Webアプリケーションはユーザーがシステムと双方向でやり取りをすることを前提としており、より高度で複雑な操作が可能です。例えば、ログイン機能、データの入力・編集・保存、リアルタイムな情報更新、メッセージの送受信などが挙げられます。Webアプリは動的な機能を備え、複雑なシステムで構築されることが一般的で、フロントエンドとバックエンドの開発に加え、データベース設計やAPIの実装なども必要となります。Webサイトは情報発信が主であるのに対し、Webアプリケーションはユーザーとの双方向のコミュニケーションやデータ処理に重点が置かれている点で異なります。
Webサービスの種類
Webサービスは多岐にわたる種類があり、私たちの日常生活のさまざまな場面で活用されています。
【Webサービスの例】
・コミュニケーション
・情報提供
・ショッピング
・決済
・マッチング
・相談
・オンライン会議
・業務効率化
・ストレージ
コミュニケーション関連サービス
コミュニケーション関連サービスは、ユーザー同士がインターネット上で交流を図るためのWebサービスです。身近な例としては、GmailのようなWebメールサービスがあり、インターネット接続があればどこからでもメールの送受信が可能です。X(旧Twitter)、Instagram、FacebookなどのSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)もこの種類に含まれ、メッセージのやり取り、写真や動画の共有、情報の拡散など、多様な形でコミュニケーションを促進しています。チャットワークやSlackのようなビジネスチャットツールも、業務上のコミュニケーションを円滑にするWebサービスとして広く利用されています。これらのサービスは、ユーザー間のつながりを生み出し、情報共有や意思疎通を効率的に行うための基盤となっています。
情報提供型サービス
情報提供型サービスは、ユーザーに対して多様な情報を提供するWebサービスです。ニュースサイトや天気予報サイトなどが典型的な例として挙げられます。これらのサービスは、常に最新の情報を更新し、ユーザーが必要とする情報を迅速に提供しています。例えば、Google検索のような検索エンジンも情報提供型サービスの代表格であり、ユーザーが入力したキーワードに基づいて関連性の高いWebページを瞬時に探し出して提示することで、知りたい情報を簡単に見つけられるという課題を解決しています。地図情報サービスや天気予報サービスのように、無償で提供される情報も多く、私たちの日常生活において欠かせない情報源となっています。
ショッピング関連サービス
ショッピング関連サービスは、インターネットを通じて商品の売買を行うことができるWebサービスです。Amazonや楽天市場といった大手ECサイト(電子商取引サイト)がこれに該当し、ユーザーはオンライン上で商品を選び、購入手続きを進めることが可能です。これらのサービスでは、商品の検索、カートへの追加、注文、そして決済までの一連の流れをWeb上で行うことができます。実店舗に足を運ぶことなく、自宅や外出先から手軽に買い物が楽しめる利便性が大きな特徴であり、多くの消費者に利用されています。
決済関連サービス
決済関連サービスは、Web上での支払いを可能にするWebサービスです。PayPalやStripeといったオンライン決済サービスや、LINEPay、PayPay、楽天ペイなどのQRコード決済サービスが挙げられます。これらのサービスを利用することで、ユーザーはクレジットカード情報などを直接入力することなく、安全かつ迅速にオンライン決済を行うことができます。特に、ECサイトでの買い物や各種サービスの利用時に、決済手段として広く導入されており、利便性の向上に貢献しています。
マッチング関連サービス
マッチング関連サービスは、特定のニーズを持つユーザー同士を結びつけるWebサービスです。例えば、メルカリのようなフリマアプリは、モノを売りたい人と買いたい人を結びつけます。また、食べログのような口コミサイトは、飲食店を探している人と、実際に利用した人の評価や意見を結びつけることで、お店選びの参考情報を提供しています。他にも、求職者と企業、あるいは特定のスキルを持つ個人と依頼者を結びつけるクラウドソーシングサービスなど、多種多様なマッチングサービスが存在します。
相談対応サービス
相談対応サービスは、ユーザーが抱える悩みや疑問に対して、専門家や経験者からのアドバイスや解決策を提供するWebサービスです。オンラインカウンセリングサービスや法律相談サービス、学習塾のオンライン質問サービスなどがこの範疇に含まれます。自宅や好きな場所から専門家と手軽にやり取りができるため、時間や場所の制約を受けずにサポートを受けられる点が大きなメリットです。
オンライン会議用サービス
オンライン会議用サービスは、インターネットを通じて複数のユーザーが同時に音声や映像、テキストでコミュニケーションを取ることを可能にするWebサービスです。ZoomやGoogleMeet、MicrosoftTeamsなどが代表例で、新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、ビジネスシーンだけでなく、教育やプライベートでも利用が拡大しました。画面共有機能やチャット機能、さらにはオンラインでアイデアを共有できるホワイトボード機能など、多岐にわたる機能が搭載されており、離れた場所にいる人同士でも円滑なコミュニケーションを実現します。
業務効率化ツール
業務効率化ツールは、ビジネスにおける様々なタスクやプロセスを効率化するためのWebサービスです。プロジェクト管理ツール、顧客管理システム、勤怠管理システム、経費精算システムなどが含まれます。例えば、かつては手作業で行っていたデータ管理や紙での申請作業などをWeb上で行えるようにすることで、時間や労力の削減、ミスの防止、情報共有の円滑化などを実現します。これらのツールは、企業の生産性向上に大きく貢献しています。
ストレージサービス
ストレージサービスはインターネット上にデータやファイルを保存できるWebサービスです。GoogleDriveやDropbox、OneDriveなどが代表的でユーザーはパソコンやスマートフォンなどのデバイスからいつでもどこでも自分のデータにアクセスできます。データのバックアップや共有が容易になるだけでなくデバイスのストレージ容量を節約できるといったメリットもあります。災害時などのデータ消失リスクの軽減にも役立ち多くのビジネスシーンや個人のデータ管理に活用されています。
Webサービス制作のプロセス
Webサービス制作は、単にシステムを開発するだけでなく、企画から公開後の運営・運用までの一連のプロセスが含まれます。一般的に、Webサービスは以下のような段階を経て制作されます。
ステップ1:戦略の構築
ステップ2:企画書(RFP)の作成
ステップ3:要件の定義
ステップ4:基本設計の構築
ステップ5:詳細設計
ステップ6:構築
ステップ7:テスト運用
ステップ8:サービスの公開
ステップ9:公開後の管理と効果測定
ステップ1:戦略の構築
Webサービスを開発する際には、企画の段階に時間をかけて、丁寧に戦略を構築する必要があります。Webサービスはユーザーに利用してもらうことではじめて価値を生じるものです。そのため、どのように開発するのかだけでなく、「リリース後にどのように運用していくのか」を明確にすることがとても重要です。具体的には、「どのようなユーザーを対象にするのか」「どのようにアプローチするのか」というマーケティングの観点での戦略設計が必要となります。まずは、市場や競合の分析を行ったうえで、ターゲットとコンバージョンへの道筋を明確にし、KPIへと落とし込みましょう。Webサービスの開発には大きなコストと労力が発生するため、スタート地点で十分に戦略を練り、精度を高めておくことが大切です。また、開発は複数のチームで進めるため、価値観や認識を共有するうえでも明確な戦略の設計が行われていたほうがスムーズです。
ステップ2:企画書(RFP)の作成
戦略の構築が完了したら、次に企画書、特にRFP(Request for Proposal:提案依頼書)の作成に進みます。RFPは、Webサービスの開発を外部の制作会社に依頼する際に、自社の要望や依頼事項、期待する内容などを具体的にまとめた文書です。RFPには、Webサービス開発の目的、ターゲットユーザー、提供したい機能、予算、納期、既存システムとの連携要件、そして成果物のイメージなどを詳細に記載します。これにより、複数の制作会社が共通の条件で提案書や見積もりを作成できるようになり、各社の提案内容を比較検討しやすくなります。RFPを準備することで、依頼内容の齟齬を防ぎ、開発プロセスをスムーズに進めるだけでなく、最終的な成果物が期待通りのものになる可能性を高めることができます。RFPの作成には労力を要しますが、成功するWebサービス開発のためには不可欠なステップです。
ステップ3:要件の定義
企画書(RFP)に基づいて、Webサービスに求められる具体的な要件を定義するステップです。この段階では、Webサービスに実装する機能(機能要件)だけでなく、システムの性能、セキュリティ、保守性、運用性といった非機能要件も明確にしていきます。例えば、「ユーザーがログインできること」「商品を検索できること」といった機能面の要件に加え、「ピーク時でもスムーズに動作すること」「個人情報が適切に保護されること」といった非機能面の要件も洗い出します。要件定義は、後の設計や開発工程における手戻りを防ぎ、プロジェクトの方向性を明確にする上で極めて重要です。ユーザーの視点に立ち、どのような体験を提供したいのかを深く掘り下げながら、技術的な実現可能性も考慮して具体的な要件を洗い出し、文書化していきます。
デパートでは、Webサービス開発にすぐに活用いただける、要件定義書のテンプレートを提供しております。ぜひご活用ください。
ステップ4:基本設計の構築
要件定義が完了したら、次にWebサービスの基本設計を構築します。この段階では、Webサービスを実際に具現化するための大まかな設計図を作成します。具体的には、要件定義で洗い出した機能や非機能要件に基づき、システム全体の構成、データベースの構造、ユーザーインターフェース(UI)の骨格、画面遷移などを決定します。機能設計では、どのような機能を実装するのか、その機能がどのように動作するのかを詳細に定義し、機能要件一覧としてまとめます。また、非機能要件に基づき、サーバー構成や運用に関する設計も行います。視覚的に分かりやすくするために、サイトマップやワイヤーフレームといったツールを用いて、Webサービスの全体像をイメージできるようにすることが一般的です。これらの設計は、次の詳細設計や実際の構築作業の基盤となるため、非常に重要な工程となります。
ステップ5:詳細設計のステップが必要
基本設計で定められた内容をさらに具体化し、開発者がプログラミングを進められるレベルまで落とし込むのが詳細設計のステップです。この段階では、個々の機能がどのように動作するか、どのデータがどのように処理されるか、各コンポーネントがどのように連携するかなど、システムの内部的な構造や動作を細部まで定義します。例えば、各画面のレイアウト、ボタンの配置、入力フィールドの種類といったUIの詳細や、データベースのテーブル定義、APIの仕様、エラー処理のロジックなどを具体的に記述します。プログラミング言語やフレームワークの選定もこの段階で行われることが多く、開発の効率性や将来的な拡張性も考慮しながら設計を進めます。詳細設計が適切に行われることで、開発段階での認識の齟齬や手戻りを減らし、高品質なWebサービスの構築につながります。
ステップ6:構築
詳細設計が完了したら、いよいよWebサービスの構築(開発)フェーズに入ります。この段階では、設計書に基づいて実際にプログラミングを行い、Webサービスを形にしていきます。大きく分けて、ユーザーが直接目にして操作する部分であるフロントエンド開発と、データの処理や保存、サーバーとの通信など、ユーザーからは見えない裏側の処理を行うバックエンド開発に分かれます。フロントエンド開発では、HTML、CSS、JavaScriptなどを用いて、Webブラウザに表示される画面やデザインを組み立てます。一方、バックエンド開発では、PHP、Ruby、Pythonなどのサーバーサイド言語を用いて、データベースとの連携やビジネスロジックの実装を行います。また、サーバーの構築やデータベースの準備もこの段階で行われます。必ずしもゼロから全てを開発するのではなく、既存のフレームワークやライブラリを活用して効率的に開発を進めることも一般的です。この構築フェーズは、Webサービスの機能や性能を左右する重要な工程であり、品質と効率性を両立させることが求められます。
ステップ7:テスト運用
構築が完了したWebサービスは、公開前に必ずテスト運用を実施します。このステップでは、開発したWebサービスが設計通りに動作するか、不具合やバグがないか、ユーザー体験が損なわれていないかなどを多角的に検証します。具体的には、機能テスト、性能テスト、セキュリティテスト、ユーザビリティテストなどを行います。機能テストでは、個々の機能が意図通りに動作するかを確認し、性能テストでは、多数のユーザーが同時にアクセスした場合でもシステムが安定して動作するかを検証します。セキュリティテストでは、不正アクセスや情報漏洩のリスクがないかを確認し、ユーザビリティテストでは、実際のユーザーが利用する視点から操作性や使いやすさを評価します。テスト運用で見つかった問題点は速やかに修正し、品質を確保することが、成功するWebサービスには不可欠です。
ステップ8:サービスの公開
テスト運用を経て品質が確保されたら、Webサービスの公開(リリース)です。このステップでは、開発したWebサービスをインターネット上にデプロイし、一般のユーザーが利用できる状態にします。具体的には、Webサーバーへのプログラムの配置、データベースとの接続設定、ドメインの取得と設定、SSL証明書の導入などを行います。サービスの公開は、これまで企画・開発してきたWebサービスが実際にユーザーの目に触れる瞬間であり、非常に重要な節目となります。公開後も、安定稼働を維持するための監視や、万が一のトラブル発生時に迅速に対応できる体制を整えておくことが不可欠です。
ステップ9:公開後の管理と効果測定
Webサービスは、公開したら終わりではありません。公開後も継続的な管理と効果測定を行うことで、サービスを改善し、ユーザーにとってより価値のあるものへと成長させていく必要があります。この段階では、Webサービスの運用状況を監視し、サーバーの負荷状況、システムのパフォーマンス、セキュリティの状態などを定期的に確認します。アクセスログや利用状況のデータを収集し、ユーザーの行動や利用傾向を分析します。例えば、どの機能がよく利用されているのか、どのページで離脱が多いのかなどを把握することで、改善点や新たな機能のアイデアを見つけ出すことができます。ユーザーからのフィードバックも積極的に収集し、サービスの改善に役立てます。これにより、Webサービスはリリース後もユーザーニーズに合わせて進化し続け、長期的な成功へとつながるのです。
Webサービスの企画を成功させるためのポイント
Webサービスを成功させるうえでは、企画段階でどれだけ明確なビジョンを持てるかが重要なカギを握ります。ここでは、より良いWebサービスを企画するための基本的なポイントについて解説します。
課題を具体的に捉える

Webサービスの企画を成功させるためには、まず解決したい課題を具体的に捉えることが非常に重要です。漠然としたアイデアではなく、「どのようなユーザーの」「どのような悩みを」「どのような技術や機能で解決するのか」を明確に言語化する必要があります。例えば、日々の生活やビジネスの中で「困っていること」や「もっとこうなったら便利なのに」と感じる課題に焦点を当てることで、ユーザーに本当に必要とされるサービスが生まれる可能性が高まります。この課題が明確であればあるほど、開発に関わる全ての関係者がサービスの必要性を深く理解し、共通の目的意識を持ってプロジェクトを進めることができます。具体的な課題設定は、サービスの方向性を定め、開発プロセス全体を円滑に進めるための最初の、そして最も重要な一歩となるでしょう。
ユーザー目線で考える

Webサービスの企画において、ユーザー目線で考えることは成功のための不可欠な要素です。開発者が「良い」と考えるサービスが、必ずしもユーザーにとって「良い」とは限りません。ユーザーがどのような目的でサービスを利用するのか、どのような操作を求めるのか、どのような情報が必要なのかを深く理解することが重要です。ユーザーの行動パターンや思考プロセスを想定し、使いやすさ、分かりやすさ、楽しさといった視点からサービス設計を行うことで、ユーザーに愛され、継続的に利用してもらえるサービスが生まれます。例えば、画面のデザインや遷移、機能の配置など、細部にわたってユーザーの視点を取り入れることで、直感的でストレスのないユーザー体験を提供できるようになります。このユーザー目線を常に持ち続けることが、Webサービスを成功に導く鍵となります。
調査に時間をかける

Webサービスの企画を成功させるためには、徹底的な調査に時間をかけることが極めて重要です。市場調査では、ターゲットとなる市場の規模、成長性、トレンドなどを把握し、自社のWebサービスが参入する価値があるかを評価します。競合調査では、競合他社がどのようなサービスを提供しているのか、どのような強みや弱みがあるのかを分析し、自社のWebサービスがどのように差別化できるかを検討します。また、ユーザーニーズ調査も不可欠で、アンケートやインタビュー、ユーザーテストなどを通じて、潜在的なユーザーがどのような課題を抱え、どのような解決策を求めているのかを深く理解します。これらの調査を綿密に行うことで、客観的なデータに基づいた根拠のある企画を立てることが可能となり、サービスの方向性を誤ることなく、市場で成功する可能性を高めることができます。十分な調査なくして、ユーザーに本当に必要とされるWebサービスは生まれないでしょう。
Webサービスを制作会社に外注するときのポイント
明確な目的と目標を共有する
まず、最も重要なのは、サービスの目的と達成したい目標を制作会社と明確に共有することです。例えば、「売上を〇%向上させる」「顧客満足度を〇%改善する」といった具体的な数値目標や、「どのようなユーザーに、どのような体験を提供したいのか」というビジョンを事前に言語化し、制作会社とすり合わせることで、認識の齟齬を防ぎ、目指すべき方向性を共有できます。
制作会社の実績を確認する
次に、制作会社の選定も非常に重要です。過去の実績や得意分野を確認し、自社のWebサービスと類似する分野での開発経験があるか、技術力は十分かなどを総合的に評価しましょう。また、提案内容だけでなく、コミュニケーションの円滑さや、担当者の熱意なども判断基準に含めることをおすすめします。信頼できるパートナーと巡り合うことが、円滑な制作進行と高品質なWebサービスの完成につながるからです。
綿密な要件定義を行う
さらに、契約内容と要件定義の徹底も欠かせません。契約書には、開発範囲、納期、費用、支払い条件、知的財産権の帰属などを明確に記載し、曖昧な点をなくすことが大切です。特に、要件定義は、後の開発工程に大きな影響を与えるため、制作会社と綿密に打ち合わせを行い、機能や仕様を具体的に落とし込むようにしましょう。これにより、開発途中の手戻りを減らし、予算オーバーや納期遅延のリスクを低減することができます。
徹底した進行管理を行う
最後に、制作の進行中は定期的な進捗確認とフィードバックを密に行うことが重要です。進捗報告会やデモンストレーションなどを通じて、開発状況を把握し、必要に応じて軌道修正を行うことで、最終的な成果物が期待通りのものになる可能性が高まります。
まとめ
Webサービスは、インターネットを通じて様々な機能や情報を提供する、私たちの生活に欠かせない存在です。WebサイトやWebアプリケーションとの違いを理解し、その企画から開発、そして公開後の運用までのプロセスを適切に進めることが、成功への鍵となります。今回解説したWebサービスの定義、多様な種類、具体的な開発事例、そして企画・開発のステップは、これからWebサービスに関わろうとしているビジネスパーソンや個人にとって、実践的な指針となるでしょう。特に、Webサービスを企画する際には、課題の具体化、ユーザー目線での思考、そして十分な調査に時間をかけることが不可欠です。また、Webサービスの制作を外部の専門会社に外注する際には、目的や要件を明確にし、コミュニケーションを密に取ることで、期待通りの成果を得られる可能性が高まります。
株式会社デパートでは、中小規模のサービス開発からエンタープライズの基幹システム開発まで、さまざまな実績を持つプロジェクトマネージャーを中心に、Webサービスの設計から開発、運用保守まで幅広く対応させていただいております。 「Webサービスを考えている」「そろそろ自社サービスが必要かもしれない」などご要望がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
Contact
制作のご依頼やサービスに関するお問い合わせ、
まだ案件化していないご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
- この記事をシェア